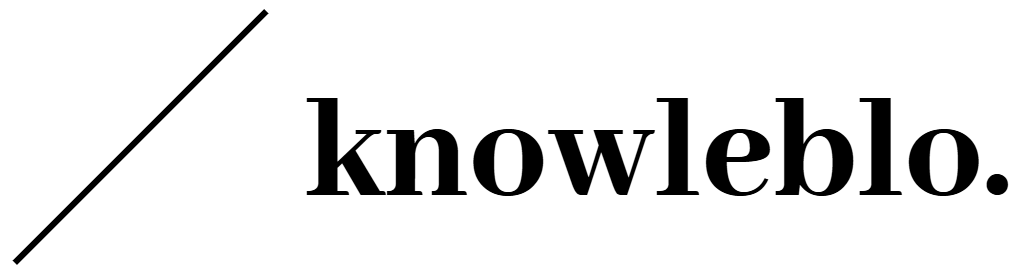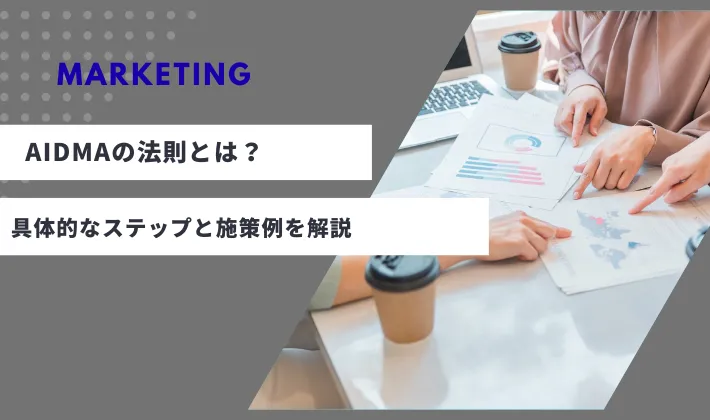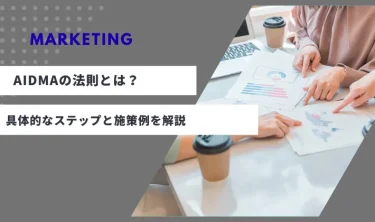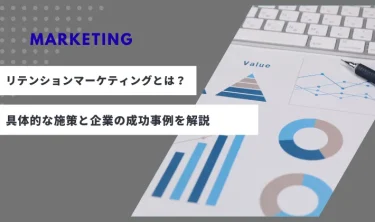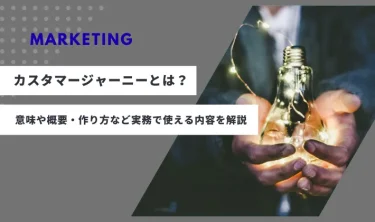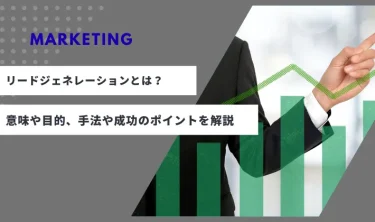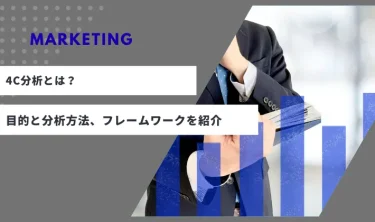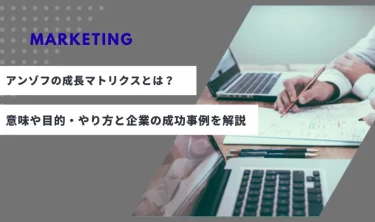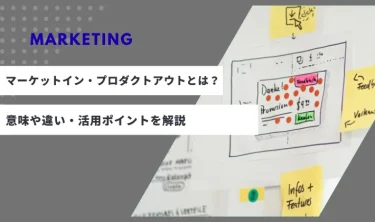マーケティング施策を考えるうえで欠かせないのが「購買心理の理解」です。
その基礎となるフレームワークが「AIDMA(アイドマ)の法則」です。消費者が商品を認知してから購入に至るまでの心理プロセスを体系化したもので、広告戦略や販売促進、Webマーケティングなど幅広い分野で活用されています。
本記事では、AIDMAの法則の意味や成り立ちから、各ステップの内容、現代の購買行動との違い、具体的な活用方法までを詳しく解説します。
マーケティング初心者でも理解できるように、図表を交えながら実践的に紹介します。
AIDMAの法則とは
AIDMA(アイドマ)の法則とは、1920年代にアメリカの広告研究家サミュエル・ローランド・ホール(S.R. Hall)によって提唱された、購買心理モデルです。
消費者が商品を認知してから購入に至るまでの心理を「Attention(注意)」「Interest(興味)」「Desire(欲求)」「Memory(記憶)」「Action(行動)」の5段階に分けて説明します。
このモデルは、主にテレビCMや店頭広告などのマス広告時代に確立された理論ですが、現在もWebマーケティングやSNS施策など、あらゆる購買行動の基盤として活用されています。
次章では、AIDMAの各プロセスをより詳しく見ていきましょう。
AIDMAの5つのステップ
AIDMAの法則は、消費者が購入を決定するまでの心理を段階的に表したものです。
それぞれのステップがどのような意味を持ち、どんな施策と結びつくのかを具体的に解説します。
| 段階 | 英語表記 | 意味・目的 |
|---|---|---|
| ①注意 | Attention | 商品やサービスの存在を認識させる段階 |
| ②興味 | Interest | 「もっと知りたい」と思わせる段階 |
| ③欲求 | Desire | 「使ってみたい」「欲しい」と思わせる段階 |
| ④記憶 | Memory | 購買を検討するために記憶に残す段階 |
| ⑤行動 | Action | 実際に購入・申し込み・問い合わせを行う段階 |
購買行動の初期段階では「Attention」や「Interest」を引きつける広告やビジュアルが重視されます。
一方、終盤の「Memory」や「Action」では、口コミ・比較表・レビューなど、意思決定を後押しする情報提供が重要になります。
AIDMAの法則を活用するメリット
AIDMAの法則を理解し活用することで、マーケティング活動全体の質が向上します。特に、施策の設計や効果測定において大きなメリットがあります。
まず、消費者の購買プロセスを可視化できる点が挙げられます。顧客がどの段階で離脱しているかを把握できれば、改善すべきポイントが明確になります。たとえば、広告のクリック率は高いのに購入率が低い場合、Interest以降の施策に課題があると判断できます。
次に、施策設計の抜け漏れを防げる点です。AIDMAのフレームに沿って施策を整理すると、「認知は獲得できているが、欲求を喚起するコンテンツが不足している」といった課題が見えてきます。広告、LP、メルマガ、SNS投稿など複数の施策を一貫性を持って設計できるようになります。
また、チーム内での共通言語ができる点も重要です。マーケティング部門、営業部門、広報部門など、異なる役割を持つメンバーが「今はAttention強化に注力すべき」といった形で、同じ認識を持って議論できます。これにより、部門間の連携がスムーズになり、施策の精度が高まります。
さらに、AIDMAは古典的な理論でありながら、デジタルマーケティングにも十分応用可能です。検索広告で認知を獲得し、ランディングページで興味と欲求を喚起し、リターゲティング広告で記憶を定着させ、CTAで行動を促すという一連の流れは、まさにAIDMAそのものです。
AIDMA各ステップの詳細と施策例
AIDMAの各段階について、より具体的に見ていきましょう。
それぞれのフェーズで消費者がどのような状態にあり、どんな施策が効果的かを理解することで、実務での活用がしやすくなります。
STEP1 Attention(注意) | まず気づいてもらう
Attentionは、消費者に商品やサービスの存在を認識してもらう段階です。情報が溢れる現代では、この最初の接点で印象を残せなければ、その後の購買プロセスに進むことはありません。
具体的な施策としては、テレビCM、Web広告、SNS投稿、検索エンジン広告などが挙げられます。視覚的なインパクトが重要になるため、色使いやキャッチコピー、画像選定に工夫が必要です。たとえばYouTube広告では、最初の5秒で視聴者の興味を引けなければスキップされてしまいます。そのため、冒頭で結論や強いメッセージを伝える設計が効果的です。
また、検索広告では広告文の見出しに数字や問いかけを入れることで、クリック率の向上が期待できます。「3分でわかる」「初心者でも簡単」といった具体的な表現が、ユーザーの注意を引きつけます。
STEP2 Interest(興味) | もっと知りたいと思わせる
Interestは、消費者が「この商品についてもっと知りたい」と感じる段階です。注意を引いた後、興味を深めてもらえなければ、すぐに離脱されてしまいます。
ここで有効なのは、商品の特徴や機能、利用シーンを具体的に伝えるコンテンツです。たとえば、ランディングページでは商品の詳細説明、導入事例、ユーザーの声などを配置します。BtoBビジネスであれば、業界別の活用事例や課題解決のストーリーを紹介することで、読者の関心を引きつけられます。
また、ブログ記事やホワイトペーパーなどの情報提供型コンテンツも効果的です。「○○の選び方」「失敗しない△△の方法」といったノウハウ記事を通じて、読者の知識欲を満たしながら自社商品への興味を育てることができます。
STEP3 Desire(欲求) | 使ってみたいと感じさせる
Desireは、消費者が「自分もこれを使ってみたい」「購入したい」と感じる段階です。興味を持った顧客の感情を動かし、購買意欲を高めることが目的です。
この段階では、商品を使うことで得られる具体的なメリット(ベネフィット)を明確に伝えることが重要です。単なる機能説明ではなく、「この商品を使うことで、あなたの生活や仕事がどう変わるか」を想像させる表現が効果的です。たとえば、「作業時間が半分になる」「月1万円のコスト削減が可能」といった具体的な数値を示すと、説得力が増します。
また、高品質な商品写真や動画、実際の利用者のビフォーアフター事例なども欲求を刺激します。期間限定キャンペーンや初回割引といった特典情報も、購買意欲を高める有効な手段です。
STEP4 Memory(記憶) | ブランドを覚えてもらう
Memoryは、消費者の記憶に商品やブランドを定着させる段階です。多くの場合、消費者はその場ですぐに購入を決めるわけではありません。検討期間を経て購入に至るため、その間ブランドを記憶してもらう必要があります。
具体的な施策としては、リターゲティング広告、メールマガジン、SNSでの定期発信などが挙げられます。一度Webサイトを訪問したユーザーに対して、Facebook広告やGoogle広告で再度商品を表示することで、記憶の定着を促せます。
また、ブランドの視覚的な統一感も重要です。ロゴ、カラー、フォント、トーン&マナーを一貫させることで、複数の接点でも同じブランドとして認識されやすくなります。定期的な情報発信を通じて、消費者の選択肢の中に自社ブランドを残し続けることが、最終的な購買につながります。
STEP5 Action(行動) | 購入や申し込みを後押しする
Actionは、消費者が実際に購入、問い合わせ、資料請求といった具体的な行動を起こす段階です。ここまで育ててきた購買意欲を、確実に行動に変えることが最終目標です。
Webサイトでは、CTA(Call To Action)ボタンの配置や文言が重要になります。「今すぐ購入する」「無料で資料請求」「初回限定で申し込む」といった明確で具体的な表現が、行動を促します。ボタンの色やサイズ、配置場所も効果に影響するため、A/Bテストを行いながら最適化することが推奨されます。
また、購入までのステップをできるだけシンプルにすることも大切です。入力フォームの項目を減らす、決済方法を複数用意する、配送料を明示するなど、ユーザーの不安や手間を取り除く工夫が、コンバージョン率の向上につながります。
AIDMAとAISASの違い
AIDMAがマス広告時代の購買モデルであるのに対し、AISAS(アイサス)の法則はインターネット時代の行動様式に対応したモデルです。
| 法則名 | ステップ構成 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| AIDMA | 注意→興味→欲求→記憶→行動 | 店舗・広告などオフライン中心。企業主導の購買行動 |
| AISAS | 注意→興味→検索→行動→共有 | インターネット・SNS中心。消費者主導の情報共有 |
現代では、AIDMAとAISASを組み合わせて考えることが主流です。
たとえば、SNSでの「興味→検索→購入→レビュー投稿」という流れは、まさに両モデルが融合した購買行動といえます。
その他の購買行動モデル
マーケティングではAIDMA以外にも多様な購買心理モデルが存在します。
代表的なものを比較すると次のようになります。
| モデル名 | 特徴 |
|---|---|
| AIDA | AIDMAの原型。Attention→Interest→Desire→Actionの4段階 |
| AISCEAS | 検索(Search)や比較(Comparison)を重視したデジタル時代の購買モデル |
| DECAX | コンテンツマーケティングに適した最新モデル。共感(Empathy)や体験共有(Experience)を重視 |
| SIPS | ソーシャルメディア時代の消費行動。共感→確認→参加→共有という流れ |
これらのフレームワークを理解することで、AIDMAの限界や発展的な活用方法も見えてきます。
AIDMAの法則の活用事例
AIDMAの考え方は、業種を問わずさまざまな場面で活用されています。
以下に、BtoCとBtoBそれぞれの活用例を紹介します。
事例①:化粧品メーカーのマーケティング
テレビCMで「Attention」を獲得し、SNSで詳細情報を発信して「Interest」を醸成。 体験モニターキャンペーンで「Desire」を刺激し、店舗購入やEC購入へ誘導するという流れです。 購入後も口コミを促し、「Memory」を維持する仕組みを構築しています。
事例②:BtoBサービス企業のリード獲得
検索広告で「Attention」を獲得し、ホワイトペーパーで「Interest」と「Desire」を喚起。 無料相談フォームを設置し「Action」へ誘導。 さらに、メールマガジンで定期的にナーチャリングを行い、「Memory」を強化しています。
AIDMAを基盤に設計することで、顧客行動を可視化し、離脱防止施策を一貫して設計できます。
AIDMAの法則は古い?現代での位置づけ
一部では「AIDMAは時代遅れ」と言われることもあります。
しかし、購買心理の基本構造は今も変わりません。「Attention」や「Interest」の重要性は、むしろ情報過多の現代でさらに高まっています。
SNSや検索エンジンが発達した今、AIDMA単体では不十分な部分をAISASやDECAXが補っています。
つまり、AIDMAは購買心理の原点として活用しつつ、現代型モデルと組み合わせて使うことが最適解です。
まとめ
AIDMAの法則は、消費者の購買行動を理解するための古典的かつ普遍的なモデルです。Attention(注意)からAction(行動)までの心理プロセスを把握すれば、マーケティング施策の精度を高めることができます。
現代ではAIDMAに加え、AISASやDECAXなどのデジタル時代に即したモデルを組み合わせることで、より多角的な施策設計が可能になります。
購買心理のフレームを理解し、戦略に落とし込むことが、成果を生み出す第一歩となるでしょう。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。