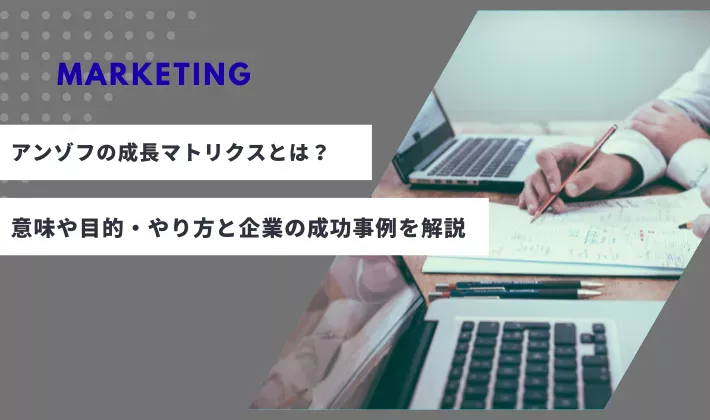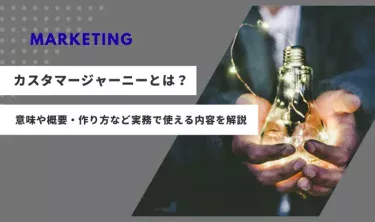アンゾフの成長マトリクスとは、企業の成長戦略を検討するための古典的なフレームワークです。市場(顧客層)と製品(商品・サービス)という2軸で成長方向性を分析し、「既存」と「新規」の組み合わせから4つの戦略オプションを導き出します。1960年代に経営学者イゴール・アンゾフ(Igor Ansoff)によって提唱され、業種を問わず多くの企業で活用されてきました。
この記事では、アンゾフの成長マトリクスの基本概念や4つの戦略、企業事例、そして実際の活用方法までをわかりやすく解説します。経営戦略に悩むマーケティング担当者の方が、本記事を読むことで、自社の成長戦略を考えるヒントを得られるでしょう。
アンゾフの成長マトリクスとは
アンゾフの成長マトリクスは、縦軸に「市場」、横軸に「製品」をとり、それぞれを「既存」「新規」の2区分に分けてマトリクス状に整理したフレームワークです。
この4象限の組み合わせによって、企業が取り得る成長戦略の選択肢を網羅的に洗い出すことができます。もともとはアンゾフが著書『企業戦略論(Corporate Strategy)』の中で紹介したもので、「事業拡大マトリクス」とも呼ばれます。
このマトリクスでは、縦軸・横軸それぞれの「既存」「新規」の組み合わせに応じて以下の4つの戦略が定義されます。
- 市場浸透戦略(既存市場×既存製品)
- 市場開拓戦略(新規市場×既存製品)
- 製品開発戦略(既存市場×新規製品)
- 多角化戦略(新規市場×新規製品)
各戦略の名称から、どういった方向性の成長を目指すものかが理解できるでしょう。
一般に、左上の「市場浸透戦略」が最もリスクが低く実行しやすく、右下の「多角化戦略」が最もリスクが高いとされています。次章では、アンゾフの成長マトリクスが具体的にどのような場面で役立つのかを見ていきます。
アンゾフの成長マトリクスが活用される場面
アンゾフの成長マトリクスは、自社の事業状況や目標に応じて柔軟に活用できる汎用的なツールです。
特に、次のような場面で現状を打開するためのヒントを与えてくれるでしょう。
事業が伸び悩んでいる場合
既存事業の成長が鈍化している、あるいは市場自体が成熟・縮小して売上が頭打ちになっている場合には、アンゾフの成長マトリクスが現状打破の策を検討するのに役立ちます。4つの戦略オプションのうちどれに注力すればよいかを見極めることで、現状に最適な成長戦略とそのリスクレベルを把握できます。
例えば自社がこれまで既存市場・既存製品の延長で成長してきたなら、新たな市場開拓や製品開発に挑戦すべきタイミングかもしれません。マトリクスを用いて各方向性の可能性を検証することで、停滞打破のヒントが得られるのです。
ビジネスモデルを再検討したい場合
既存事業のビジネスモデルをブラッシュアップしたいときにも、アンゾフの成長マトリクスは有効です。事業戦略の見直しでは、自社を取り巻く外部環境の変化に目を向けることが重要です。アンゾフのマトリクスは「市場」と「製品」の視点で外部環境要因を整理するため、現行ビジネスに影響を与える要素を俯瞰できます。
例えば新技術の台頭で市場ニーズが変化していないか、新規参入すべき顧客層はないか、といった点を洗い出すことができます。こうして自社ビジネスモデルの再構築に向けた施策を検討しやすくなるでしょう。
新規事業を計画するとき
まったく新しい事業アイデアのプランニングにも、このマトリクスが活用されています。ゼロから新規事業を立ち上げる際にはリスクが伴いますが、アンゾフの成長マトリクスを使って市場軸・製品軸で外部環境を分析することで、事前にリスク要因を洗い出すことができます。
例えば、新事業のターゲット市場が自社にとって未知の領域であれば、市場開拓戦略としての課題や競合状況を把握できます。また、自社に無い新製品を投入する場合には技術開発や投資コストの面での課題が見えてくるでしょう。事前に障害を予測し対応策を講じることで、新規事業の成功確率を高めることが期待できます。
アンゾフの成長マトリクスの4つの戦略
それでは、アンゾフの成長マトリクスから導かれる4つの成長戦略について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
各戦略の基本的な考え方と具体例、リスクの大きさの特徴を解説します。
市場浸透戦略(既存市場×既存製品)
市場浸透戦略は、現在扱っている既存製品で、今まで通りの既存市場に対してさらなる成長を図る戦略です。言い換えれば、今の製品を今の市場でもっと売ることでシェア拡大や売上増加を目指します。
具体的な施策としては、既存顧客の購買頻度や購入単価を高めるマーケティング施策、販売チャネルの強化、プロモーションによる需要喚起などが挙げられます。
新たな開発投資を伴わない分、4戦略の中では最もリスクやコストが低い戦略とされています。
飲料メーカーのサントリーは若者のウイスキー離れに直面した際、既存商品であるウイスキーの新たな飲み方として「ハイボール」を提案しました。同社は専用ジョッキの配布や飲み方のPRキャンペーンを展開し、若年層にウイスキーを浸透させることで売上を大きく伸ばしました。これは市場浸透戦略によって既存市場の需要を喚起し、成果を上げた成功事例です。
市場開拓戦略(新規市場×既存製品)
市場開拓戦略は、今ある既存製品を新しい市場に投入する戦略です。地理的に未進出の地域や、新たな顧客セグメントなど、これまでアプローチしてこなかった市場を開拓します。
たとえば国内限定の商品を海外市場で販売する、あるいは子供向けだった商品を大人向けにも展開するといった施策が該当します。
市場開拓戦略は見込みのある新市場を見極めるための調査やマーケティングが必要なため、市場浸透よりリスクやコストが高くなる傾向があります。しかし成功すれば売上の大幅拡大につながる可能性があり、企業成長のための重要な選択肢です。
牛丼チェーンの吉野家は、日本国内で培ったビジネスを中華圏という新市場に展開しました。当初、牛丼は現地で馴染みの薄い料理でしたが、あえて高級路線の価格設定や内装で出店する戦略を取り、現地顧客の支持を獲得しています。その結果、北京で「消費者がもっとも愛するブランド」に選ばれるなど、中華圏での事業拡大に成功しました。吉野家のケースは市場開拓戦略によって新市場への進出を果たした事例と言えるでしょう。
製品開発戦略(既存市場×新規製品)
製品開発戦略は、現在の既存市場(既存顧客層)のニーズに合わせて新しい製品やサービスを開発する戦略です。すでに自社が持つ市場で培った顧客理解や販売チャネルを活用しつつ、新商品の投入によってさらなる成長を図ります。
例えば、既存商品のアップグレード版や関連商品の開発、新サービスの付加などがこれに当たります。
製品開発には研究開発投資や設備投資が伴うため、市場浸透戦略よりハイリスク・高コストである点が特徴です。しかし、自社ブランドへのロイヤルティがある市場での新商品投入は、需要を的確に捉えれば大きなリターンをもたらす可能性があります。
即席麺メーカーのまるか食品は主力製品「ペヤングソース焼きそば」で製品開発戦略を積極的に展開しました。同社は既存の焼きそば市場において、チョコレート味や納豆入りなどインパクトの強い新フレーバーの商品を次々と発売。これら奇抜な新商品はSNSで話題となり、結果的にペヤングブランドの認知度向上と売上拡大につながりました。このように既存顧客層に響く新商品を送り出すことで、市場シェアを拡大した好例です。
多角化戦略(新規市場×新規製品)
多角化戦略は、自社にとって新しい市場に新しい製品を投入して事業拡大を図る戦略です。既存事業と関連性の低い領域に乗り出すことになるため、4つのオプションの中で最もリスクが高い挑戦となります。
しかし、事業ポートフォリオを多角化することで既存事業の衰退リスクを分散できるメリットもあります。全く新規の分野に進出するため、必要な技術や知見の不足、市場での無名性など課題も多いですが、成功すれば企業に新たな収益源をもたらします。
富士フイルムは写真フィルム事業で培った技術を活かし、全く異なる分野への多角化に成功した企業です。同社はデジタルカメラの普及で主力の写真フィルム需要が急減した2000年代、フィルムの化学技術を応用できる新規領域を模索しました。その結果、ヘルスケア(医薬・化粧品)事業に進出し、大きな成果を収めています。例えばフィルム製造で培ったコラーゲンの酸化抑制技術を活かして化粧品ブランドを立ち上げるなど、新市場×新製品への大胆な挑戦で事業転換に成功しました。このように多角化戦略はリスクこそ高いものの、企業存続と成長のブレークスルーとなるケースがあります。
多角化戦略の4つの種類
一口に「多角化戦略」と言っても、その進め方にはいくつかパターンがあります。
アンゾフ自身も第4象限の多角化戦略をさらに4種類に分類しており、企業がどのように新規分野へ乗り出すかの方向性を示しています。
水平型多角化
自社の既存技術・強みを活用し、現在の顧客層に近い市場へ新製品を提供するタイプの多角化です。比較的リスクが低く、シナジーが得られやすい戦略です。
例として、自動車メーカーが自社のエンジン技術を活かしてバイク製造を開始するケースなどが挙げられます。
既存の技術基盤と顧客に近い分野であるため、比較的スムーズに展開できるでしょう。
垂直型多角化
既存事業のバリューチェーン上で前後に広がる形の多角化です。つまり、現在の事業と関連する上流・下流分野に新規参入するケースを指します。
例えば、コーヒーショップ運営企業がコーヒー豆の自社栽培・販売を新事業として始める場合などがあります。
自社の取引先や顧客に近い市場を狙うためブランドや信頼を活かせますが、新たな設備投資やノウハウ習得が必要となりリスクはやや高まります。
集中型多角化
自社の中核技術やノウハウと高い関連性を持つ分野へ進出する多角化です。既存の強みを新分野に応用することで比較的成功率を高められる戦略です。
例として、カメラメーカーが医療用内視鏡やレンズを開発するケース、ペットフードメーカーの技術を活かしてベビーフード事業に乗り出すケースなどがあります。
新分野でヒットを生めば大きな成長が見込めますが、専門領域が変わる分だけリスクも小さくはありません。
集成型多角化
自社の既存事業との関連性がほとんどない全く新しい分野に挑む多角化です。シナジー効果は期待しにくいものの、思い切ったポートフォリオ転換によってリスク分散を図る戦略と言えます。
例えば、食品メーカーが金融事業に参入するといったように、業種が大きく異なる分野への進出が典型です。他の3種類と比べても最もリスクが高いですが、既存事業が衰退した際の保険として全く別の収益源を確保できる点がメリットです。
企業が多角化戦略を検討する際は、自社の強みとの関連度合いやリスク許容度に応じて、これら4つのタイプのどの方向で多角化するかを判断します。関連性が高いほど成功確率は上がりやすく、無関連の分野ほど慎重な見極めが求められるでしょう。
アンゾフの成長マトリクスを活用するメリット
アンゾフの成長マトリクスを企業戦略の策定に取り入れることで、以下のようなメリットが得られます。
成長戦略の選択肢を網羅的に発見できる
マトリクスを使うことで、自社の成長方向を「市場×製品」の組み合わせで体系的に整理できます。
抜け漏れなく戦略オプションを洗い出せるため、従来の延長線上では気づかなかった成長の機会を見つけるのに役立ちます。結果として、短期・中長期それぞれで取り得る戦略の全体像が明確になります。
経営資源を効果的に配分できる
4象限で方向性を比較検討することで、自社の人材・資金・技術といった経営資源をどの戦略に投入すべきか判断しやすくなります。
例えば、安全性の高い市場浸透に資源を集中するのか、将来性を見据えて新市場開拓にも投資するのか、意思決定の指針が得られます。
限られたリソースを最適に活用し、成長効率を高められる点がメリットです。
戦略ごとのリスクとリターンを可視化できる
マトリクス上に4戦略をプロットすることで、各オプションのリスクの大きさや期待されるリターンを比較できます。
一般に「市場浸透 ⇒ 市場開拓 ⇒ 製品開発 ⇒ 多角化」の順でリスクが高まるため、自社の状況に応じたリスク許容度で戦略を選択できます。
また、新規市場・新規製品に踏み出す難易度も事前に認識でき、無謀な挑戦を避けるブレーキにもなります。
戦略を社内で共有しやすい
2×2のシンプルなマトリクス図によって戦略全体像を表現できるため、経営層から現場まで共通認識を持ちやすくなります。
視覚的に整理されたフレームワークはプレゼン資料などにも活用しやすく、チームで戦略を議論・合意する土台として有用です。複雑な事業環境をシンプルな図で捉えることで、戦略立案プロセスがスムーズになる効果も期待できます。
アンゾフの成長マトリクスの作り方・活用方法
アンゾフの成長マトリクスを実際に自社で活用するには、以下の手順で進めるとスムーズです。
自社の現状分析からアイデア創出まで、チームで協力して取り組みましょう。
- STEP1:市場ニーズの調査
- STEP2:戦略立案メンバーの招集
- STEP3:アイデアの整理と戦略策定
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP1:市場ニーズの調査
まずは市場のニーズを調べることから始めます。マトリクスの縦軸は「市場」ですから、現在の市場環境や顧客ニーズの把握は欠かせません。いくら魅力的な事業アイデアでも、市場に需要がなければビジネスは成り立たないためです。
具体的には、既存市場の動向や顧客満足度、新規に参入を検討する市場の規模や成長性などを調査します。必要に応じてアンケート調査やヒアリングを行い、顧客が求める商品・サービスや不満を洗い出しましょう。
市場ニーズが明らかになったら、その情報をマトリクスの各象限で検討する材料としてメモしておきます。例えば「既存市場にまだ満たされていないニーズはないか」「新規市場(未開拓の顧客層)に自社製品を求める声はあるか」など、仮説を立てる土台を作ります。
STEP2:戦略立案メンバーの招集
次に、戦略立案のメンバーを集める段階です。成長戦略のアイデア出しや検討は、一人よりも複数人で行ったほうが多角的な視点が得られます。自分一人で考えると発想が偏ったり非現実的な戦略になりがちなので、指摘し合える仲間が必要です。集めるメンバーは、できれば社内の様々な部門から選びましょう。
特に「ヒト・モノ・カネ」の経営資源に詳しい人がチームにいると、新商品の開発可能性や必要なリソースについて現実的な議論ができます。
例えば、営業担当から市場の生の声を聞いたり、技術担当から製品開発の見通しを確認したりすることで、戦略アイデアの実現性が高まります。多様な知見を持つメンバーでチームを構成し、戦略立案の準備を整えましょう。
STEP3:アイデアの整理と戦略策定
最後に、チームでブレインストーミングを行い成長戦略のアイデアをできるだけ多く出すステップです。集めたメンバーで各象限ごとに取り得る施策を自由に挙げてみます。
この段階では実現可能性は一旦脇に置き、柔軟な発想でアイデアを出し合うことがポイントです。ブレストの場では以下のルールを意識すると、活発な議論が進みます。
- 他の人がアイデアを話している間は否定や批判をしない
- 実現性は気にせず、斬新な発想を歓迎する
- 質より量を重視し、できるだけ多くのアイデアを出す
- 他人のアイデアに自分のアイデアを足して発展させる(足し算の発想)
こうしたルールのもとで各象限にアイデアを書き出し、マトリクス上に整理します。
例えば「既存市場×既存製品」では「既存顧客の購入頻度アップ施策」「顧客ロイヤルティプログラム強化」など、「新規市場×新規製品」では「○○分野に参入して新事業立ち上げ」など、ブレインストーミングの結果を埋めていきます。アイデア出しの後は、それぞれの戦略オプションの実現可能性や投資対効果を評価しましょう。
市場ニーズとの合致度、自社の強みとのフィット、必要なコストや時間などの観点から検討し、優先順位をつけます。最終的に有望な戦略プランを選定したら、具体的なアクションプランに落とし込みを行います。ここまでのプロセスを経ることで、アンゾフの成長マトリクスを実践に結びつけることができます。
アンゾフの成長マトリクスの企業事例
アンゾフの成長マトリクスは多くの企業で戦略立案に活用されてきました。その中から、日本企業の代表的な成功事例を2つ紹介します。
富士フイルム株式会社
前述のように、富士フイルムは写真フィルム需要の激減という危機に対し、アンゾフのマトリクスを踏まえた複数の成長戦略を実行しました。まず既存市場に向けてはインスタントカメラ「チェキ」の投入(市場浸透戦略)でヒット商品を生み出し、既存技術を応用して液晶ディスプレイ用フィルムなど周辺分野に展開(市場開拓戦略)することで事業領域を拡大。
そして極めつけはフィルム技術を転用した化粧品・医療分野への進出(多角化戦略)で、ヘルスケア事業を第二の柱に育て上げました。これらの取り組みにより富士フイルムは事業構造の転換に成功し、現在も成長を続けています。
株式会社吉野家
牛丼チェーンの吉野家は国内市場の成熟化を見据え、早くから海外展開を図ってきました。中でも人口規模の大きい中華圏への進出は戦略的に重要視され、同社は現地でのブランディングに工夫を凝らしました。
具体的には、牛丼が現地では認知が低いことを踏まえ、高級志向の店舗スタイルや価格設定で出店する差別化戦略を採用。これが功を奏し、現地富裕層の支持を得てブランド浸透に成功しました。北京では「最も愛されるブランド」に選出されるなど、吉野家の中華圏進出は市場開拓戦略の成功例として知られています。現在では東アジア各地に店舗網を広げ、海外売上の拡大に貢献しています。
これらの事例からも分かるように、アンゾフの成長マトリクスは自社の状況に応じて柔軟に戦略を導き出すフレームワークです。富士フイルムは危機対応策として多角化を含む複数戦略を講じ、吉野家は成長機会として海外市場開拓に踏み出しました。いずれも自社の強みを活かしつつリスクとリターンを見極めた戦略選択が功を奏したケースと言えるでしょう。
アンゾフの成長マトリクスを活用するポイント
最後に、アンゾフの成長マトリクスを実践で効果的に活用するためのポイントを押さえておきましょう。
以下の点に注意することで、マトリクスを使った戦略策定の質を高めることができます。
ターゲット顧客を明確にすること
戦略オプションを考える際、常に「誰に向けた製品・サービスか」を意識しましょう。ターゲットが不明確なままだと戦略自体がぼやけてしまいます。
例えば新規市場開拓なら、その市場の顧客像(ペルソナ)を具体的に描くことが重要です。顧客像によりマーケティング手法も変わるため、戦略立案の段階から明確なターゲティングを行いましょう。
市場環境の変化を捉えること
マトリクスで検討した戦略が有効かどうかは、時代の市場環境に適合しているかによります。技術革新や法規制の変更、顧客の価値観の変化など、外部環境を常にモニタリングしましょう。
例えばAIやIoTの普及によって新しい市場ニーズが生まれていないか、既存市場が縮小傾向にないか、といった点です。環境変化を無視した戦略ではせっかくのアイデアも実現が難しくなるため、柔軟に戦略を見直す姿勢も大切です。
コストとリソースを確認すること
検討した戦略それぞれに対し、必要となる投資額や人員・期間を試算してみましょう。どんなに魅力的な戦略でも、費用対効果が低ければ実行すべきではないかもしれません。
特に新規製品開発や新市場参入は時間とコストがかかるため、事前にシミュレーションして利益率への影響を評価します。
自社に不足するリソースがある場合は、外部パートナーとの提携やM&Aも視野に入れるなど、リスクに見合うリターンが得られるか慎重に見極めましょう。
既存事業も含めて見直すこと
アンゾフのマトリクスは新規事業だけでなく、現在の既存事業の整理にも有効です。マトリクスを作成する過程で、自社の現行事業の強み・弱みや、改めて注力すべき領域が見えてくることがあります。成長戦略を検討する際には、既存事業のポートフォリオも同時に振り返りましょう。
不要な事業の縮小や撤退判断、新たな投資配分の決定など、トータルで最適な経営資源配分につなげることができます。つまり、新規と既存のバランスを考えることが、持続的成長のポイントです。
以上のポイントを踏まえれば、アンゾフの成長マトリクスを「描いただけ」で終わらせず、実効性のある戦略立案ツールとして活用できるでしょう。
アンゾフの成長マトリクスで自社の成長戦略を検討しよう
アンゾフの成長マトリクスは、「市場」と「製品」の視点から自社の成長戦略を考えるための強力なフレームワークです。4つの戦略オプション(市場浸透・市場開拓・製品開発・多角化)は、自社がどの方向に事業を拡大すべきかを検討する指針となります。リスクとリターンのバランスを比較しながら、最適な戦略の組み合わせを見出すことで、企業は持続的な成長への道筋を描くことができます。
本記事で紹介したように、アンゾフの成長マトリクスは事業が停滞している時や新たな挑戦を考える時など、様々な場面で意思決定の助けになります。実際に多くの企業がこのフレームを活用し、新市場への進出や新商品の開発で成功を収めています。ぜひ自社の状況に当てはめてマトリクスを作成し、網羅的に戦略アイデアを洗い出してみてください。
最後は自社の強みや経営資源との照らし合わせになりますが、アンゾフの成長マトリクスを土台に検討することで、納得感のある成長戦略プランを策定できるはずです。あなたの企業の次なる成長シナリオを描く一助として、アンゾフの成長マトリクスをぜひ活用してみましょう。
ナレブロについて

「ナレブロ」は、ナレッジブログ(Knowledge Blog)の略称です。運営者自身が実務を通じて培ってきた知見や経験(ナレッジ)を惜しみなくアウトプットし、読者の皆さまに還元することを目的としています。
現代において、真に価値のある情報の多くはクローズドな場所に偏っています。だからこそ本ブログでは、オープンなプラットフォームでありながら、実戦で役立つ高鮮度な情報発信を追求しています。「マーケティング」や「スキルアップ」の知見を提供することで、志高く働く方々の「近道」となる。それがナレブロの運営理念です。
関連ページ:コンテンツ制作・運営ポリシー