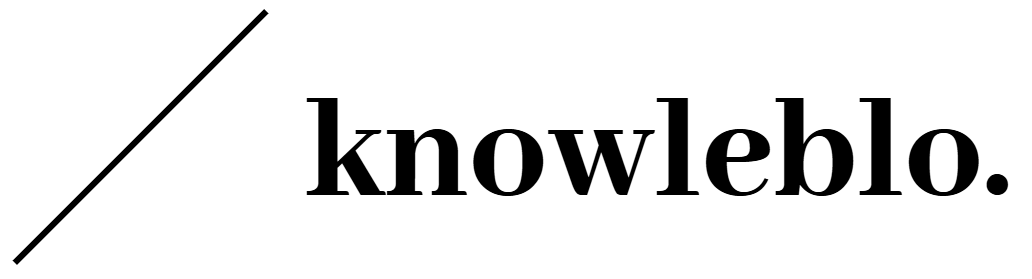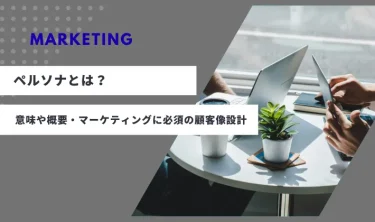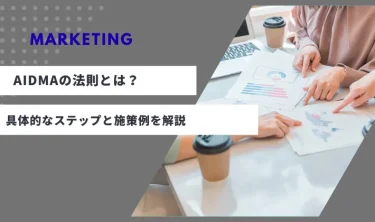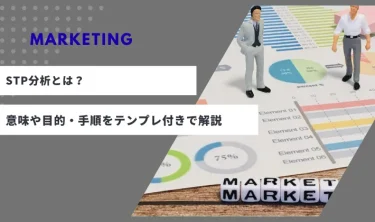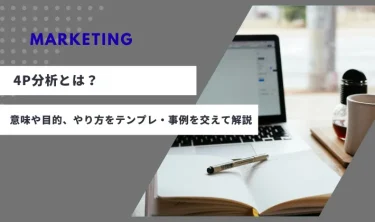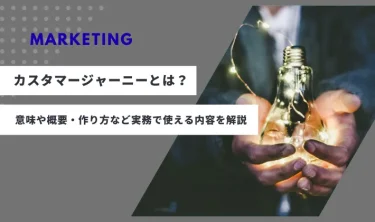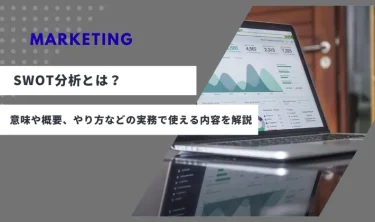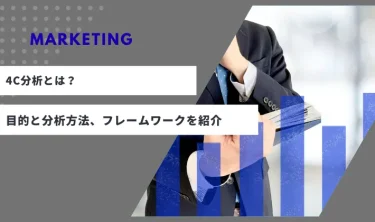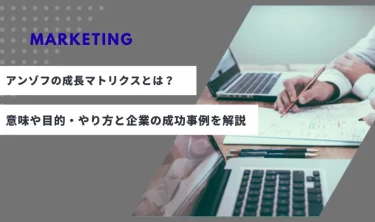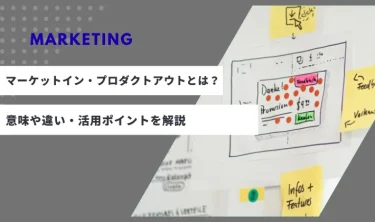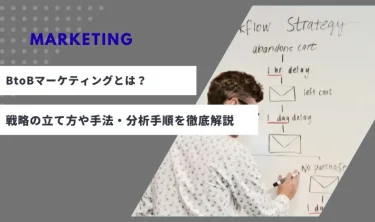「カスタマージャーニーを作ってほしい」と上司に言われたものの、何から始めればいいのか分からない。そんな悩みを抱えるマーケティング担当者の方は少なくありません。
カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入し、継続利用するまでの一連の行動と感情を可visible化した設計図です。この設計図があれば、顧客がどこでつまずいているのか、どの施策が効果的なのかが一目で分かります。
本記事では、カスタマージャーニーの基本的な概念から、実務で使える作成手順、B2CとB2Bの具体例、KPIの設定方法、継続的な改善の仕組みまでを網羅的に解説します。記事を読み終えるころには、明日から実践できる知識とテンプレートが手に入るでしょう。
カスタマージャーニーとは
カスタマージャーニーとは、顧客の行動・思考・感情と、企業のタッチポイント・施策・KPIを時系列に対応づけるための図表です。
顧客が商品を知ってから購入し、継続的に利用するまでの道のりを「旅」に例え、その過程で顧客が何を考え、どこで迷い、何をきっかけに前に進むのかを可視化します。この可視化により、改善すべきポイントが自然に浮かび上がり、優先順位も明確になります。
たとえば、広告では「最短で使える」と訴求しているのに、実際の初回設定に30分以上かかるとしたら、メッセージと体験にズレが生じています。このようなズレは顧客の離脱を招きますが、カスタマージャーニーを作成すれば、どの接点で何を補うべきかが一目瞭然になります。
カスタマージャーニーの目的
カスタマージャーニー作成の主な目的は2つあります。
目的1.戦略と施策の矛盾を防ぐ
第一に、全体戦略と現場の施策に矛盾が生じないように整えることです。マーケティング部門が発信するメッセージと、カスタマーサポートが提供する体験が一致していなければ、顧客は混乱します。カスタマージャーニーは、部署間の施策を一つの流れにつなげる役割を果たします。
目的2.施策の優先度と順番を明確にできる
第二に、顧客がつまずく地点を特定し、手を打つ順番をはっきりさせることです。限られたリソースを効果的に配分するには、どの課題から解決すべきかを明確にする必要があります。カスタマージャーニーがあれば、データに基づいて優先順位を判断できます。
カスタマージャーニーのメリット
カスタマージャーニーを作成すると、以下のようなメリットが得られます。
一貫性のあるマーケティングを展開できる
メッセージの統一とコンテンツの差し替えが迅速に進みます。すべての接点で一貫したメッセージを発信できるため、顧客の信頼を獲得しやすくなります。
安定した成果につながる
CVR(コンバージョン率)や継続率のような指標が安定します。顧客体験の改善ポイントが明確になるため、施策の効果が数値として現れやすくなります。
マーケティングの会議が建設的な議論になる
会議が「状況説明」から「解決策の選択」へと重心が移ります。カスタマージャーニーという共通言語があれば、現状認識のすり合わせに時間を取られず、本質的な議論に集中できます。
チーム全体で同じ顧客視点を共有できます。営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、異なる部署が同じ顧客像を理解することで、連携がスムーズになります。
カスタマージャーニーの構成要素
カスタマージャーニーを作成する際は、要素を固定しておくと迷いにくくなります。以下の要素を順番に設定していくことで、実用的なカスタマージャーニーが完成します。
ペルソナの設定
ペルソナとは、ターゲットとする顧客を具体的な一人の人物として定義したものです。
ペルソナを設定する際は、一人に絞って具体的に描くことが重要です。年齢、職業、役職、課題、価値観など、できるだけ詳細に設定します。「30代の女性」という漠然とした設定ではなく、「35歳、化粧品メーカーのマーケティング担当、敏感肌に悩んでいる」といった具体性が必要です。
また、意思決定者と利用者が異なる場合は、両者の視点を分けて考えます。たとえばB2Bのソフトウェアでは、経営層が購入を決定し、現場の担当者が実際に使用するケースが多くあります。この場合、それぞれの関心事や行動パターンが異なるため、両方の視点を考慮する必要があります。
ペルソナとは?
ペルソナとは、マーケティング活動において「理想的な顧客像」をデータと実際の顧客の声に基づいて、一人の具体的な人物として描いた設計図のことです。単なる年齢や職業といった属性情報だけでなく、情報収集の行動パターン、購買時の判断[…]
フェーズの定義
フェーズとは、顧客が商品やサービスと関わる過程を段階的に分けたものです。
基本的なフレームワークは「認知 → 検討 → 比較 → 購入 → 利用 → 継続・推奨」という流れです。ただし、業界や商材によってフェーズの名称や数は調整します。たとえば、高額商品の場合は「検討」と「比較」の間に「試用」というフェーズを追加することもあります。
各フェーズにおける顧客の行動・思考・感情を短文で記録します。「このフェーズで顧客は何をしているのか」「何を考えているのか」「どんな気持ちなのか」を具体的に書き出すことで、顧客の心理状態が明確になります。
タッチポイントの整理
タッチポイントとは、顧客が商品やサービスと接する接点のことです。
オンラインとオフラインの両方の接点を漏れなく洗い出します。オンラインには広告、SNS、Webサイト、メール、アプリなどが含まれます。オフラインには店舗、イベント、営業面談、電話サポートなどがあります。
顧客がサービスと触れるすべての場面を可視化することで、体験の全体像が把握できます。見落としがちなタッチポイントも含めて、徹底的にリストアップすることが重要です。
マーケティング活動で頻繁に耳にする「タッチポイント」という言葉をご存知でしょうか。企業と顧客の接点を意味するこの概念は、売上向上や顧客満足度の向上において重要な役割を果たします。しかし、「言葉は聞いたことがあるが具体的に何を指し、どのように[…]
阻害要因と施策の対応
阻害要因とは、顧客が次のステップに進むことを妨げる要素です。
各タッチポイントで生じる問題点を特定します。たとえば「価格が分からない」「使い方が難しそう」「自分に合うか判断できない」といった不安や疑問が阻害要因になります。
そして、その阻害要因を解消するための施策案を対にして配置します。「価格が分からない」という阻害要因に対しては「価格帯の早期提示」や「料金シミュレーター」といった施策を考えます。阻害要因と施策を常にセットで管理することで、具体的なアクションにつながりやすくなります。
KPI設定
KPI(重要業績評価指標)とは、各フェーズの成果を測定する指標です。
フェーズごとに追うKPIをひとつに絞ることで、効果の確認が簡潔になります。認知フェーズではCTR(クリック率)、検討フェーズでは滞在時間、購入フェーズではCVR(コンバージョン率)といった具体的な数値を設定します。
データ源と更新頻度も明記しておきます。たとえば「GA4から週次で取得」「CRMから月次で集計」といった具体的な運用方法を決めておくことで、継続的な測定が可能になります。
他のフレームワークとの関係
カスタマージャーニーを効果的に活用するには、他のマーケティングフレームワークとの関係を理解しておくことが重要です。
心理モデルとの関係
AIDA、AIDMA、AISASなどの消費者行動モデルは、顧客の心理変化を示す骨格の役割を果たします。
AIDAは「Attention(注意)→ Interest(興味)→ Desire(欲求)→ Action(行動)」という購買心理の基本的な流れを表したモデルです。AIDAMAは、これに「Memory(記憶)」を加えたモデルで、広告を見てから購入までに時間がかかる商品に適しています。AISASは「Attention → Interest → Search(検索)→ Action → Share(共有)」という、インターネット時代の購買行動を表したモデルです。
カスタマージャーニーは、これらの心理モデルを実務に引き寄せ、具体的なタッチポイントやコンテンツに落とし込む実践的なツールとして機能します。心理モデルが「顧客は何を考えているか」を示すのに対し、カスタマージャーニーは「顧客は何をしているか」「企業は何を提供すべきか」まで含めて設計します。
マーケティング施策を考えるうえで欠かせないのが「購買心理の理解」です。
その基礎となるフレームワークが「AIDMA(アイドマ)の法則」です。消費者が商品を認知してから購入に至るまでの心理プロセスを体系化したもので、広告戦略や販売促進、[…]
AS-ISとTO-BEの活用
AS-IS(現状の姿)とTO-BE(理想の姿)を分けて描くことで、より実践的なカスタマージャーニーになります。
AS-ISでは、現在の顧客体験をありのままに記録します。データやヒアリングに基づいて、顧客が実際にどう行動し、どこでつまずいているのかを客観的に整理します。理想を語る前に、まず現実を正しく把握することが改善の第一歩です。
TO-BEでは、理想的な顧客体験と、それを実現するために必要な施策を描きます。AS-ISとTO-BEを並べることで、両者の差分が明確に浮かび上がり、改善ロードマップが作りやすくなります。議論も抽象論に流れにくくなり、具体的なアクションに焦点を当てやすくなります。
推奨する順番は、先にAS-ISを事実で固め、後からTO-BEで理想の流れと必要施策を置くことです。
カスタマージャーニーの作り方
カスタマージャーニーの作成は、以下の5つのステップで進めます。各ステップを丁寧に実行することで、実用的なカスタマージャーニーが完成します。
STEP1 目的と対象の明確化
最初に、カスタマージャーニー作成の目的、評価指標、対象ペルソナを一文で定義します。
このステップが重要な理由は、チーム全体で同じ方向を向いて作業を進めるための基盤を作るためです。目的が曖昧なまま作成を始めると、途中で方向性がブレたり、関係者間で認識のズレが生じたりします。
具体的には、以下の3要素を明文化します。
- 目的:何を達成したいのかを明確にします。「新規顧客の獲得数を増やす」「既存顧客の継続率を向上させる」など、具体的なゴールを設定します。
- 評価指標:成果をどう測るかを決めます。CVR、獲得単価、継続率、NPS(顧客推奨度)など、目的に応じた測定可能な指標を選びます。
- 対象ペルソナ:誰をターゲットにするかを定義します。年齢、職業、課題、価値観など、できるだけ具体的に設定します。
記載例としては「Q3に30代女性の新規購入数を20%増やす。評価はCVRと獲得単価で測定する」といった形式です。この一文があれば、後の作業で迷ったときにも立ち返る基準になります。
STEP2 データと顧客の声の収集
次に、定量データと定性データを集めます。
このステップが必要な理由は、主観や推測ではなく、事実に基づいたカスタマージャーニーを作成するためです。データがなければ、チームメンバーの思い込みだけで設計してしまい、実際の顧客行動とかけ離れたものになってしまいます。
定量データは数値で表現できる客観的な情報です。以下のような情報源から収集します。
- GA4(Google Analytics 4)からは、サイト訪問数、滞在時間、離脱率、コンバージョン率などのデータを取得します。どのページで離脱が多いのか、どの導線が効果的なのかが分かります。
- MA(マーケティングオートメーション)からは、メール開封率、クリック率、リードのスコアリング情報などを取得します。見込み顧客がどのコンテンツに反応しているかが把握できます。
- CRM(顧客関係管理システム)からは、購買履歴、問い合わせ履歴、顧客属性などを取得します。既存顧客の行動パターンや傾向が見えてきます。
- 売上データや行動ログからは、購入金額、購入頻度、利用状況などを分析します。
定性データは数値では表現しにくい、顧客の声や感情に関する情報です。
- 顧客インタビューでは、購入に至った理由、迷ったポイント、満足している点、不満に感じている点などを直接聞き取ります。1対1の対話により、深い洞察が得られます。
- カスタマーサポートログからは、よくある質問、苦情内容、問い合わせのタイミングなどを分析します。顧客がどこでつまずいているかの貴重なヒントが含まれています。
- アンケート結果やレビュー、SNSでのフィードバックからは、多くの顧客の率直な意見を収集できます。
これらのデータを組み合わせることで、顧客の真の行動と感情を把握できます。
STEP3 フェーズ×タッチポイント表の作成
収集したデータを基に、フェーズ×タッチポイントの表を作成します。
このステップが重要な理由は、散らばった情報を一つの流れに整理し、全体像を可視化するためです。表形式にすることで、どのフェーズのどのタッチポイントに課題があるのかが一目で分かります。
表には以下の項目を書き込みます。
- 顧客の行動:各フェーズで顧客が実際に取る行動を記述します。「広告をクリックする」「比較サイトでレビューを読む」「無料トライアルに申し込む」といった具体的な行動を書きます。
- 顧客の思考・感情:その行動をしているときに顧客が何を考え、どう感じているかを記述します。「本当に効果があるのか不安」「価格が妥当か判断できない」「使いこなせるか心配」といった内面を言語化します。
- 阻害要因:顧客が次のステップに進むことを妨げる要素を記述します。「価格が分からない」「導入事例が少ない」「問い合わせ窓口が見つからない」など、具体的な障壁を特定します。
- 解消施策:阻害要因を解決するための具体的な対策を記述します。「料金ページを分かりやすく改善」「導入事例コンテンツを10件追加」「チャットサポートを導入」といった実行可能な施策を考えます。
各セルは簡潔に、事実に基づいた内容で記載することが重要です。一つのセルに複数の情報を詰め込まず、要点を絞って記述します。
記載例として、認知フェーズの広告タッチポイントでは「行動:SNS広告をクリック / 思考・感情:興味はあるが本当に効果があるのか不安 / 阻害要因:具体的な使用感が分からない / 解消施策:ユーザーの体験談動画を広告に追加」といった形式で整理します。
STEP4 KPI設定と施策の優先順位付け
各セルで見つかった阻害要因と解消施策を対にし、フェーズごとにKPIをひとつ設定します。
このステップが必要な理由は、改善活動を測定可能にし、効果を客観的に評価できるようにするためです。KPIがなければ、施策が成功したのか失敗したのか判断できず、改善のサイクルが回りません。
KPI設定時のポイントは以下の通りです。
測定可能で具体的な指標を選びます。「顧客満足度を向上させる」といった曖昧な目標ではなく、「NPS(ネットプロモータースコア)を20ポイント向上させる」「CVRを現在の2.5%から3.5%に改善する」といった数値目標を設定します。
データ取得の頻度と方法を明確にします。「GA4から毎週月曜日にデータを取得」「CRMから月次でレポートを作成」など、誰がいつどのように測定するかを決めておきます。
改善目標値を設定します。現状値と目標値の両方を記録し、どれだけ改善すればよいかを明確にします。
記載例として、検討フェーズでは「KPI:記事の平均滞在時間 / 現状値:1分30秒 / 目標値:3分以上 / 測定方法:GA4から週次で取得 / 担当者:マーケティング担当A」といった形式で管理します。
優先順位付けでは、影響度と実現可能性の両方を考慮します。影響度が高く、実現が容易な施策から着手することで、早期に成果を出しやすくなります。
STEP5 ロードマップ化と実行計画
AS-ISとTO-BEを並べ、差分を時系列のロードマップに変換します。
このステップが重要な理由は、理想的なカスタマージャーニーを実現するための具体的な行動計画に落とし込むためです。ロードマップがなければ、カスタマージャーニーは絵に描いた餅で終わってしまいます。
この段階で以下が自然に決まります。
1.各施策の担当者
各施策の担当者を明確にします。誰がその施策を実行するのか、責任者は誰なのかを決めておくことで、実行の確実性が高まります。
2.施策の期限
施策の実施期限を設定します。「今月中」「Q2まで」といった具体的な期限を設けることで、先延ばしを防ぎます。
3.必要なリソース
必要なリソースを洗い出します。予算、人員、ツール、外部パートナーなど、施策を実行するために必要なものをリストアップします。
4.効果測定の期間やタイミング
成果測定のタイミングを決めます。施策を実施してから、どのタイミングで効果を測定するかを事前に決めておきます。
記載例として、「施策:導入事例コンテンツの作成 / 担当者:コンテンツチームB / 期限:6月末まで / 予算:50万円 / 測定タイミング:7月第2週」といった形式でロードマップを作成します。
ロードマップは四半期ごとに見直し、実行状況と成果を確認しながら調整していきます。
カスタマージャーニーテンプレート
実際にカスタマージャーニーを作成する際に使える、基本テンプレートを紹介します。
基本テンプレート
以下のテンプレートをコピーして使用してください。セルは短文で、名詞と数値を優先して記入することがポイントです。
| フェーズ | タッチポイント | 行動 | 思考・感情 | 阻害要因 | 解消施策 | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知 | 広告/SNS | 広告を閲覧 | 興味はあるが不安 | 価格が分からない | 価格帯の早期提示、FAQ導線 | CTR |
| 検討 | 記事/LP | 比較情報を探す | 信頼できる根拠が欲しい | 事例不足 | 事例・数字の追加、第三者評価 | 滞在時間 |
| 比較 | レビュー/資料 | レビュー・資料を読む | 自分に合うか不明 | 自己判断が難しい | 診断ツール、チャット相談 | CVR(CV前) |
| 購入 | カート/申込 | 情報入力 | 手間が負担 | 入力項目が多い | フォーム最適化、保存機能 | CVR(購入) |
| 利用 | アプリ/サポート | 初期設定 | 使いこなせるか不安 | 手順が複雑 | 3分ガイド、オンボ動画 | 活性率 |
| 継続・推奨 | メール/コミュニティ | 継続利用 | 成果を実感したい | 成果が見えにくい | 成果レポート、紹介特典 | 継続率/紹介率 |
テンプレート活用のコツ
このテンプレートを効果的に活用するために、以下の点に注意してください。
各セルの内容は具体的で測定可能なものにします。「顧客が不安に感じる」ではなく、「価格が適正か判断できず不安」といった具体的な表現を使います。抽象的な表現では、後で施策を考える際に役立ちません。
また、業界や商材に応じてフェーズ名をカスタマイズします。このテンプレートは汎用的なものですが、自社のビジネスモデルに合わせて調整することが重要です。たとえば、サブスクリプションサービスであれば「解約検討」というフェーズを追加することも考えられます。
カスタマージャーニーは、定期的に内容を見直し、最新の顧客データで更新します。カスタマージャーニーは一度作って終わりではなく、顧客行動やマーケット環境の変化に合わせて進化させていくものです。四半期ごとの見直しを習慣化することをおすすめします。
複数のペルソナがある場合は、それぞれにテンプレートを作成します。異なる顧客セグメントでは行動パターンや阻害要因が大きく異なるため、一つのテンプレートに無理にまとめようとせず、分けて管理します。
カスタマージャーニーの具体例
実際のビジネスシーンでカスタマージャーニーがどのように活用されるのか、B2CとB2Bの具体例を紹介します。
B2C事例:コスメECサイト
「肌へのやさしさ」を重視する30代女性を想定したコスメECのカスタマージャーニー例です。
| 認知フェーズ | 肌刺激への不安が先立つため、価格よりも安全性の根拠を前面に配置します。 広告クリエイティブでは「無添加」「皮膚科医推奨」といったキーワードを優先的に使用し、安心感を醸成します。 |
| 検討フェーズ | 第三者の評価や成分の詳細説明が購入の鍵になります。 美容ライターの推奨記事や、成分ごとの効果説明を充実させ、科学的根拠に基づいた情報提供を行います。 |
| 比較フェーズ | 「自分に合うかどうか」の判断に迷うため、肌質診断ツールやチャット相談機能が背中を押す役割を果たします。 パーソナライズされた商品推奨により、選択の不安を軽減します。 |
| 購入フェーズ | フォーム離脱が起きやすい段階のため、入力の自動補完機能や途中保存機能が効果的です。 また、配送オプションの明確な表示により、最後の一歩を後押しします。 |
| 利用フェーズ | 3分間のオンボーディング動画で正しい使用方法を伝え、効果実感までの期間や使用感の変化について事前に説明することで、継続利用を促進します。 |
| 継続・推奨フェーズ | 肌状態の改善を数値化したレポート機能や、友人紹介特典システムが口コミ拡散を生み出します。 |
B2B事例:SaaS企業
従業員50〜300名で専任の情シスがいない企業を想定したSaaS企業のカスタマージャーニー例です。
| 認知から検討フェーズ | 「導入負担への懸念」が一貫した障壁となります。 広告や資料では機能訴求よりも「導入は最短30分、運用はチャットで即時支援」という導入・運用の簡単さを軸にメッセージを統一します。 |
| 比較フェーズ | 既存ツールとの連携可否やセキュリティ要件が検討の焦点となります。 API連携の対応範囲や、SOC2/ISO27001などの監査対応情報を早い段階で提示し、技術的な不安を解消します。 |
| 購入フェーズ | 複数部署を巻き込んだ決裁フローが長引く傾向にあるため、以下の資料を準備します。
|
| 導入フェーズ | オンボーディングのチェックリストと週次の伴走支援により、確実な定着を図ります。 専任のカスタマーサクセス担当者が初期設定から活用方法まで一貫してサポートすることで、早期の成果実感を促します。 |
| 継続・推奨フェーズ | 月次の活用レポートとベンチマーク情報の提供により、継続的な価値を実感してもらいます。 ユーザーコミュニティやカンファレンス招待により、他社事例の共有と推奨行動を促進します。 |
チャネル設計と施策の当て込み
カスタマージャーニーを実際の施策に落とし込む際は、チャネル設計と施策の統合が重要になります。
統一されたメッセージ戦略
カスタマージャーニーを基に、チャネルとコンテンツの位置づけを統一します。
認知から比較フェーズ
認知から比較フェーズでは、核となる一言メッセージを統一し、媒体ごとに表現の濃度を調整します。たとえば、「30分で始める業務効率化」というコアメッセージがあれば、Twitter広告では「30分で始まる、新しい働き方」、Google検索広告では「導入30分|IT担当者不要の業務効率化ツール」、LPでは「専門知識は不要です。アカウント作成から初期設定まで、わずか30分で完了します」といった形で展開します。
チャネル横断でのメッセージ一貫性を保持することで、顧客が複数の接点で同じ企業に触れたときに、ブランドイメージが強化されます。広告で「簡単導入」と言いながら、Webサイトでは技術的な専門用語が並んでいると、顧客は混乱します。
購入・導入フェーズ
購入・導入フェーズでは、入力や設定のつまずきを減らす設計に注力します。ユーザビリティテストを定期的に実施し、実際のユーザーがどこで迷うのかを観察します。テスト参加者に声に出して考えを話してもらう「シンクアラウド法」を使うことで、心理的な障壁も把握できます。
エラー発生時のサポート体制も強化します。エラーメッセージは「エラーが発生しました」といった曖昧な表現ではなく、「入力された郵便番号の形式が正しくありません。ハイフンなしで7桁の数字を入力してください」といった具体的な指示を提供します。
利用・継続フェーズ
利用・継続フェーズでは、成果を実感できる仕掛けを中心に設計します。定期的なレポート配信により、「今月は先月より業務時間が10時間短縮されました」といった具体的な数値を示します。グラフやビジュアルを活用し、変化を視覚的に分かりやすく伝えます。
コミュニティ運営による横のつながり創出も効果的です。ユーザー同士が活用方法を共有できるオンラインコミュニティを作ることで、企業からの一方的な情報提供だけでなく、ユーザー同士の学び合いが生まれます。
効率的な施策管理
カスタマージャーニーに紐づいた施策管理により、以下のメリットが得られます。
- 施策がバラバラに増えることを防ぎます。新しい施策を検討する際、「これはカスタマージャーニーのどのフェーズ、どの阻害要因に対応するものか」を必ず確認します。目的が不明確な施策は実行しないという判断基準を持つことで、リソースの無駄遣いを防げます。
- 更新時に不要な要素を素早く削除可能です。四半期ごとの見直しで、効果が出ていない施策を特定し、継続・改善・中止の判断を迅速に行います。カスタマージャーニー上で効果が可視化されているため、感情的な議論ではなく、データに基づいた冷静な判断ができます。
- ROIの測定と改善が容易になります。各施策にかかったコスト、実施期間、KPIの変化を一元管理することで、投資対効果が明確になります。「この施策に月10万円投資して、CVRが1.5ポイント向上したので、獲得単価は3,000円改善した」といった具体的な効果測定が可能です。
計測と改善の仕組み
カスタマージャーニーは作成して終わりではなく、継続的に測定し改善していくことで真の価値を発揮します。
KPI設定の原則
フェーズごとにKPIをひとつに絞ることで、効果の確認が簡潔になります。
測定可能性の確保は、定量的に測定できる指標を選択することから始まります。「顧客満足度を向上させる」ではなく、「NPSを現在の30ポイントから45ポイントに向上させる」といった具体的な数値目標を設定します。
データ取得の方法と頻度を明確化します。「誰が」「どのツールから」「いつ」「どのように」データを取得するのかを文書化しておきます。担当者が変わってもデータ取得が継続できるよう、手順書を作成することが重要です。
目標値と改善幅を設定します。現状値だけでなく、「いつまでに」「どこまで」改善するのかを明確にします。「Q2末までにCVRを2.5%から3.5%に向上させる」といった期限付きの目標を設定することで、チーム全体に緊張感が生まれます。
原因特定のための仕組み
ログデータだけでは顧客の意図が読み取りづらいため、以下を組み合わせます。
- 顧客アンケートでは、特定の行動を取った直後にフィードバックを求めます。購入完了直後に「購入の決め手は何でしたか」と尋ねることで、鮮明な記憶に基づいた回答が得られます。選択肢だけでなく、自由記述欄も設けることで、想定外の要因を発見できます。
- ユーザビリティテストでは、実際のユーザーに特定のタスクを実行してもらい、その過程を観察します。「この商品をカートに入れて、購入手続きを完了してください」といった指示を出し、どこで迷うのか、どこでエラーが出るのかを記録します。5〜10名程度の小規模なテストでも、多くの問題点が発見できます。
- インタビューや観察調査では、顧客の行動の背景にある動機や感情を深く掘り下げます。「なぜその選択をしたのか」「その時どんな気持ちだったのか」を丁寧に聞き取ることで、データだけでは見えない洞察が得られます。
継続的改善のサイクル確立
更新ルールの設定では、四半期に一度の定期見直しを基本とします。見直しのタイミングは、事業年度のサイクルに合わせて、4月、7月、10月、1月といった固定スケジュールにすることで、習慣化しやすくなります。結果を必ずジャーニー図へ反映します。施策を実行して効果があった場合は、その施策をTO-BEに組み込みます。効果がなかった場合は、阻害要因の分析が不十分だった可能性があるため、再度顧客の声を集めます。
チーム全体での学習共有も重要です。月次のレビューミーティングで、各担当者が実施した施策の結果と学びを共有します。成功事例だけでなく、失敗事例も積極的に共有することで、チーム全体の学習速度が向上します。成功のための重要ポイントは、データに基づいた客観的な分析を徹底することです。「私はこう思う」ではなく、「データではこうなっている」という議論のスタイルを組織に根付かせます。
小さく早い改善サイクルの維持も大切です。大きな変更を一度に行うのではなく、小さな改善を頻繁に繰り返すアプローチを取ります。A/Bテストを活用し、変更前後の効果を定量的に測定することで、確実に前進できます。
関係部署を巻き込んだ協力体制を構築します。マーケティング、営業、カスタマーサポート、プロダクト開発など、顧客接点を持つすべての部署がカスタマージャーニーを共通言語として使えるようにします。
オンラインとオフラインの統合
顧客体験は、オンラインとオフラインを行き来しながら形成されます。両者を切り離さず、一つの流れとして設計することが重要です。
全チャネル体験の設計
店舗やイベント、営業面談といったオフライン接点を、Webの体験と切り離さずに一つの流れとして設計します。
データ連携の重要性は、顧客情報を一元管理することで実現します。来店時のヒアリング内容をSFA(営業支援システム)に記録し、次回のオンライン接触時にその情報を活用します。「先日店舗でご相談いただいた○○の件ですが」とメールで続きの提案ができれば、顧客は「ちゃんと覚えていてくれた」と感じます。
名刺交換情報をCRMに即座に連携することで、展示会で名刺交換した翌日には、その人の興味関心に合わせたフォローメールを送ることができます。手動での入力作業を減らすため、名刺スキャンアプリとCRMを連携させることも有効です。
オンライン行動履歴とオフライン接点の紐付けも重要です。Webサイトでどのページをじっくり見ていたのか、どの資料をダウンロードしたのかといった情報を、営業担当者が商談前に確認できるようにします。
シームレスな体験の創出
オンラインとオフラインの行き来がデータとして可視化されることで、以下が実現します。
- 部門間の連携速度が向上します。マーケティング部門が獲得したリードの情報が、営業部門にリアルタイムで共有されることで、タイムリーなフォローアップが可能になります。「資料請求から24時間以内に電話連絡」といったルールを設けることで、顧客の関心が高いうちにアプローチできます。
- 体験の継ぎ目が目立たなくなります。顧客が複数のチャネルを使っても、一貫した体験を提供できます。店舗で試着した商品を、後日オンラインで購入する際に、店舗での試着履歴が表示されれば、「この商品を試着されましたね。サイズはMでよろしいですか」といった提案ができます。
- 顧客に合わせたパーソナライズされた対応が実現します。過去の購買履歴、閲覧履歴、問い合わせ内容などを総合的に分析し、その顧客に最適な提案を行います。
具体的な統合施策例
小売業での統合例では、店舗での商品体験後、オンラインでの購入フォローを行います。店舗で商品を手に取った顧客に、「詳しい情報はこちら」とQRコードを提示し、オンラインの商品ページに誘導します。オンラインページでは、店舗では伝えきれない詳細なスペック、他の顧客のレビュー、コーディネート例などを提供します。
ECサイトでの閲覧履歴を店舗スタッフが確認できるシステムを導入します。来店した顧客がオンラインでどの商品を見ていたかを把握し、「こちらの商品に興味をお持ちでしたね。実物をご覧になりますか」と声をかけることで、顧客は驚きと同時に特別感を感じます。
在庫状況のリアルタイム連携により、「オンラインでは在庫切れですが、○○店舗には在庫があります。取り置きしましょうか」といった提案が可能になります。
B2B営業での統合例では、ウェビナー参加後の営業フォローアップを迅速に行います。ウェビナー中のアンケート結果、Q&Aでの質問内容、チャットでのコメントなどを営業担当者に共有し、その情報を基にパーソナライズされたフォローを実施します。
オンライン資料ダウンロード履歴を商談で活用します。「先月、当社の導入事例集をダウンロードいただきましたが、特に興味を持たれた事例はありましたか」と切り出すことで、顧客のニーズをより深く理解できます。
提案書送付後のオンライン行動を追跡します。メールで送付した提案書PDFがどのページまで読まれたのか、何回開かれたのかをトラッキングし、関心度を測ります。じっくり読まれている場合は確度が高いと判断し、優先的にフォローします。
カスタマージャーニー作成に役立つツール
カスタマージャーニーの作成と運用を効率化するツールを紹介します。
作成・編集ツール
ホワイトボード型ツールは、カスタマージャーニー作成に相性が良く、関係者が同時に編集作業を行えます。
- Miroは豊富なテンプレートと直感的な操作性が特徴です。カスタマージャーニー専用のテンプレートが複数用意されており、初心者でもすぐに始められます。付箋機能を使ってアイデアを出し合い、整理していく作業がスムーズに行えます。
- FigJamはデザイナーとの連携がしやすいツールです。デザインチームがビジュアルアセットを直接貼り付けたり、UIの改善案をその場で描いたりできるため、議論が具体的になります。
- Microsoft Whiteboardは、Office365との連携が強力です。既にMicrosoft製品を社内で使用している企業であれば、追加コストなく導入でき、TeamsやOutlookとの連携もスムーズです。
- Lucidchartはフローチャート機能が充実しており、カスタマージャーニーだけでなく、業務フローやシステム構成図なども作成できます。プロセス全体を可視化する際に有効です。
計測・分析ツール
基盤となる分析ツールとして、以下が活用されます。
- GA4(Google Analytics 4)は、Webサイトの行動分析に不可欠なツールです。ユーザーの流入経路、ページ遷移、滞在時間、離脱ポイントなどを詳細に分析できます。イベントトラッキングを設定することで、ボタンクリック、動画再生、フォーム入力など、細かな行動も追跡可能です。
- Search Consoleは検索流入の分析に使います。どのキーワードで検索されて自社サイトに到達したのか、検索結果でのクリック率はどうかを確認できます。顧客の検索意図を理解する上で重要な情報源です。
- MA(マーケティングオートメーション)は、リード育成の可視化に役立ちます。HubSpot、Marketo、Pardotなどのツールを使うことで、見込み顧客がどのコンテンツに反応し、どのタイミングで商談化しやすいかが分かります。
- CRMは顧客情報の一元管理を実現します。Salesforce、Microsoft Dynamics、kintoneなどを活用し、営業活動、購買履歴、問い合わせ履歴を統合的に管理します。
詳細分析ツールとして、以下が活用されます。
- ヒートマップツール(Clarity、Hotjarなど)は、ユーザーの操作行動を可視化します。ページのどこがクリックされているのか、どこまでスクロールされているのか、どこで離脱が多いのかが視覚的に分かります。
- セッションリプレイツールは、実際の操作画面を録画・分析します。ユーザーがどのように操作し、どこで迷ったのかを動画で確認できるため、ユーザビリティの問題点を発見しやすくなります。
- A/Bテストツール(Google Optimize、Optimizelyなど)は、施策の効果を定量的に検証します。2つのパターンを用意し、どちらが効果的かをデータで判断できるため、主観に頼らない改善が可能です。
ツール選定のポイント
ツール選定時は機能の多さよりも、以下の要素を重視することが運用の長続きにつながります。
編集のしやすさ
直感的で迅速な更新が可能かどうかで判断します。複雑な操作が必要なツールは、担当者しか触れなくなり、更新頻度が下がってしまいます。誰でも簡単に編集できるツールを選ぶことで、チーム全体での活用が進みます。
履歴管理機能
変更履歴の追跡と復元機能があるかを確認します。「誰が」「いつ」「何を」変更したのかが分かれば、問題が起きたときにすぐに原因を特定できます。また、誤って削除してしまった内容も復元できるため、安心して編集作業ができます。
共有・権限管理
チームでの安全な情報共有を実現します。部署や役職によって閲覧・編集の権限を設定できるツールを選びます。経営層には閲覧のみ、担当者には編集権限を付与するといった柔軟な運用が可能です。
他ツールとの連携性・互換性
既存システムとの連携のしやすさを確認します。APIが公開されているか、Zapierなどの連携ツールに対応しているかをチェックします。データを手動でコピー&ペーストする手間が発生すると、運用の負担が大きくなります。
よくある失敗と回避策
カスタマージャーニー作成でよく見られる失敗パターンと、その回避策を紹介します。
理想論に偏った設計
理想だけを並べて現状分析が抜けると、実装段階で現実とのギャップに直面し、プロジェクトが頓挫しがちです。
「こうあるべき」という理想の顧客体験を描くことは重要ですが、現状を無視して理想だけを語っても、実現可能性が低くなります。たとえば、「24時間以内にすべての問い合わせに回答する」という理想を掲げても、現状の人員体制では不可能であれば、絵に描いた餅になってしまいます。
回避策として、AS-IS(現状)を事実に基づいて詳細に分析することから始めます。現在の顧客がどのような体験をしているのか、データとヒアリングで正確に把握します。離脱率が高いページ、問い合わせが多い内容、苦情の傾向など、ありのままの姿を記録します。
TO-BE(理想)は現状からの差分のみを記載します。現状から大きくかけ離れた理想ではなく、「現状+α」で実現可能な改善を積み重ねるアプローチを取ります。
実現可能性を考慮した段階的な改善計画を策定します。「まず3ヶ月でここまで改善し、次の3ヶ月でさらにこれを追加する」といった具体的なロードマップを作成します。
主観的な判断に依存
チームメンバーの主観的な意見の寄せ集めになってしまい、データに基づかない推測で施策を決定してしまうケースです。
「私は顧客はこう考えているはずだ」「おそらくこれが問題だろう」といった推測だけでカスタマージャーニーを作成すると、実際の顧客行動とかけ離れたものになります。特に、長年その業界にいる人ほど、自分の経験則に頼りがちです。しかし、顧客の行動や価値観は時代とともに変化しているため、過去の成功体験が今も通用するとは限りません。
回避策として、名詞と数値による具体的な記載を徹底します。「顧客は不安を感じている」ではなく、「アンケート回答者の65%が価格の妥当性について不安を感じている」といった具体的な表現を使います。
情報の出典と更新日を必ず明記します。各セルに記載した内容が、どのデータソースから得られたものかを記録しておきます。「2024年12月の顧客アンケート結果より」「GA4の2025年1月データに基づく」といった形で、根拠を明確にします。
定期的な顧客データによる検証と更新を行います。四半期ごとに最新のデータを収集し、カスタマージャーニーの内容が実態と乖離していないかを確認します。仮説が間違っていた場合は、素直に修正します。
作成で終了してしまう
カスタマージャーニーを作った時点で満足してしまい、継続的な改善につながらないケースが多く見られます。
数日かけて立派なカスタマージャーニーを作成し、関係者で共有して終わり。その後、誰も見返すことなく、施策も変わらず、結局何も変わらなかったという失敗パターンです。カスタマージャーニーは作成すること自体が目的ではなく、顧客体験を改善するための手段であることを忘れてはいけません。
回避策として、ロードマップ、担当者、期限、指標を同じ資料に記載します。カスタマージャーニーと改善計画を別々の資料にすると、連携が取れなくなります。一つの資料の中で、現状分析から改善施策、実行計画までをすべて管理します。
定期的な見直しスケジュールを設定します。四半期ごとのレビューミーティングをあらかじめカレンダーに登録し、強制的に見直しの機会を作ります。参加者も固定し、全員が必ず出席するルールを設けます。
改善結果をジャーニー図に反映する運用ルールを策定します。「施策を実施したら、必ず効果測定を行い、その結果をカスタマージャーニーに書き込む」というルールを徹底します。成功した施策は緑色、効果が薄かった施策は黄色、失敗した施策は赤色といった形で色分けすることで、学びが蓄積されていきます。
その他の失敗パターン
データドリブンなアプローチの欠如では、定量データと定性データをバランスよく活用できていないケースがあります。数値だけを見ていても顧客の感情は分かりませんし、インタビューだけでは全体像が見えません。両方を組み合わせることで、真の顧客理解が得られます。
仮説と検証のサイクルを継続的に回すことも重要です。「こうすれば改善するはず」という仮説を立て、小規模なテストを実施し、結果を測定して次の改善につなげます。このサイクルを高速で回すことで、学習速度が上がります。
小さな改善を積み重ねる文化の醸成も必要です。大きな成果を一度に求めるのではなく、毎週・毎月小さな改善を積み重ねる姿勢が、長期的には大きな成果につながります。
チーム全体での共有不足も典型的な失敗です。マーケティング部門だけでカスタマージャーニーを作成し、営業やカスタマーサポートが関与していないと、現場の実態とずれたものになります。
関係部署を巻き込んだ作成プロセスを設計します。作成の初期段階から、営業、カスタマーサポート、プロダクト開発など、顧客接点を持つすべての部署の代表者を参加させます。
定期的なレビューミーティングを実施し、各部署からの情報をアップデートします。営業が現場で聞いた顧客の声、カスタマーサポートに寄せられた問い合わせ内容などを共有することで、カスタマージャーニーが常に最新の状態に保たれます。
成果の共有と学習の促進も大切です。改善によって得られた成果を全社で共有し、成功事例を横展開します。「この施策でCVRが2ポイント向上しました」といった具体的な成果を共有することで、カスタマージャーニー活用の価値が組織全体に浸透します。
カスタマージャーニー作成前のチェックリスト
事前準備の確認項目
カスタマージャーニー作成に着手する前に、以下の項目を確認しましょう。
□ 目的・指標・ペルソナが一文で定義されているか
- 何を達成したいのか明確になっている
- 成果測定の方法が決まっている
- 対象顧客が具体的に絞り込まれている
□ 必要なデータが収集できる環境が整っているか
- GA4などの分析ツールが導入されている
- 顧客の声を収集する仕組みがある
- データの更新頻度と責任者が決まっている
□ 関係者の協力体制が構築されているか
- マーケティング、営業、カスタマーサポートが参加
- 定期的なミーティングスケジュールが確保されている
- 各部署のデータ共有に合意が得られている
完成度の確認項目
作成したカスタマージャーニーが機能するために、公開前に以下を確認しましょう。
□ AS-ISとTO-BEが分かれ、差分からロードマップが作られているか
- 現状分析が事実に基づいている
- 理想の姿が実現可能なレベルで設定されている
- 改善の優先順位が明確になっている
□ フェーズごとにKPIが設定され、運用方法が決まっているか
- 測定可能で意味のある指標が選ばれている
- データの取得方法と更新頻度が明記されている
- 改善活動の担当者と期限が設定されている
これらの項目をクリアすることで、カスタマージャーニーは”飾り”ではなく”実用的な進行表”として機能し始めます。
他のマーケティングフレームワークとの違い
カスタマージャーニーを効果的に活用するには、他のマーケティングフレームワークとの違いと使い分けを理解しておくことが重要です。
SWOT分析・3C分析
SWOT分析・3C分析は、市場分析や競合分析に優れたフレームワークです。
強みは事実の棚卸しに優れている点です。自社の強み・弱み、市場の機会・脅威を整理したり、顧客・競合・自社の関係性を分析したりする際に有効です。
用途は市場分析や競合分析です。新規事業の立ち上げ、市場参入の判断、競合との差別化ポイントの特定などに使われます。
カスタマージャーニーとの関係は、分析結果をジャーニー作成の基礎データとして活用することです。SWOT分析で特定した自社の強みを、カスタマージャーニーのどのフェーズでアピールするかを決めます。3C分析で明らかになった競合との違いを、比較フェーズでの訴求ポイントに反映します。
STP分析
STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)は、狙いの絞り込みに特化したフレームワークです。
強みは市場をセグメントに分け、ターゲットを選定し、自社の立ち位置を明確にすることです。誰に何を提供するかを決める際に不可欠なプロセスです。
用途はマーケット戦略の方向性決定です。新商品のターゲット設定、ブランドポジショニングの再構築などに使われます。
カスタマージャーニーとの関係は、ペルソナ設定とメッセージ設計の指針として活用することです。STPで定義したターゲットが、カスタマージャーニーのペルソナになります。ポジショニングで決めた差別化ポイントが、各フェーズでのメッセージの核になります。
「STP分析」は、市場を区切り(Segmentation)、狙いを定め(Targeting)、価値の置きどころを決める(Positioning)ための考え方です。
この記事では、定義だけでなく、実務で使える手順やテンプレート、ミニ事例[…]
4P分析
4P分析(Product・Price・Place・Promotion)は、具体的な施策設計に向いているフレームワークです。
強みは製品、価格、流通、プロモーションという4つの要素を統合的に考えられる点です。マーケティングミックスの最適化に役立ちます。
用途はマーケティング施策の具体化です。新商品発売時のマーケティング計画、既存商品のリニューアル戦略などに使われます。
カスタマージャーニーとの関係は、各フェーズでの施策詳細化に活用することです。認知フェーズでは主にPromotion、比較フェーズではProductとPrice、購入フェーズではPlaceといった形で、4Pの要素を各フェーズに配置します。
「4P分析」は、製品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・販促(Promotion)をそろえて検討するための枠組みです。
この記事では、定義だけでなく、実務で使える手順やテンプレート、ミニ事例、注意点までを一つに[…]
補完的フレームワークとの組み合わせ
サービスブループリントは、顧客の体験だけでなく、提供側のバックオフィス業務や内部プロセスも同時に可視化できるフレームワークです。
カスタマージャーニーと組み合わせることで、フロントエンドとバックエンドの連携が明確になります。顧客が体験する表側の流れと、それを支える裏側の業務プロセスを一枚の図で表現できます。
オペレーショナルな改善点が特定しやすくなります。顧客体験を向上させるために、どの業務プロセスを改善すべきかが分かります。たとえば、「問い合わせ回答に時間がかかる」という顧客の不満に対し、サービスブループリントを見れば、「社内承認フローが複雑すぎる」という根本原因が特定できます。
組織全体での顧客体験向上が可能になります。マーケティング、営業、カスタマーサポート、バックオフィスなど、すべての部署が顧客体験にどう貢献しているかが可視化されます。
JTBD(Jobs To Be Done)は、顧客が「雇いたい仕事」という観点から製品・サービスを捉えるフレームワークです。
カスタマージャーニーと組み合わせると、より深い顧客インサイトが得られます。顧客が本当に解決したい課題は何か、製品やサービスにどんな「仕事」を期待しているのかを深く理解できます。
競合の定義が広がり、新たな脅威や機会を発見できます。たとえば、ドリルを販売する企業にとって、競合は他社のドリルだけではありません。JTBDの観点では、「壁に穴を開ける」という仕事を達成できるものすべてが競合です。釘のいらない接着式フックなども競合になり得ます。
顧客の本質的なニーズに基づいた体験設計が可能になります。表面的な要望ではなく、その背景にある真のニーズを理解することで、より的確な施策を考えられます。
統合的な活用方法
これらのフレームワークを効果的に組み合わせるための推奨フローは以下の通りです。
戦略レベルでは、3C・SWOT・STPで方向性を決定します。市場環境を分析し、ターゲットを絞り込み、自社のポジショニングを明確にします。この段階で「誰に」「何を」提供するかの大枠が決まります。
設計レベルでは、カスタマージャーニーで体験を設計します。戦略レベルで決めたターゲットとポジショニングを基に、顧客の行動と感情の流れを可視化します。どのフェーズでどんな体験を提供するかを具体的に設計します。
実装レベルでは、4P・サービスブループリントで具体化します。カスタマージャーニーで設計した体験を実現するために、製品、価格、流通、プロモーションの詳細を決めます。サービスブループリントで業務プロセスも設計します。
検証レベルでは、JTBDで本質的価値を確認します。実装した施策が、顧客が本当に解決したい課題に応えているかを検証します。必要に応じて、設計レベルや実装レベルに戻って修正します。
この統合的なアプローチにより、図の解像度が上がり、より実効性の高いカスタマージャーニーが作成できます。
まとめ
カスタマージャーニーは、顧客の行動・思考・感情と、企業のタッチポイント・施策・KPIを時系列に対応づける実践的なツールです。この記事では、基本概念から作成手順、具体例、継続的な改善方法まで、実務で活用できる知識を網羅的に解説しました。
カスタマージャーニーの最大の利点は、議論を「顧客の道筋」に統一し、改善の優先順位を明確にする点にあります。部署ごとの個別最適ではなく、顧客視点での全体最適を実現できる強力なツールです。
今日から始められるアクションとして、対象ペルソナと改善目標を一文で定義することから着手してください。既存の顧客データを整理し、関係部署の担当者とキックオフミーティングを設定します。本記事のテンプレートを活用し、まずはAS-IS版のカスタマージャーニーを作成してみましょう。カスタマージャーニーは顧客理解を深め、ビジネス成果を向上させる実践的なツールです。完璧を求めず、まずは始めることから顧客体験の改善への第一歩を踏み出しましょう。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。