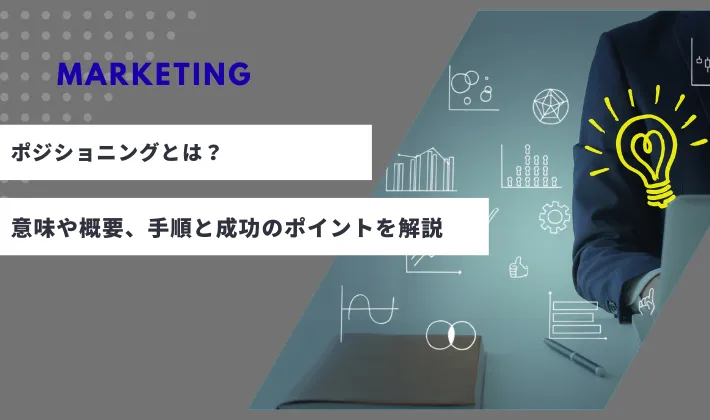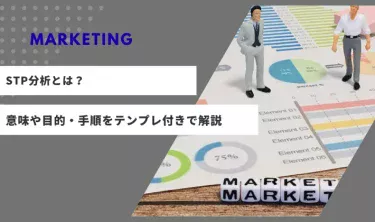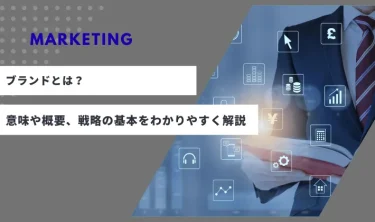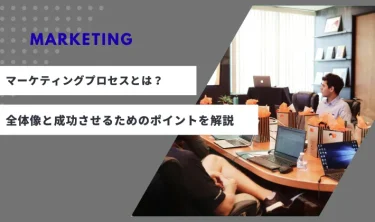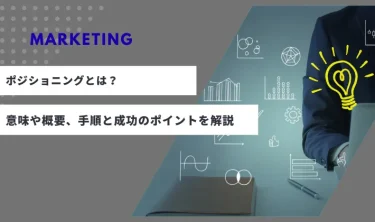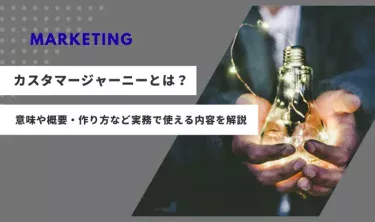マーケティング担当者なら一度は耳にする「ポジショニング」という言葉。しかし、実際に「マーケティングにおけるポジショニングとは何か」と問われると、具体的に説明できない方も多いのではないでしょうか。
ポジショニングは、自社の商品やサービスを市場で際立たせ、顧客に選ばれる存在にするための戦略です。その意味を正しく理解し、上手に活用することで、競合がひしめく市場の中でも自社の強みを発揮しやすくなります。
本記事では、マーケティングのポジショニングの基本的な意味から、その重要性、具体的な進め方や成功のポイントまでをわかりやすく解説します。企業のマーケティング担当者をはじめ、ビジネスで売上アップや市場競争力強化を求められている初心者の方に向けた内容です。読み進めることで、ポジショニングの概要を理解し、明日からの戦略立案に活かせるノウハウを得られるでしょう。
マーケティングのポジショニングとは?意味と重要性
マーケティングにおけるポジショニングとは、企業やブランドが市場で目指す立ち位置を決め、競合と差別化できる独自の価値を打ち出していくプロセスのことです。言い換えれば、ターゲット顧客の心の中に「この商品は価値がありユニークだ」と感じてもらえる位置づけを築く活動を指します。
ポジショニングはマーケティング戦略の中核とも言われ、その巧拙が市場での成功を大きく左右します。実際、ポジショニングが優れていれば、製品の性能やデザインが必ずしも業界で飛び抜けていなくても、市場で際立つ存在になり得るのです。
例えば、価格競争に陥りがちな市場でも、「高品質だけど手頃なブランド」としての位置づけに成功すれば、顧客に選ばれる強い理由を作ることができます。つまりポジショニングとは、自社商品を選んでもらうための必然性を顧客に感じさせる戦略なのです。
また、ポジショニングはブランド戦略や広告など他のマーケティング施策とも深く関わっています。ポジショニングによって「市場における自社の立ち位置」が明確になることで、顧客に浸透させたいブランドイメージも定まり、効果的なブランディングが可能になります。逆に言えば、明確なポジショニングなくして魅力あるブランドイメージを築くことは難しいでしょう。
このように、マーケティングのポジショニングは自社の提供価値を市場で最大限に伝え、競争優位を確立するために欠かせない基本戦略だと言えます。
マーケティングプロセスにおけるポジショニングの役割
ポジショニングは、マーケティング戦略立案の一連の流れにおいて重要な役割を担います。以下では、STP分析の中でポジショニングがどのように位置づけられるのかを詳しく解説します。
STP分析とポジショニングの関係
マーケティングではまず市場を細分化するセグメンテーション、次に狙う市場を決めるターゲティングを行い、最後にポジショニングで自社の提供価値を明確にします。この一連の流れをSTP分析(Segmentation/Targeting/Positioning)と呼び、ポジショニングはその最終段階です。
STP分析のうちS(セグメンテーション)では、市場を地域や年齢、ニーズなどで分類し、自社が入り込める細分市場を洗い出します。次にT(ターゲティング)で、魅力的なセグメントを選び出し、自社がターゲットとする顧客層を明確にします。
そしてP(ポジショニング)では、選定したターゲット顧客に対して自社商品がどのような価値で競合より魅力的かを示す立ち位置を定めます。このポジショニングによって、その後に実行するマーケティング・ミックス(いわゆる4P:製品・価格・流通・プロモーション)の方針が大きく変わることもあります。
たとえば、同じ「若い女性向けの自然食レストラン」を開業する場合でも、「安全でナチュラルなイメージ」を打ち出すのか、「おしゃれで洗練されたイメージ」を打ち出すのかによって、店名やメニュー、価格帯、内装や広告のデザインなど4P全てが変わってきます。このようにポジショニングはSTP分析の仕上げであり、後続の戦略全体の方向性を決定づける重要な意思決定なのです。
STP分析とは、マーケティング戦略立案の基本フレームワークです。自社の商品・サービスを「どこの市場で、誰に向けて、どんな立ち位置で提供するか」を整理する手法で、Segmentation(セグメンテーション)・Targeting(ターゲティン[…]
ブランディングとの違い
なお、ポジショニングとしばしば混同される概念にブランディング戦略がありますが、両者は目的が異なります。ブランディング戦略が「狙ったイメージを顧客に浸透させ、統一化を図ること」を目指すのに対し、ポジショニング戦略は「その前提として、市場における自社商品の立ち位置を定めること」に主眼があります。
明確なポジショニングが定まっているからこそ、一貫したブランドイメージを築き、顧客に真っ先に思い浮かぶ存在になってもらうことが可能になるのです。
マーケティングの現場で「ブランド」は重要なキーワードですが、「マーケティング ブランド」という言葉の意味や具体的な戦略について悩んでいませんか。企業のマーケティング担当者や初心者の方に向けて、本記事ではブランドマーケティングの基礎から効果的[…]
マーケティング担当者として、「マーケティングプロセスという言葉は聞くけれど、具体的に何をすればいいのだろう?」と悩んでいませんか。
本記事は、企業のマーケティング担当者や初心者の方に向けて、マーケティングプロセスの基本から具体的な実践[…]
マーケティングにおけるポジショニングの手順と進め方
それでは、実際に自社の商品やサービスのポジショニング戦略を立てるにはどのような手順で進めればよいのでしょうか。ここからは基本的なステップを具体例を交えながら解説します。
ポジショニングのプロセスは一度きりで終わりではなく、状況に応じて見直し改善していく継続的なサイクルです。最初は以下の5つのステップで進め、得られた結果をもとに随時調整していくと良いでしょう。
STEP1:ターゲット市場の選定と競合分析
まずは、自社が参入する市場セグメントと狙う顧客層を明確にすることから始めます。自社の商品・サービスが提供できる価値とマッチし、なおかつビジネスチャンスが大きい市場を見極めましょう。
市場調査や既存顧客の分析を行い、地域・年齢層・購買動機など様々な切り口で市場を細分化(セグメンテーション)します。例えば、食品業界であれば「健康志向の若年層」「高級志向のシニア層」などに市場を分けるイメージです。その上で、自社が特に強みを発揮できそうなセグメントをターゲット市場として選定します。
なぜこのステップが必要なのか
ターゲット市場を明確にすることで、その後の戦略がブレなくなります。市場を絞り込まずに「誰にでも売りたい」と考えると、結果的に誰にも響かないメッセージになってしまうからです。
競合分析の進め方
ターゲット市場を決めたら、その市場における競合他社の状況を分析しましょう。同じターゲット層を狙っている競合製品・ブランドがどれくらい存在し、それぞれがどんな特徴や訴求ポイントで戦っているのかを洗い出します。
若年層向けの健康食品市場をターゲットにするなら、既存の主要ブランドが「低価格」を武器にしているのか、「味やデザイン性」で差別化しているのかなどを調査します。
競合分析によって、市場における空白領域(競合が手薄なニーズや特徴)や、逆に避けるべき激戦領域が見えてくるでしょう。このSTEP1で得た「ターゲット顧客は誰で、競合環境はどうなっているか」という理解が、後のステップ全ての土台となります。
STEP2:顧客ニーズの把握とKBFの特定
次に、ターゲット顧客のニーズを深く理解し、その購買決定要因(KBF)を特定します。
KBFとは
KBFとはKey Buying Factorの略で、顧客が商品を選ぶ際に最も重視する要素のことです。業界や商品カテゴリによって異なりますが、一般的には以下のような要素が含まれます。
- 価格
- 品質
- デザイン
- 機能性
- ブランドイメージ
- アフターサービス
ターゲットとする顧客層にとって何が決め手になるのか、アンケート調査やインタビュー、SNSでの声の分析などを通じて明らかにしましょう。
似たようなTシャツが並んでいる中で最終的に一番安いものを選ぶ顧客が多ければ、その層にとってのKBFは「価格」ということになります。一方で、高くてもオーガニック素材にこだわった商品を選ぶ人が多い市場であれば、「品質(安全性)」や「ブランドの信頼性」がKBFかもしれません。
顧客視点を最優先する理由
KBFを特定する際には、顧客視点を最優先することが重要です。自社が強みと感じる点でも、顧客にとって価値がなければ意味のない特徴になってしまいます。
例えば、あるスマートフォンのメーカーが「自社の新機種は特殊な素材で耐久性が非常に高い」と考えても、ユーザーがそれを重要視していなければ差別化要因にはなりません。それよりも「SNS映えする高画質なカメラ機能」の方が購入の決め手になることも多いでしょう。
したがって、このステップではターゲット顧客が本当に求めている価値は何かを徹底的に探ります。この顧客ニーズ・KBFの分析結果が、次のポジショニング設定でどの軸で差別化を図るべきかを判断する材料となります。
STEP3:ポジショニング軸の設定とマップ作成
ポジショニングの方向性を具体化するために、縦軸・横軸の二つの視点で市場をマッピングします。これをポジショニングマップと呼びます。
ポジショニング軸の選び方
まず、STEP2までの分析から自社と競合を比較するのに有効な2つの軸を選びましょう。軸に設定する要素は、前述のKBFを踏まえて顧客が商品を評価・比較する基準となるものを選びます。
【具体例】
- 「価格(高い・低い)」×「品質(高品質・低品質)」
- 「デザイン(シンプル・個性的)」×「性能(多機能・シンプル機能)」
重要なのは、選ぶ2つの軸が互いにあまり相関しない要素であることです。例えば「性能」と「機能数」はほぼ同じ意味になりやすいため、一方を「価格」に変えるなど、異なる切り口の組み合わせにします。
マップの作成方法
軸が決まったら、次に競合各社の製品・サービスをマップ上にプロットしていきます。各競合が選んだ二軸上でどの位置に当てはまるかを調査データや客観的な指標に基づいて配置します。
縦軸に「価格(高⇔低)」、横軸に「品質(高⇔低)」を取った場合、以下のように配置します。
| 競合 | 位置づけ |
|---|---|
| A社 | 高品質・高価格 |
| B社 | 低品質・低価格 |
| C社 | 高品質・中価格 |
なぜマップが有効なのか
ポジショニングマップを作成することで、市場全体のポジション関係が一目で分かるようになります。この図を眺めると、競合が密集している領域(競争が激しいゾーン)や、まだどのブランドもいない空白の領域が浮かび上がります。
空白領域は、新たな顧客ニーズが潜んでいる可能性があり、自社の商品コンセプトのヒントになるでしょう。逆に、競合が集中する領域で真っ向から戦うのは得策ではないかもしれません。このようにマップによって、自社が取るべきポジションの候補を視覚的に洗い出すことができます。
STEP4:自社商品のポジションと差別化ポイントの決定
ポジショニングマップを踏まえて、自社商品・サービスの取るべきポジションを具体的に決定します。すなわち、「どの顧客ニーズに対して、どんな独自の価値を提供するのか」という差別化ポイントを明確化する段階です。
ここでは、自社の商品特徴や強みと、ターゲット顧客が求める価値(KBF)とを照らし合わせながら、競合に負けない自社ならではの売りを打ち出します。
新しい価値の提案
例えば、前ステップで「高品質・低価格」の象限に顧客ニーズの空白が見つかったなら、自社の商品コンセプトを「手頃な価格で高い品質を提供するブランド」と定めることが考えられます。
あるいは既存の市場にない全く新しい価値を提案するポジションを取るのも有効です。実際に、1979年にソニーが初代ウォークマンを発売した際には、社内で「録音機能のない携帯テープレコーダーなんて売れるはずがない」という声もあったそうです。
しかしソニーは、単に「録音ができない小型テープレコーダー」としてではなく、「歩きながら音楽が聴ける」という全く新しい価値を打ち出すポジショニング戦略を取り、大ヒットにつなげました。この例は、既存の商品カテゴリーにとらわれずに顧客にとって新しいメリットを提示することで、競合不在の独自ポジションを築いた成功例と言えます。
訴求ポイントを絞り込む理由
自社のポジションを決定する際には、訴求ポイントを絞り込むことも重要です。あれもこれもと特徴を詰め込みすぎると、結局何が優れているのか伝わらなくなってしまいます。
経験的に、1人の顧客が特定の商品について強く認識できる特徴はせいぜい2つ程度までだと言われます。例えばデジタルカメラで「軽い・画質が良い・価格が安い・デザインが良い・操作が簡単・メモリー容量大」などといくつもアピールしても、情報過多で印象がぼやけてしまうのです。
そのため「ポータブルなのに高音質」「業界最安値なのに高性能」のように、最も伝えたい価値を大胆に絞り込むことが効果的です。絞り込んだ差別化ポイントこそが、自社のポジショニングを象徴するキーメッセージとなります。決定したポジションとメッセージは社内でも共有し、全員が一貫してその価値を伝えられるようにしておきましょう。
STEP5:ポジショニング戦略の実行と検証
最後に、決定したポジショニングを実際のマーケティング施策に落とし込み、効果を検証します。
戦略の具体化
ポジショニングは戦略として定めただけでは不十分で、それを具体的なマーケティング活動(製品開発やプロモーションなど)で体現してこそ意味があります。まず、マーケティングミックス(4P)の各施策をポジショニングに沿って設計しましょう。
商品そのものの機能やデザイン、価格設定、販路(チャネル)の選択、広告や販売促進のメッセージまで、すべてがポジショニングで決めた方向性と矛盾しないように整合させます。
「高級志向でプレミアムなブランド」というポジションなら、低価格を強調する広告を打つのはミスマッチですし、逆に「低コストが売り」の商品なのに高級百貨店だけで販売していては顧客に伝わりません。顧客に狙い通りのイメージを持ってもらうため、あらゆる接点で一貫したメッセージを届けることが大切です。
効果検証と改善
ポジショニング戦略を実行に移したら、その成果を検証し、必要に応じて調整する段階に入ります。具体的には、以下のような指標をモニタリングします。
- 製品の売上推移
- マーケットシェアの変化
- 顧客からのフィードバック
- 認知度や好意度調査の結果
狙ったポジション通りに顧客から評価されているか、競合の反応に変化はないか、といった点を定期的にチェックしましょう。
もし期待した成果が出ていない場合は、戦略を部分的に見直すことも必要です。例えば、以下のような要因が考えられます。
- ターゲット設定が極端にニッチすぎて市場規模が小さかった
- 伝えたかった価値がそもそも顧客に響いていなかった
- 競合がポジションを変えてきた
そうしたフィードバックを踏まえてポジショニングマップに再度手を入れ、軸や訴求ポイントを修正することも戦略の一環です。市場環境や顧客ニーズは時間とともに変化するため、ポジショニングも常に「検証→改善」を繰り返して磨き上げていく姿勢が重要と言えるでしょう。
ポジショニング戦略成功のポイント
以上の手順を踏まえてポジショニング戦略を実践する際、最後に押さえておきたい成功のポイントがあります。効果的なポジショニングを実現して競合に差をつけるために、以下の点に注意しましょう。
顧客のニーズを正確に理解する
戦略の出発点は常に顧客視点です。ターゲット顧客が何を求め、何に価値を感じるのかを正確に把握しましょう。顧客のニーズに合致しない差別化は意味がないため、事前の市場調査やユーザーインタビューを怠らないことが重要です。
競合にはない独自の価値を打ち出す
「他社には真似できない強み」を明確にすることで、顧客に選ぶ理由を提供できます。差別化ポイントはシンプルかつユニークであるほど効果的です。他社と似たような訴求では価格競争に陥るだけなので、発想を転換して自社ならではのポジションを狙いましょう。
訴求メッセージは絞り込んで一貫性を保つ
あれもこれもと盛り込みすぎず、1〜2つのキーコンセプトに絞って訴求します。決めたポジションに沿って、商品コンセプトから広告表現までトーンを揃えることが大切です。特に長年にわたり商品展開する場合、世代を超えて一貫したイメージを築くことでブランドへの信頼感も高まります。
ターゲット市場の規模と収益性を見極める
狙ったポジションがニッチすぎて市場が極端に小さいと、ビジネスとして成り立たない可能性があります。また、顧客が求める価値に対して適切な価格設定ができるか(収益を確保できるか)も検討しましょう。ポジショニング戦略を考える際は、理想だけでなく事業採算や市場規模といった現実面とのバランスも取る必要があります。
自社のブランド理念や強みとの整合性を図る
設定したポジションが自社の企業理念や長期戦略と矛盾していないか確認します。例えば、高級志向のブランドが「業界最安値」に舵を切るとブランド価値を損ねる恐れがあります。自社が本来持っている強み・得意分野を活かせるポジショニングにすることで、社内の実行力も高まり、継続的な改善努力がしやすくなります。
定期的に検証し、環境変化に適応する
ポジショニング戦略は一度決めたら終わりではありません。市場のニーズ変化や競合の新規参入など、状況は常に変わります。定期的にデータをモニタリングし、必要に応じてポジションや戦術を微調整しましょう。「軸を変えたら売上が改善した」「新たな空白領域を見つけた」などの発見があれば、迅速に戦略に反映させることが成功への鍵です。
以上のポイントを踏まえてポジショニング戦略を推進すれば、見込み顧客に「選ぶ必然性」を感じてもらえる商品を作り上げることができるでしょう。
まとめ
マーケティングにおけるポジショニングとは、簡単に言えば「自社の商品やサービスを、ターゲット顧客の心の中で唯一無二の存在として位置づけること」です。
ポジショニング戦略を正しく行えば、競合ひしめく市場の中でも自社の提供価値が埋もれずに伝わり、「この商品ならではの魅力があるから選ぶ」という必然性をお客様に感じてもらえるようになります。そのためには、市場と顧客の理解から始まり、差別化の軸の選定、ポジショニングマップの活用、訴求メッセージの絞り込み、そして一貫したマーケティング施策への展開まで、一連のプロセスを丁寧に進めることが大切です。
記事内で解説したように、ポジショニング戦略は決して一度きりの作業ではなく、実行と検証を通じて常に磨き上げていくものです。市場環境が変化しても軸がぶれない強いブランドは、常に適切なポジションを再構築しながら顧客の信頼を勝ち得ています。
ぜひ本記事の内容を参考に、皆さんの商品・サービスに最適なポジショニングを見つけ出し、マーケティング戦略の効果を最大化してみてください。きっと、今まで以上に自社の強みが輝き、顧客から選ばれる喜びを実感できるはずです。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。
ナレブロについて

「ナレブロ」は、ナレッジブログ(Knowledge Blog)の略称です。運営者自身が実務を通じて培ってきた知見や経験(ナレッジ)を惜しみなくアウトプットし、読者の皆さまに還元することを目的としています。
現代において、真に価値のある情報の多くはクローズドな場所に偏っています。だからこそ本ブログでは、オープンなプラットフォームでありながら、実戦で役立つ高鮮度な情報発信を追求しています。「マーケティング」や「スキルアップ」の知見を提供することで、志高く働く方々の「近道」となる。それがナレブロの運営理念です。
関連ページ:コンテンツ制作・運営ポリシー