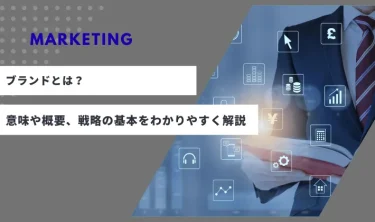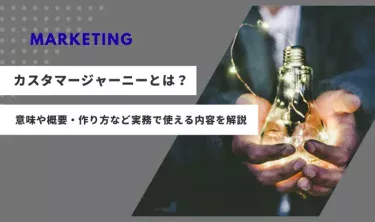マーケティング戦略で成果を求められる企業の担当者に向けて、マーケティングセグメンテーションの基本から具体的なやり方までを解説する記事です。市場を細分化して顧客をいくつかのセグメント(顧客グループ)に分け、それぞれに最適な戦略を立てることで、限られたリソースでも効果的に売上やビジネス成果を向上させる方法がわかります。
初心者にもわかりやすいように意味や重要性から順を追って説明し、実践しやすい手順や有名企業の事例も紹介します。
マーケティングセグメンテーションとは
マーケティングセグメンテーションとは、マーケティング分野において自社の製品やサービスの顧客となりうる市場を、特定のニーズや特性に応じて細分化し、いくつかの顧客グループに分ける手法です。
簡単にいえば「市場の細分化」を意味し、現代の多様化した消費者ニーズに対応するため不可欠なマーケティング戦略の出発点となっています。セグメンテーションによって顧客をグループ分けすることで、それぞれのグループの特徴やニーズを深く理解でき、効果的なマーケティング施策の土台を築くことができます。
ターゲティング・ポジショニングとの違い
マーケティング戦略を立案する際、セグメンテーションに続くステップとしてターゲティング(標的顧客層の選定)とポジショニング(選定顧客に対する自社の立ち位置の策定)があり、これら3つでSTP分析を構成します。セグメンテーションが市場を特性やニーズに基づいてグループ分けすることなのに対し、ターゲティングはその中から自社が狙うべきグループを選定すること、ポジショニングは選んだターゲットに対し自社製品やブランドをどのように位置づけ差別化するか決めることです。セグメンテーションが適切に行われなければ正しいターゲットの選定ができず、ポジショニング戦略の決定も難しくなります。したがって、STP分析の中でもセグメンテーションは最初の重要な工程と言えます。
マーケティングセグメンテーションの重要性
現代では顧客のニーズや購買行動が多様化しており、すべての顧客に一律のアプローチをしても効果を得にくくなっています。セグメンテーションによって市場を細分化することで、各セグメントごとに最適な戦略を立てられ、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ)を効果的に投下して投資対効果を最大化することが可能です。
実際、セグメンテーションを行えば各顧客グループのニーズを深く理解できるため、パーソナライズされた製品開発や心に響くメッセージ発信が可能となり、結果として売上や顧客満足度の向上が期待できます。正しく市場をセグメントしターゲットを絞ることは、無駄な広告費を抑えつつ高い反応を得るためにも重要と言えるでしょう。
マーケティングセグメンテーションの種類
市場をセグメント化する際には、さまざまな切り口(軸)で顧客を分類できます。この切り口はセグメンテーション変数とも呼ばれ、代表的なものに「地理的変数」「人口動態変数」「心理的変数」「行動変数」の4種類があります。
それぞれの概要と例を以下の表にまとめました。
| 変数の種類 | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 地理的変数(ジオグラフィック) | 国や地域、都市規模など地理的条件による分類。 | 例:「東京都在住」「勤務先が大阪府」 |
| 人口動態変数(デモグラフィック) | 年齢、性別、職業、所得、家族構成など人口統計的属性による分類。 | 例:「40代男性」「30代で子どもが一人いる夫婦」「年収500万円以上」 |
| 心理的変数(サイコグラフィック) | ライフスタイル、価値観、興味関心、性格など心理面の特徴による分類。 | 例:「趣味が旅行」「喫煙者」 |
| 行動変数(ビヘイビアル) | 購買履歴、利用頻度、ウェブ上の行動パターンなど行動データによる分類。 | 例:「商品Aを購入した経験がある」「直近1ヶ月以内に問い合わせしたユーザー」 |
一般的には、これら複数の変数を組み合わせて顧客グループを定義します。
例えば、地理的変数の「東京都在住」と人口動態変数の「30代男性」、心理的変数の「喫煙者」を組み合わせれば、「東京都に住む30代の男性喫煙者」といった具体的なセグメントが作成できます。このように定義したセグメントを、次に述べる評価基準で魅力度を判断し、最終的なターゲット(狙う顧客層)の選定につなげます。
マーケティングセグメンテーションの進め方と手順
マーケティングセグメンテーションは勘や思いつきで行うのではなく、論理的な手順に沿って進めることでその精度と実用性が高まります。
- STEP1: 市場分析とセグメント軸の設定
- STEP2: 顧客セグメントの分類とプロフィール分析
- STEP3: セグメントの評価とターゲット選定
ここでは、セグメンテーションを実施する標準的なステップを順番に解説します。
STEP1: 市場分析とセグメント軸の設定
まず初めに、自社が参入する市場全体の状況を把握します。市場規模や成長性、顧客の属性分布、競合他社の動向、外部環境のトレンド(PEST分析など)といったマクロ視点で情報収集・分析を行い、市場全体像を掴みます。市場理解を踏まえた上で、どの切り口で市場を分類するか(セグメンテーションの軸となる変数)を決定します。
先述した地理・人口動態・心理・行動などの代表的な変数を参考に、自社の製品や顧客特性に最も適したものを選びましょう。ポイントは変数を一つだけでなく複数組み合わせることです。
例えば「年齢」という人口動態変数だけで分けてもセグメント内の多様性が大きく有効な示唆を得づらいため、「年齢 × ライフスタイル(心理的)× 購買頻度(行動)」のように掛け合わせ、より具体的で意味のある顧客グループ像を浮かび上がらせます。
STEP2: 顧客セグメントの分類とプロフィール分析
STEP1で決めた軸に従って、市場に存在する顧客を具体的なグループ(セグメント)に分類していきます。アンケートデータがある場合はクラスター分析など統計手法を用いて、回答パターンが似ている顧客同士を自動的にグルーピングすることも可能です。また、手元にある顧客データや定性的な情報(インタビュー結果など)に基づき、チームでディスカッションしながら手動で分類していく方法も一般的です。この分類作業では、各セグメントについて「同じセグメント内の顧客はニーズや行動が互いに似ているか(同質性)」「異なるセグメントの顧客同士では明確に異なる特徴があるか(異質性)」を意識しましょう。理想的なセグメンテーションとは、セグメント内のばらつきが小さく、セグメント間の違いが大きい状態です。
セグメント分けができたら、各セグメントのプロフィール(特徴像)を詳細に分析・言語化します。セグメントごとに平均的な年齢や性別比、所得水準、職業、家族構成といった基本属性、重視する価値観やライフスタイル、抱えているニーズ・課題、自社商品に関する購買行動の傾向(情報収集源、購入頻度、価格感度など)、セグメント規模(属する顧客のおおよその人数)といった項目を明らかにしていきます。このプロフィール分析を深めることで、後のターゲティングやマーケティング施策の立案が格段にやりやすくなります。必要に応じて各セグメントを象徴する代表的な人物像(ペルソナ)を設定することも有効です。
STEP3: セグメントの評価とターゲット選定
複数のセグメントの詳細が明らかになったら、自社にとってどのセグメントが最も有望かを客観的な基準で評価します。代表的な評価フレームワークとして、「4Rの原則」と呼ばれる4つの指標が知られています。
- Rank(優先度):そのセグメントは自社の事業戦略やビジョンとの整合性が高く、優先的に狙う価値があるか。
- Realistic(有効性):ビジネスとして十分な売上や利益が見込める市場規模があるか。
- Reach(到達可能性):そのセグメントに自社の商品やマーケティングメッセージを的確に届けられるか。
- Response(測定可能性):そのセグメントの規模や特性を定量的に測定でき、施策の効果を検証できるか。
これらの基準に沿って各セグメントを比較検討し、自社にとって最も魅力的で実行可能なターゲットを絞り込みます。最後に重点アプローチすべきターゲットセグメントを決定します(これはSTP分析における「T」の工程です)。ターゲット選定のパターンとしては、最有望な単一セグメントに絞る集中型マーケティング、複数のセグメントを選んでそれぞれに異なる戦略を展開する差別型マーケティング、セグメントの違いを考慮せず市場全体に同じ製品・戦略で訴求する無差別型マーケティングなどがあります。
自社のリソースやビジョン、競合状況に照らして最適なターゲット戦略を検討しましょう。ターゲットが決まればセグメンテーション工程は完了し、次は選んだターゲットに対する自社の提供価値の設計(ポジショニング)へと進みます。
マーケティングセグメンテーション実施時の注意点
効果的にセグメンテーションを行うために、以下のポイントに注意しましょう。
4Rの原則を満たすか
設定したセグメントが先述の4R基準を満たしているか確認します。細かく分けすぎて市場規模が小さくなりすぎたり、利益に繋がらないセグメントを選んでしまうと、せっかく施策を実行しても成果に結びつかない恐れがあります。
客観的で明確な区分か
セグメントの定義が主観的すぎたり曖昧になっていないかチェックします。市場規模や特性が特定できないような漠然とした区分では効果的な戦略立案ができません。誰が見ても同じ解釈になる明確な基準でセグメントを設計しましょう。
ターゲティングに繋げられるか
分類したセグメントに対して実際にアプローチできなければ、セグメンテーションの意味がありません。選んだセグメントを狙うためにどんな施策・チャネルが有効かを考えながらセグメントを設定すると、後のターゲティングや施策実行がスムーズに進みます。
マーケティングセグメンテーションの活用事例
セグメンテーションの考え方が実際のマーケティング戦略でどのように活かされているか、著名企業の事例で確認してみましょう。
事例1:ユニクロの市場細分化戦略
ファッション小売大手のユニクロでは、従来の「20代女性」「40代男性」といった属性ベースのセグメンテーションではなく、「カジュアルかフォーマルか」「トレンドかベーシックか」という軸で市場を細分化しました。その結果、「カジュアルでベーシック」な商品の品揃えに注力し、1998年に発売されたフリースが大ヒット。「フリースといえばユニクロ」と言われるほどの大成功を収めています。このように、自社の商品特性に合った切り口で市場を再定義することで、新たなニーズに応える戦略が奏功した例と言えます。
事例2:コカ・コーラの多角的セグメンテーション
世界的飲料ブランドのコカ・コーラは、非常に多角的なセグメンテーションを行っています。年齢や性別といった基本的な属性だけでなく、ライフスタイルや価値観、さらには飲用シーンごとに細かく市場を分類しています。
例えば心理的変数の視点では、「健康志向」「甘いもの好き」「気分転換」といった志向でセグメント化し、それぞれにカロリーゼロのコーラ、通常のコカ・コーラ、フレーバー系コーラと対応する製品を展開しています。また行動(利用シーン)の視点では、「仕事中のリフレッシュ」「スポーツ・イベント中」「家族団らん時のテーブルドリンク」といった場面ごとに需要を想定し、プロモーションやパッケージデザインを調整しています。
つまりコカ・コーラは「いつ・誰が・どんな気持ちで飲むか」というあらゆる角度で市場を細分化し、それに基づいた商品設計とプロモーションを展開しています。この徹底したセグメンテーション戦略により、コカ・コーラは単なる炭酸飲料を超えて「文化」や「感情体験」を提供するブランドへと昇華させることに成功しています。
事例3:メルカリの競合回避戦略
フリマアプリ大手のメルカリは、競合サービスであるヤフオク!(Yahoo!オークション)との差別化のために、ユーザーの心理的動機による市場細分化を行いました。ヤフオク!が「少しでも高く売りたい」というニーズ(競り形式)に応えるのに対し、メルカリは「共感してくれる相手に売りたい」というシェア志向を重視する利用者に焦点を当てたのです。このセグメンテーションによってヤフオク!と直接競合しない新たな市場(いわゆるブルーオーシャン)を開拓し、国内で圧倒的な人気を獲得することに成功しました。
まとめ
マーケティングセグメンテーションはマーケティング戦略の基本であり、競争の激しい市場で効率よく成果を上げるための強力な武器となります。戦略の立案から個別施策の設計まで、さまざまな場面でターゲットの明確化に活用できる手法です。この記事で紹介した基本事項を理解したうえで、ぜひ自社の現在のターゲット設定を見直してみましょう。もし「見込み顧客全体に一律で同じ施策を打っている」「漠然としたターゲット設定しかしていない」という場合は、セグメンテーションからやり直すことで大きな効果アップが見込めます。
市場を適切に細分化し、選んだ顧客セグメントに資源を集中してアプローチすることで、限られたリソースでもマーケティング施策の成功率を高めることができるでしょう。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。
ナレブロについて

「ナレブロ」は、ナレッジブログ(Knowledge Blog)の略称です。運営者自身が実務を通じて培ってきた知見や経験(ナレッジ)を惜しみなくアウトプットし、読者の皆さまに還元することを目的としています。
現代において、真に価値のある情報の多くはクローズドな場所に偏っています。だからこそ本ブログでは、オープンなプラットフォームでありながら、実戦で役立つ高鮮度な情報発信を追求しています。「マーケティング」や「スキルアップ」の知見を提供することで、志高く働く方々の「近道」となる。それがナレブロの運営理念です。
関連ページ:コンテンツ制作・運営ポリシー