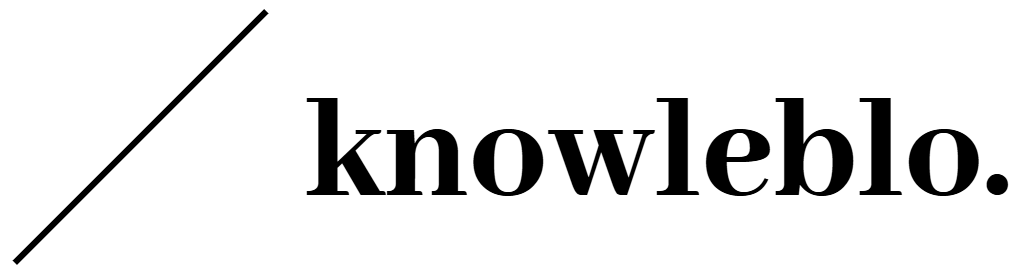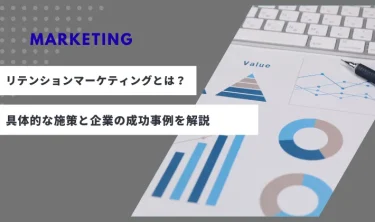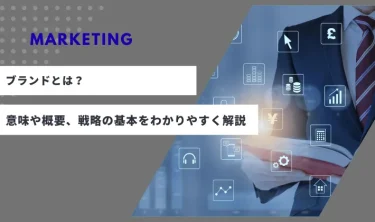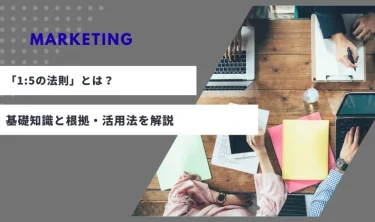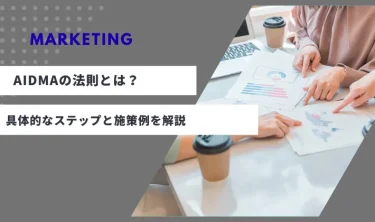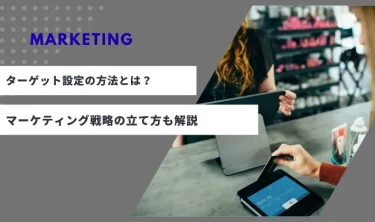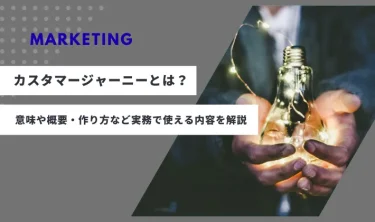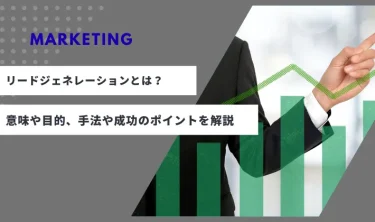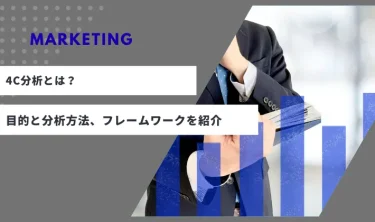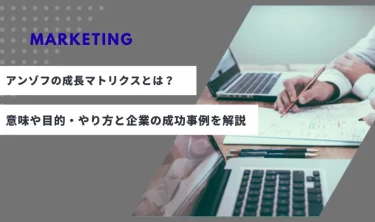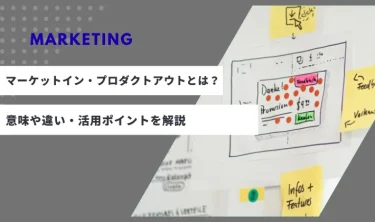マーケティング業界でよく耳にする「1:5の法則」をご存じでしょうか。
これは新規顧客よりも既存顧客を大切にすることでコスト削減や利益向上につながるという法則です。企業のマーケティング担当者で、専門用語に不慣れな初心者の方でも安心してください。本記事では、マーケティング1:5の法則の意味や効果をわかりやすく解説し、具体的な活用方法までご紹介します。
マーケティングにおける1:5の法則とは?
マーケティング1:5の法則とは、「新規顧客を獲得するためのコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかる」という経験則を指します。たとえば、既存顧客に追加購入してもらうのに1万円のコストがかかるとしたら、新規顧客を獲得して同じ売上を上げるには5万円かかる、といったイメージです。新規顧客への広告宣伝費や営業工数など獲得コストが非常に高いのに対し、一度商品やサービスを購入した既存顧客への再アプローチは比較的低コストで済みます。
この1:5の法則は、マーケティングの権威フィリップ・コトラー氏も著書で言及しています。コトラー氏は「新規顧客の獲得には既存顧客維持の5倍のコストがかかる」と述べており、顧客満足度を高め既存顧客を維持することが将来の市場シェア拡大に重要だと指摘しています。なお、この法則を初めて提唱したのは米国コンサル会社ベイン・アンド・カンパニーのフレデリック・F・ライクヘルド氏で、顧客ロイヤルティ(忠誠心)の重要性を説いたことで知られる人物です。
ポイントとして、「1対5の法則」と表記されることもありますが意味は同じです。新規顧客開拓は事業拡大に必要ではあるものの、コスト効率の面では既存顧客の維持に軍配が上がることを、この法則は示しています。つまり、限られた予算やリソースを効果的に使うには、新規ばかりに注力するのではなく現在の顧客との関係を深める戦略が欠かせないという考え方です。
5:25の法則とは?
5:25の法則とは、「顧客離れ(解約や流出)を5%改善できれば、利益率が25%改善される」という法則です。わずか5%の離脱防止で4分の1もの利益増につながるというインパクトの大きい内容であり、1:5の法則とセットで語られることが多いです。これは、既存顧客を維持できればできるほど収益性が飛躍的に向上することを統計的に示したものです。実際、ハーバード・ビジネス・レビューでも「顧客維持率を5%高めると利益が25%〜95%増加する」と報告されており、業種によっては25%を上回る大幅な利益アップが期待できる場合もあります。
5:25の法則の背景には、前述の1:5の法則が関係しています。既存顧客への販売コストが低い(=利益率が高い)ため、少しでも顧客離れを減らせば利益に大きく貢献するというわけです。言い換えれば、「新規顧客獲得よりも既存顧客の流出防止や単価向上に注力した方が、事業成長を効率的に達成できる」ことを示唆しています。多くの企業は売上拡大のために新規顧客数の増加に目を向けがちですが、既存顧客の維持こそが隠れた利益向上のカギである、というのが5:25の法則の伝えるメッセージです。
なお、1:5の法則と同様に5:25の法則もライクヘルド氏が発見したとされ、コトラー氏のマーケティング論にも組み込まれています。両者を組み合わせると、「同じコストを投下するなら既存顧客の維持に使った方が利益は向上する」というシンプルな結論になります。新規開拓はもちろん重要ですが、既存顧客の重要性を見失うと利益機会を逃すことになるのです。
既存顧客維持が重要な理由
1:5の法則と5:25の法則が示す通り、既存顧客の維持(リテンション)に注力することはマーケティング戦略上きわめて重要です。では具体的に、新規顧客より既存顧客を大事にすることで何がそれほど有利なのでしょうか。その主な理由を整理してみましょう。
コスト効率が圧倒的に良い
新規顧客の獲得には広告宣伝・営業など多大な費用がかかりますが、既存顧客への販促は低コストで済みます。新規獲得コストは既存の約5倍とも言われ、業界によっては「5〜25倍にもなる」という報告もあります。つまり1人の新規顧客を取る費用で、5人の既存顧客にアプローチできる計算です。結果として費用対効果が高まり、マーケティング予算を効率よく使えます。
購入率・成約率が高い
既存顧客は既に商品価値を理解し信頼しているため、新規より購入につながりやすい傾向があります。実際のデータでも既存顧客への提案の成約率は60〜70%と高く、新規見込み客では5〜20%程度にとどまるとされています。この差は歴然で、リピート客は初回客より約9倍も購入してくれるとも言われます。つまり、既存顧客の方が圧倒的に売上につながりやすいのです。
利益率が高い
既存顧客への追加販売はコストが低いため、そのまま利益率の高さにつながります。特に満足度の高い既存顧客は次回購入時により高額な商品を買ってくれる可能性も高く、客単価アップにも寄与します。逆に新規顧客は獲得コストが重く利益を圧迫しがちです。5:25の法則が示すように、わずかな離反防止で利益が大きく伸びるのは既存顧客の利益率が高いからこそです。
追加の売上機会(クロスセル・アップセル)が見込める
既存顧客はすでに自社と取引実績があるため、新たな関連商品や上位サービスを提案しやすいです。たとえば現在の利用プランからワンランク上のプランへのアップセルや、関連商品のクロスセルによって、無理なく売上を伸ばせます。新規顧客に一から説明し購入いただくよりも、ハードルが格段に低いのです。
紹介(口コミ)による新規顧客獲得効果
満足した既存顧客は、自社のアンバサダー(熱心な推薦者)となって周囲にサービスを紹介してくれる可能性があります。いわゆる口コミ効果で、新規顧客を広告費ゼロで連れてきてくれるわけです。この紹介経路の顧客は信頼度が高いため定着しやすいメリットもあります。新規獲得にお金をかけるより、既存顧客をファン化して自然な紹介を生む方が長期的に見て効果的です。
以上のように、既存顧客を大切にすることはコスト削減だけでなく売上拡大にも直結することがわかります。実際、コトラー氏によれば「企業は毎年平均して10〜20%の顧客を失っている」とも言われ、放っておけば顧客離れは常に起きるものです。だからこそ、流出を減らし既存顧客をつなぎ留める努力が企業の収益維持・向上に欠かせません。
では、新規顧客と既存顧客では具体的にどんな違いがあるのか、主なポイントを表にまとめてみます。
新規顧客と既存顧客の比較表
| 項目 | 新規顧客 | 既存顧客 |
|---|---|---|
| 獲得・販売コスト | 高い(既存の5倍程度) | 低い(新規の1/5程度) |
| 利益率 | 低い(コスト高のため利益圧迫) | 高い(コスト低減により利益寄与) |
| 商品・サービス理解度 | 低い(説明や教育が必要。初回購入への不安あり) | 高い(説明不要。内容を理解済み) |
| 購入転換率 | 低い(5〜20%程度) | 高い(60〜70%程度) |
| 将来の追加購買 | 不明(関係が浅く予測困難) | 期待大(満足度が高ければ継続購入・高額商品も購入) |
| 紹介(口コミ) | あまり期待できない | 期待できる(知人に紹介し新規客獲得に貢献) |
ご覧のとおり、新規顧客と既存顧客ではマーケティング上の扱いやすさが大きく異なります。特に既存顧客は「低コスト・高成約率・高利益・周囲への波及効果」という利点があり、ビジネスにおいてまさに「宝」とも言える存在です。1:5の法則と5:25の法則は、この違いを数値で端的に表現したものと言えるでしょう。
もちろん、新規顧客を増やさなくて良いという極端な意味ではありません。事業拡大には一定の新規開拓も欠かせませんし、新規顧客が将来の優良顧客に育つ可能性もあります。ただ、短期的な売上確保のキャンペーンばかりに頼って既存顧客をおろそかにすると、安定的な成長は望めないという点を強調したいのがこれらの法則の趣旨です。限られたリソースを賢く配分するためにも、今いる顧客を満足させ関係を維持する戦略が重要なのです。
1:5の法則を踏まえたマーケティング施策の活用方法
ここからは、1:5の法則を実際のマーケティング戦略に活かす方法について具体的に解説します。既存顧客の維持・活用にフォーカスしたリテンションマーケティングを進める上で、どのようなポイントに取り組めばよいのかをステップごとに見ていきましょう。
STEP1: 顧客セグメントを正しく見極める
まずは顧客のセグメンテーション(細分化)です。マーケティングの基本としてターゲット設定の重要性がよく説かれますが、既存顧客維持の観点でも同様です。自社の顧客を「新規顧客」と「既存顧客」に分け、それぞれに適切な戦略を立てることが第一歩となります。さらに既存顧客の中でも、特にロイヤルティ(愛着・忠誠心)が高く繰り返し購入してくれる優良顧客層を見極めましょう。有名なパレートの法則(80:20の法則)にもある通り、全顧客のうち上位20%ほどのコアなファンが売上の大半を支えているケースは珍しくありません。この最も重要な顧客層を特定できれば、以降の施策も効果的に絞り込むことができます。
例えばECサイトであれば、年間購入金額が高い上位顧客グループを抽出する、サブスクリプションサービスであれば長期間契約を続けている利用者をリストアップするといった具合です。それぞれのセグメントごとに適したアプローチを考えることで、限られたリソースを無駄なく投下できるようになります。
マーケティング戦略で成果を求められる企業の担当者に向けて、マーケティングセグメンテーションの基本から具体的なやり方までを解説する記事です。市場を細分化して顧客をいくつかのセグメント(顧客グループ)に分け、それぞれに最適な戦略を立てることで、[…]
STEP2: 顧客満足度を向上させる
顧客満足度(CS)を高めることは、既存顧客にリピート購入してもらうための基本中の基本です。商品・サービスに満足していなければ、顧客は離れていってしまいます。逆に言えば、不満要因を減らし満足度を上げることが離脱防止と継続利用につながるのです。
具体的には、自社の商品やサービスの品質向上はもちろん、顧客の声に耳を傾け改善を重ねる姿勢が重要です。購入後のアンケートやカスタマーレビューを収集・分析し、不満点や要望に迅速に対応しましょう。たとえば「問い合わせ対応が遅い」という声があればサポート体制を見直し、「商品説明が分かりにくい」という指摘があればマニュアルを改善するといった対応です。こうした改善により顧客との信頼関係が深まり、次も自社を選んでもらえる可能性が高まります。
また、初回購入時の不安を減らす工夫も満足度向上に寄与します。初めて利用する顧客には手厚いフォローを行い、安心してもらうことがリピートにつながります。例えば、ECサイトで初購入の顧客に対し丁寧なサンクスメールを送り使い方をフォローする、初回限定で使い切りサイズのサンプルを付けるなど、「また利用したい」と思える体験を提供しましょう。
STEP3: 顧客との継続的なコミュニケーションを図る
顧客と継続的にコミュニケーションを取ることも欠かせません。一度購入してくれたお客様でも、何も接点がないと徐々に関係は希薄になってしまいます。そこで、購入後も定期的に情報発信やコンタクトを行い、自社への関心を持続してもらう施策が重要です。
具体的な方法としては、メールマガジンやSNS、LINE公式アカウントなどを活用した情報提供があります。新商品の案内、キャンペーンのお知らせ、役立つノウハウ記事の配信など、顧客にとって価値のあるコンテンツを定期的に届けましょう。「あの会社からのメールは有益だから読んでいるうちについまた購入してしまう」と思ってもらえれば成功です。
また、顧客コミュニティの場を作ることも効果的です。自社ブランドのファン同士や担当スタッフと交流できるオンラインコミュニティやユーザーグループを用意すれば、顧客はブランドに愛着を持ち続けてくれます。これはまさに「企業と顧客との共創」の場であり、顧客からの率直な意見を聞ける貴重な機会にもなります。参加型のイベント(ウェビナーや限定セミナー等)を開催し、顧客とのつながりを深めることも長期的なリテンションに効果を発揮します。
リテンションマーケティング(Retention Marketing)は、既存顧客との関係を深め、継続的な売上を生み出すためのマーケティング手法です。新規顧客の獲得コストが上昇するなか、リピート率を上げてLTV(顧客生涯価値)を高めることが企[…]
STEP4: アップセル・クロスセルで顧客価値を高める
既存顧客への販売機会を最大化するため、アップセル(上位プラン・高価格商品の提案)やクロスセル(関連商品の提案)も積極的に検討しましょう。既に取引のある顧客は自社への信頼があるため、新しい提案にも耳を傾けてもらいやすいです。
アップセルの例としては、現在利用中のサービスの上位版や追加機能のあるプランへの誘導が挙げられます。例えばソフトウェアの無料プラン利用者に有料プランのメリットを伝えて移行を促すケースです。また、クロスセルの例では、パソコンを購入した顧客にプリンターや周辺機器を案内したり、服を買った顧客にコーディネート商品をおすすめしたりすることが考えられます。
ポイントは、顧客のニーズや購買履歴データを分析し、適切な提案を行うことです。ただやみくもに売り込みをかけると逆効果になりかねません。過去の購買商品や閲覧履歴から興味を予測し、「このお客様にはきっとこれが役立つ」というものを提示しましょう。適切なアップセル・クロスセルは、顧客にとっても新たな価値発見につながり、結果的に満足度向上と売上増の双方を実現できます。
STEP5: 優良顧客に特別な体験や特典を提供する
既存顧客の中でも特にロイヤルティの高い優良顧客には、一般顧客とは差別化した特別な体験や特典を提供することが効果的です。これは顧客のロイヤルティをさらに強化し、競合他社への乗り換えを防ぐ施策となります。
よくある手法としてロイヤルティプログラム(会員プログラム)があります。累積購入金額や利用年数に応じてランクを設定し、上位ランクの顧客にはポイント還元率アップ、送料無料、専用サポート窓口などの特典を付与します。クレジットカードのゴールド会員や航空会社の上級会員向けサービスなどが典型例です。こうした優遇策によって顧客は「特別扱いされている」と感じ、さらに長く利用してくれるようになります。
ただし、特典を金銭的なポイントや割引だけに頼りすぎるのは注意が必要です。ポイント目当てだけの顧客は、より条件の良い他社があればそちらに流れてしまう恐れがあります。そこで大切なのは、自社ならではの魅力的な体験を提供することです。例えば、ブランドの世界観を味わえるファンイベントに招待する、新商品を一般公開前にモニター体験してもらう、開発担当者と直接話せる座談会を開催する、といった心理的満足や共感を得られる施策が効果的です。優良顧客ほど自社への愛着が強いので、その愛着に応える特別な場を設けることでさらなるロイヤルファン化が期待できます。
このように、優良顧客にはポイントや割引以上の「思い出に残るサービス」を提供しましょう。それによって顧客は自社の良さをますます理解し、周囲の人にも積極的にその良さを伝えてくれるようになります。単なる顧客を超えてビジネスの良きパートナーになってもらえるのです。
マーケティングの現場で「ブランド」は重要なキーワードですが、「マーケティング ブランド」という言葉の意味や具体的な戦略について悩んでいませんか。企業のマーケティング担当者や初心者の方に向けて、本記事ではブランドマーケティングの基礎から効果的[…]
STEP6: アンバサダーを育成し紹介を促す
最後に、アンバサダーマーケティングの視点です。満足度が高く熱量のある顧客は、他の潜在顧客に対して最強の営業マンになってくれます。そこで、そうした自社のファン(アンバサダー)を育成し、紹介を促進する施策を行いましょう。
具体的には、紹介プログラムの導入が挙げられます。既存顧客が知人を紹介してくれた場合に、紹介者・被紹介者の双方に特典を提供する仕組みです。例えば「友達紹介で双方に○○円分のクーポン進呈」といった施策は多くのサービスで採用されています。紹介されて来た新規顧客は最初から信頼度が高く、その後の定着率も高い傾向があります。紹介者にとってもメリットがあるため、自発的に周囲へ声をかけてくれるようになります。
また、特典に頼らずともファン同士が口コミしやすい環境作りも大切です。前述のコミュニティを活用してユーザー事例を共有してもらったり、SNSでハッシュタグキャンペーンを行って投稿を促したりと、顧客発信による宣伝を後押ししましょう。特に昨今はインフルエンサーマーケティングなども注目されていますが、身近な人からの紹介の方が信頼度が高く持続的だという調査結果もあります。地道ではありますが、一人ひとりのファンを増やしていくことが長期的な顧客基盤拡大につながります。
以上、1:5の法則を踏まえた既存顧客重視のマーケティング施策を6つのステップに分けて紹介しました。これらを実践することで、「顧客を逃さず、ファンを増やす」好循環を生み出しやすくなるでしょう。
まとめ
マーケティング1:5の法則は、「新規顧客の獲得コストは既存顧客維持の5倍」というシンプルな経験則から、既存顧客を大切にすることの重要性を教えてくれます。さらに5:25の法則が示すように、既存顧客の離脱を防ぐことが利益率の向上につながるのも確かな事実です。これらの法則により、多くの企業が新規開拓一辺倒の戦略を見直し、顧客維持(リテンション)や顧客満足度向上に目を向けるようになっています。
企業のマーケティング担当者にとって、1:5の法則は予算配分や施策立案の指針となる考え方です。もちろん新規顧客の獲得も事業成長には必要ですが、限られたリソースの中で最大の成果を上げるには「既存顧客の維持 vs 新規顧客の獲得」のバランスを見極めることが重要です。市場環境や自社の成長フェーズによっても最適解は異なりますが、中長期的な視点で顧客との関係を育てる戦略を持つ企業は強い基盤を築けます。
本記事で解説したリテンションマーケティングの具体策(セグメント分析、顧客満足度向上、コミュニケーション継続、アップセル・クロスセル、特別体験提供、紹介促進)を組み合わせて実践すれば、既存顧客がより長く、そしてより多く自社に貢献してくれるようになるでしょう。それは同時に顧客にとっても価値ある体験を提供することになり、双方にメリットのある持続的なビジネス成長が期待できます。
マーケティング1:5の法則を正しく理解し活用することで、「顧客を大切にする企業は成果につながる」ということを実感できるはずです。ぜひ今日から、自社のマーケティング戦略に取り入れてみてください。短期的な売上だけでなく、長期的な顧客との絆がもたらす大きな成果にきっと驚くことでしょう。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。