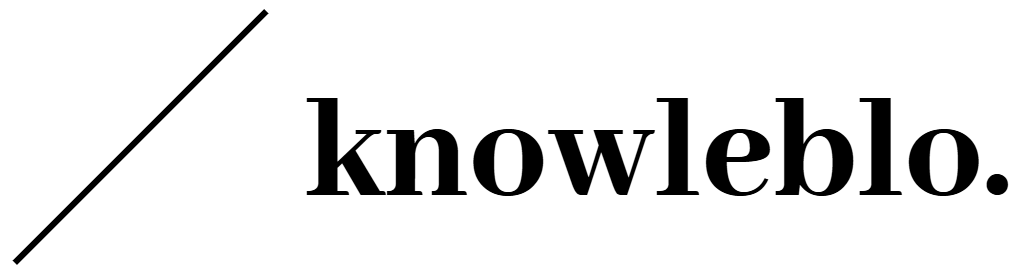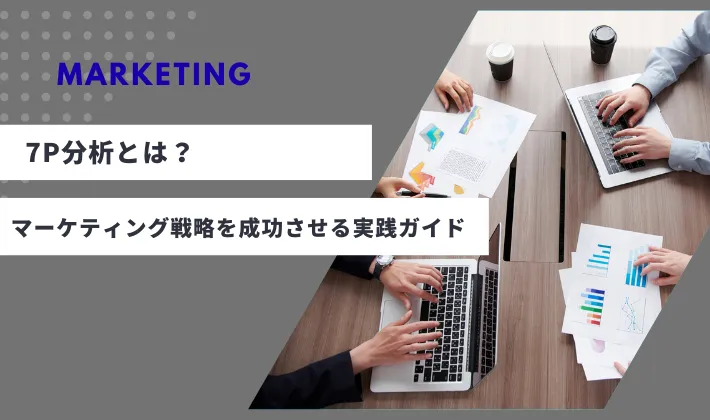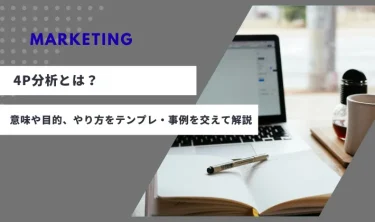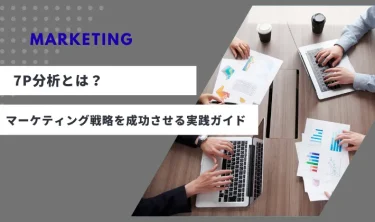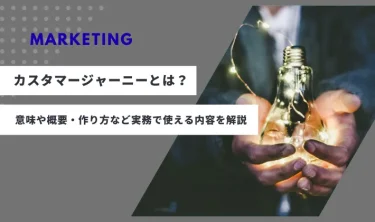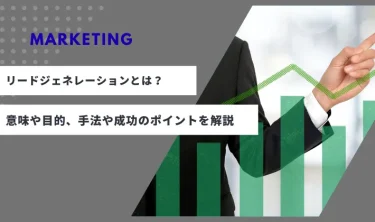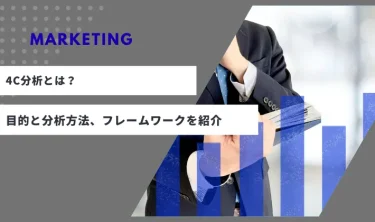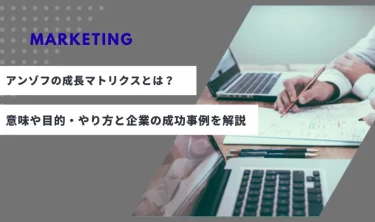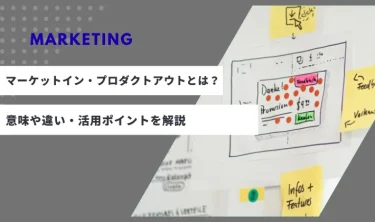マーケティング施策を実行しても成果が出ない、サービスの品質にばらつきがある、そんな課題を抱えていませんか。
7P分析は、製品・価格・流通・販促の基本要素に加えて、人・プロセス・物的証拠という3つの要素を組み合わせることで、サービスビジネスの課題を解決するフレームワークです。この記事では、7P分析の基本から実践的な使い方、テンプレート、成功事例まで、明日から使える形で解説します。
7P分析とは
7P分析とは、マーケティングミックスの基本である4P(Product/Price/Place/Promotion)に、People(人)、Process(プロセス)、Physical Evidence(物的証拠)の3つを加えた、サービスマーケティングのフレームワークです。
従来の4Pが製品中心の考え方だったのに対し、7P分析はサービスや顧客体験全体を設計するための道具として活用されます。特に無形のサービスを提供するビジネスでは、提供する人やプロセス、信頼を可視化する証拠が重要になるため、7つの要素を同時に設計することで一貫性のある顧客体験を実現できます。
例えば、美容クリニックを考えてみましょう。優れた施術メニューを用意するだけでは不十分です。カウンセラーの対応品質、来店から施術までの流れ、症例写真や認証マークなど、すべての要素が揃って初めてお客様は安心して予約できます。7P分析は、こうした要素を漏れなく設計し、矛盾をなくすための枠組みなのです。
4Pとの違い
7P分析と4P分析の最大の違いは、サービス提供における「人」と「プロセス」、そして「信頼の証拠」まで設計対象に含める点にあります。
4P分析は、製品やパッケージ商品のように、品質が安定していて一度購入すれば完結する取引に適しています。一方、7P分析はサービス業やサブスクリプションビジネスなど、人が関わり継続的な関係が生まれるビジネスに威力を発揮します。
なぜなら、同じ価格設定や広告訴求をしていても、接客の質や提供プロセスが異なれば、顧客満足度も解約率も大きく変わるからです。例えばSaaSビジネスでは、契約後のオンボーディングが不十分だと顧客は定着しません。広告費を増やしても、その後の体験が伴わなければ投資効果は上がらないのです。
7P分析を使うことで、価値提案から価格設定、販売チャネル、プロモーション、そして提供体制やプロセス、信頼の証まで、すべての整合性を取ることができます。これにより、無駄な施策を減らし、成果につながる投資に集中できるようになります。
「4P分析」は、製品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・販促(Promotion)をそろえて検討するための枠組みです。 この記事では、定義だけでなく、実務で使える手順やテンプレート、ミニ事例、注意点までを一つに[…]
7P分析の7つの要素
7P分析を構成する7つの要素について、それぞれ詳しく解説します。
各要素がどのように顧客体験に影響するのか、実務でどう設計すればよいのかを理解しましょう。
【7P分析の要素】
- Product(製品・サービス)
- Price(価格)
- Place(流通・販売チャネル)
- Promotion(販促・コミュニケーション)
- People(人・体制)
- Process(提供プロセス)
- Physical Evidence(物的証拠)
それぞれ詳しく解説します。
Product(製品・サービス)
Productでは、「誰に、どんな課題を、どう解決するか」を明確にします。これがすべての起点となるため、曖昧なまま進めてしまうと他の要素にもぶれが生じてしまいます。
具体的には、提供する価値を一言で言い切り、それをメニューやプランに落とし込みます。美容クリニックであれば「短時間で痛みが少なく、自然な仕上がりを実現する」といった価値軸を設定し、各施術メニューには施術時間・ダウンタイム・保証内容を明記します。
SaaSビジネスの場合は「導入の手間を最小限に抑え、チャットで即座にサポートする」といった核となる価値を定義し、機能リストを「顧客が得られる成果」に紐づけて整理します。品質基準や例外対応のルールもこの段階で決めておくことで、以降の価格設定や教育内容の判断基準となります。
製品やサービスの定義が明確であるほど、チーム全体が同じ方向を向いて施策を実行できるようになります。
Price(価格)
Priceでは、単純な価格設定だけでなく、料金体系全体を設計します。単発購入か定期購入か、従量課金か年額契約か、どの体系を選ぶかで顧客の購入ハードルや継続率が変わるからです。
また、価格の表示方法や支払い方法、割引条件、返金ポリシーなども含めて設計する必要があります。サービスや商品で得られる価値と実際の支払いに矛盾が生じると、離脱率やクレームが増加するからです。
D2Cビジネスでは、常時割引を避け、期間限定や数量限定でメリハリをつけることで価値の毀損を防げます。SaaSでは、月額プランと年額プランの差を明確にし、年額プランは稟議を通しやすいシンプルな条件にすることが重要です。
税込表記の統一、解約条件の明示、返金ポリシーの明確化など、細部まで整えることでカート離脱や返金対応などを減らし、顧客体験を向上できます。
Place(流通・販売チャネル)
Placeでは、顧客がどこで、どのように商品やサービスを受け取るかを設計します。現代ではオンラインとオフラインを組み合わせたオムニチャネル戦略が前提となります。
購入や利用の機会、提供スピードは顧客満足度や生涯価値に直結します。ECを中心とするビジネスなら、在庫配分と入荷通知の仕組みを整えることが重要です。店舗も併用する場合は、予約枠と在庫を一元管理し、チャネル間でスムーズな体験を提供する必要があります。
SaaSビジネスでは、直販と代理店の役割分担を明確にし、PoC(概念実証)や導入支援の有無と責任範囲を文書化します。チャネル間で価格や特典に差を設ける場合は、明確なルールを定めて社内で齟齬が出ないようにします。
販売チャネルの設計が整っていると、顧客は自分に合った方法でスムーズに購入・利用でき、満足度が高まります。
Promotion(販促・コミュニケーション)
Promotionでは、複数の媒体を横断して一貫したメッセージを届ける設計をします。媒体ごとにメッセージが変わると、顧客の記憶に残らず、比較検討段階での離脱率が高まるからです。
B2Cビジネスなら「低刺激・専門家監修・テスト済み」といった核となるメッセージを設定し、検索広告では比較情報、SNSでは実感や体験談、動画ではストーリーと、媒体特性に応じて情報の濃度を調整します。
B2Bビジネスでは「導入負担が最小・即座にサポート」を軸に、資料の構成を「導入事例→比較表→ROI試算」の順に再構成します。第三者評価であるレビュー、認証マーク、専門家の監修情報などを早い段階で提示することで、信頼の根拠を示すことができます。
媒体配分はPESO(Paid/Earned/Shared/Owned)モデルなどを参考に、予算と目的に応じてバランスを取ります。
People(人・体制)
Peopleでは、サービスを提供する人材の採用、教育、評価までを設計します。サービスの品質は、誰が提供するかによって大きく変わるからです。
美容クリニックであれば、カウンセラーに対して傾聴力、説明力、同意形成のスキルを磨くトレーニングを実施します。評価は成約率だけでなく、顧客満足度やクレーム率など質の指標も含めることで、バランスの取れた接客を促せます。
SaaSビジネスでは、オンボーディング担当者にプロダクトの知識だけでなく、顧客の業務理解と課題把握の研修を実施します。エスカレーション(上位者への引き継ぎ)の基準を共有し、対応品質のばらつきを防ぎます。
属人化を避け、誰が対応しても同じ水準のサービスを提供できる体制を整えることが、顧客満足度と事業の拡張性を両立させる鍵となります。
Process(提供プロセス)
Processでは、顧客が申し込みや来店をしてから、サービスを受け、アフターフォローを受けるまでの一連の流れを設計します。体験のばらつきが離脱や不満の原因となるため、標準手順(SOP)を明確に定義します。
美容クリニックなら「予約→事前案内→当日受付→カウンセリング→施術→アフター連絡」という流れを分単位で設計します。待ち時間の目標値を設定し、それを超えた場合の対応も決めておきます。
SaaSビジネスでは「契約→キックオフミーティング→初期設定→初回の価値体験→効果測定→機能拡張」といったマイルストーンを設定します。各ステップの標準所要時間を定め、遅延が発生した場合の閾値とエスカレーション基準を明確にします。
プロセスを可視化することで、ボトルネックが明らかになり、改善の優先順位をつけやすくなります。
Physical Evidence(物的証拠)
Physical Evidenceでは、無形のサービスを可視化し、信頼を伝える要素を設計します。顧客は不確実性を嫌うため、目に見える証拠によって不安を解消します。
美容クリニックであれば、施術前後のビフォーアフター写真、掲載基準、顧客の許諾や加工ルールを明確にします。受付の清潔感、スタッフの身だしなみ、院内の雰囲気なども重要な物的証拠です。
SaaSビジネスでは、導入実績、監査対応の記録、セキュリティ認証を一覧化し、顧客が簡単にアクセスできるようにします。資料のデザイン品質、Webサイトの第一印象、SLA(サービスレベル契約)の明示なども信頼を構築する要素です。
証拠が自然に目に入る配置を工夫することで、顧客は安心して購入や契約の決断ができるようになります。
7P分析の作り方
7P分析を実務で活用するための具体的な手順を5つのステップで解説します。
各ステップの目的と、なぜそのステップが必要なのかを理解することで、形骸化せず実用性のある分析ができるようになります。
STEP1:目的・KPI・制約を明確にする
最初に「何を達成したいのか(目的)」「何で成果を測るのか(KPI)」「どんな制約があるのか(予算・人員・法規制・設備)」を一文で定義します。
このステップが必要な理由は、ここが曖昧だと各要素の判断基準がぶれてしまい、整合性のある設計ができなくなるからです。すべての施策は、この一文に照らして「妥当かどうか」を判断します。
【記載例】
「第3四半期に新規売上を20%増加させる。KPIはコンバージョン率と投資回収月数。制約条件は広告予算の上限300万円、施術室2室、薬機法による表現制限」
この一文があることで、価格設定の妥当性、媒体への予算配分、予約枠の設計、広告表現の限界まで、すべての判断軸が定まります。
チーム内の議論も「この施策は目的とKPIに対して効果的か」という基準で進められるようになります。
STEP2:事実とデータを収集する
次に、判断の根拠となる事実とデータを収集します。主観や思い込みではなく、数値と出典のある情報を集めることで、課題の優先順位と改善の方向性が明確になります。
【収集すべき情報】
- 顧客インサイト(検索クエリ、レビュー内容、解約理由)
- 競合情報(価格設定、購入導線、提示している証拠)
- チャネルデータ(到達率、獲得単価、在庫回転率)
- 現場の実態(待ち時間、問題解決にかかる時間、クレーム内容)
【記載例】
「”低刺激”の検索クエリが前年比22%増加」「カート離脱率68%」「平均待ち時間14分」「症例写真の掲載が競合より少ない」
このように数値で事実を整理すると、どの要素から改善すべきか(例:プロセスの待ち時間、物的証拠の不足)をチーム内で合意しやすくなります。
感覚ではなくデータに基づく議論ができるため、施策の優先順位も明確になります。
STEP3:7Pに情報を当てはめて整合性を確認する
収集した事実を7Pの枠組みに当てはめ、要素間の矛盾を洗い出します。このステップが重要なのは、矛盾の解消こそが顧客体験の改善と成果向上の最短ルートだからです。
一枚の表に7つの要素を並べ、矛盾している箇所を赤字でマーキングします。例えば「高品質を訴求しているのに常時割引をしている」「安心を謳っているのに証拠が不足している」「短時間を売りにしているのに待ち時間が長い」といった矛盾です。
【記載例】
Promotionで「低刺激・安心」を訴求すると決めたら、Productでは保証内容を明示し、Physical Evidenceでは成分データや認証を増やし、Processでは施術時間を短縮する、といった連鎖を同時に設計します。
表の中で要素同士を線で結び、整合性をチェックしながら調整していくことで、一貫性のある顧客体験が実現します。矛盾を放置すると、どれだけ個別の施策を磨いても成果は限定的になってしまいます。
STEP4:予算・体制・手順・媒体計画を数値化する
整合性が取れたら、次は実行計画を具体的な数値と責任者に落とし込みます。計画が数字と担当者に紐づいていないと、現場で実行されず絵に描いた餅になってしまうからです。
決めるべき項目
- 予算配分(ブランド広告60%、刈り取り広告40%など)
- 人員配置と教育計画(カウンセラー研修を月2回実施)
- 標準手順(平均待ち時間を10分以内に短縮)
- 物的証拠の強化(症例写真を月10件掲載)
- 媒体プラン(検索広告30%、動画20%、SNS30%、メール20%)
【記載例】
「検索広告に月90万円、動画制作に月60万円、SNS運用に月90万円、メールマーケティングに月60万円を配分。カウンセラーは毎月第2・第4水曜日に2時間の研修を実施。受付から施術開始までの平均時間を10分以内に短縮し、週次で測定。症例写真は毎月10件以上掲載し、許諾とガイドラインに従う」
各項目に担当者、期限、測定方法をセットで記載し、定例会議で進捗を確認します。数値化されているからこそ、達成できているか、改善が必要かの判断が可能になります。
STEP5:小規模テストで検証して改善する
7Pのミックスは仮説に過ぎません。実際の顧客の反応を見ながら、継続的に改善していく必要があります。影響が大きく変更しやすい箇所から優先的にテストし、結果をKPIで評価して分析表に反映させます。
テストすべき項目の例
- ランディングページの訴求メッセージ(低刺激vs価格重視)
- 初回価格の提示順序
- 予約フローの短縮
- 症例写真の配置位置
- 接客トークスクリプトの変更
【評価指標の例】
コンバージョン率、顧客獲得コスト、待ち時間、NPS(顧客推奨度)、レビューの件数と評価
【記載例】
「ランディングページのメイン訴求を”低刺激”と”初回50%オフ”の2パターンでA/Bテストを2週間実施。コンバージョン率と獲得コストで評価し、優れた方を採用。その結果を次回の7P分析表に反映する」
四半期ごとの定例会議に「予算配分の見直し」「標準手順の更新」という固定議題を設け、継続的に運用を回していくことが重要です。小さく試して学習し、改善を積み重ねることで、7P分析の精度が高まっていきます。
7P分析のテンプレート
実務で使える7P分析のテンプレートを用意しました。このテンプレートに沿って記入することで、重要な要素を漏れなく整理できます。
| セクション | 記入内容 |
|---|---|
| 目的・KPI・制約 | Q3の新規売上20%増加 / KPIはCVRと回収月数 / 広告予算300万円、施術室2室、薬機法の表現制限 |
| Product(製品・サービス) | 価値:低刺激・短時間・自然な仕上がり / メニュー・保証内容・品質基準を明記 |
| Price(価格) | 月額制/都度払いの選択肢 / 税込表記 / 期間限定割引 / 返金条件の明示 |
| Place(販売チャネル) | ECサイトと店舗 / 在庫と予約の一元管理 / 出荷・待ち時間のSLA設定 |
| Promotion(販促) | メッセージ「低刺激・専門家監修」/ 媒体ごとの配分と訴求の濃度調整 |
| People(人・体制) | 採用基準 / 教育計画(研修頻度と内容)/ 評価指標(成約率・満足度・クレーム率) |
| Process(プロセス) | 来店から提供、アフターまでのSOP / 待ち時間と解決時間の目標値 |
| Physical Evidence(物的証拠) | 症例写真・レビュー・認証マーク / 資料デザイン / 店舗の清潔感基準 |
| 予算・人員・媒体 | 月次予算配分 / 人員配置表 / 媒体別カレンダー |
| 担当・期限・測定 | 各施策の責任者 / 実施期日 / 測定方法とKPI |
このテンプレートを使用する際は、まず上から順に埋めていき、STEP3で横の整合性を確認しながら調整していくと効率的です。
7P分析のKPI設定
7Pの各要素に対して適切なKPIを設定することで、施策の効果測定と改善が可能になります。
以下の表を参考に、自社のビジネスに合わせてKPIを設定しましょう。
| 要素 | KPI例 | 測定の目的 |
|---|---|---|
| Product | 商品稼働率・返品率・苦情発生率 | 製品やサービスの品質と適合度を測る |
| Price | 顧客獲得コスト(CAC)・投資回収月数・平均単価 | 価格戦略の効果と収益性を測る |
| Place | 在庫回転率・欠品率・予約待ち時間 | チャネルの効率性と顧客の利便性を測る |
| Promotion | 想起率・クリック率(CTR)・コンバージョン率(CVR)・獲得単価(CPA) | プロモーションの到達度と効果を測る |
| People | 成約率・顧客満足度(CS)/NPS・一次解決率 | 人材の対応品質と顧客への影響を測る |
| Process | 平均解決時間・再来店率・キャンセル率 | プロセスの効率性と顧客体験を測る |
| Physical Evidence | レビュー件数と評価・症例掲載数・資料閲覧率 | 信頼構築の効果を測る |
これらのKPIは月次または週次で測定し、定例会議で確認することで、改善のサイクルを回すことができます。
KPIが悪化している要素があれば、その原因を7P全体の整合性の中で検討し、対策を講じます。
7P分析の成功事例
実際のビジネスで7P分析を活用し、成果を上げた事例を2つ紹介します。
事例1:美容クリニック(BtoC)
課題
7P分析による改善
- Promotion: 「低刺激・自然な仕上がり」というメッセージを維持
- Product: 施術時間・ダウンタイム・保証内容を明文化
- People: カウンセリングの傾聴スキルと説明スクリプトを刷新し、研修を強化
- Process: 受付から施術開始までの待ち時間を14分から9分に短縮
- Physical Evidence: 症例写真を月10件ずつ掲載し、認証ロゴを上部に配置
成果
7Pの整合性を取ることで、顧客の不安が解消され、定着率が大きく改善した事例です。
事例2:SaaS企業(BtoB)
課題
7P分析による改善
- Product: 「導入の手間最小・即座にサポート」という価値を明確に再定義
- Price: 年額プランを稟議通過しやすいシンプルな条件に設計
- Place: 直販と代理店でオンボーディング枠を確保し、役割分担を明確化
- Promotion: 資料構成を「導入負担の少なさ→ROI→競合比較」の順に変更
- People: カスタマーサクセス担当に顧客業務の理解を深める研修を実施
- Process: 「初回の価値体験を7日以内に」という標準手順を設定
- Physical Evidence: 導入実績と監査対応の記録を早い段階で提示
成果
契約後の体験を7P全体で再設計したことで、顧客の成功体験が早まり、継続利用につながった事例です。
7P分析とデジタルマーケティングの連携
7P分析は、デジタルマーケティングの各種ツールやデータと組み合わせることで、さらに効果を高めることができます。
カスタマージャーニー(顧客の体験の流れ)やファネル分析(各段階での歩留まり)と7P分析を往復させることで、改善ポイントがより具体的になります。例えば、ファネル分析で「カート到達後の離脱率が高い」と分かれば、7PのPriceやProcessを重点的に見直すといった判断ができます。
データはGoogle Analytics 4、CRM、カスタマーサクセスツールなどで一元管理し、目的・KPI・7P・実行カレンダーを同じダッシュボードで確認できるようにします。これにより、施策の実行状況と成果を常に可視化できます。
媒体配分はPESO(Paid/Earned/Shared/Owned)モデルなどを参考に決定し、メッセージは7P分析で定義した一言を統一し、媒体特性に応じて情報の濃度だけを調整します。施策の変更はA/Bテスト計画とセットにし、四半期の見直し会議で必ず分析表に反映させる運用にすることで、継続的な改善サイクルが回ります。
マーケティング施策を考える際、「何から手をつければいいかわからない」「チーム内で議論がまとまらない」といった悩みを抱えていませんか。そんなときに役立つのが「マーケティングフレームワーク」です。 本記事では、マーケティングフレームワーク[…]
7P分析における法規制とリスク管理
7P分析を実施する際は、関連する法規制を必ず確認し、コンプライアンスを守る必要があります。
販促表現は景品表示法、医療・美容サービスは薬機法(医薬品医療機器等法)、通信販売は特定商取引法、個人情報の取り扱いは個人情報保護法の対象となります。誇大広告や根拠のない効能表現、常時割引による優良誤認、顧客の体験談の不適切な利用などは、指摘や処分の対象となる可能性があります。
特に薬機法の効能表現については、ガイドラインに沿った表現を使用し、レビューや症例写真は顧客の許諾と加工基準を明確に定めます。標準手順(SOP)に法務レビューの工程を組み込み、公開前に必ずチェックを通す運用にすることで、手戻りやリスクを最小限に抑えられます。
法規制は頻繁に更新されるため、定期的に最新情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。コンプライアンス違反は企業の信頼を大きく損なうため、7P分析の初期段階から法規制の確認を組み込むことが重要です。
7P分析でよくある失敗と対策
7P分析を実務で活用する際に、よくある失敗パターンとその対策を紹介します。これらを事前に把握しておくことで、効果的な分析と施策実行が可能になります。
失敗1:要素間の整合性が取れていない
最も多い失敗は、4Pで決めた製品価値とPeople/Process/Physical Evidenceが一致しておらず、顧客体験が分断されてしまうケースです。例えば、プロモーションで「高品質・丁寧なサービス」を訴求しているのに、実際のスタッフ教育が不十分で対応品質にばらつきがあったり、待ち時間が長くてプロセスが洗練されていなかったりする状況です。
対策
まず目的とKPIを一文で明確に固定し、7P分析の表を作成して要素間の矛盾を赤字でマーキングします。矛盾が見つかったら、すべての要素が同じ方向を向くように調整してください。一つの要素だけを変更するのではなく、連動する要素も同時に見直すことで、一貫性のある顧客体験を実現できます。
失敗2:属人化により品質が安定しない
サービスの提供が特定の人材に依存してしまい、担当者によって品質にばらつきが出るケースです。優秀なスタッフ一人に頼りすぎると、その人が不在の時や退職した時に大きな影響が出ます。
対策
Peopleの要素で教育計画を明確にし、Processで標準手順(SOP)を文書化します。誰が対応しても同じ水準のサービスを提供できるよう、マニュアルや研修プログラムを整備します。定期的なロールプレイングや事例共有の場を設けることで、チーム全体のスキルを底上げできます。
失敗3:物的証拠が不足している
サービスの価値を可視化する証拠が不十分なため、顧客が不安を感じて購入や契約をためらってしまうケースです。特に高額なサービスや新しいサービスでは、信頼の証拠が重要になります。
対策
Physical Evidenceを強化し、症例写真、導入事例、顧客レビュー、認証マーク、専門家の推薦などを早い段階で提示します。掲載する際は、顧客の許諾を必ず取得し、加工ルールや掲載基準を明確にしてコンプライアンスを守ります。Webサイトやパンフレットなど、顧客が最初に接するタッチポイントに重点的に配置しましょう。
失敗4:すべてを一度に改善しようとする
7P分析で多くの課題が見つかると、すべてを同時に改善しようとして失敗するケースがあります。リソースが分散し、どの施策も中途半端になってしまうのです。
対策
改善項目を「影響度×実行の容易さ」のマトリクスで整理し、優先順位をつけます。影響が大きく比較的簡単に実行できる施策から着手し、小規模にテストして効果を確認します。成果が出たら次の施策に進むという形で、段階的に改善を進めることで、着実に成果を積み上げられます。
失敗5:一度作成したら見直さない
7P分析を一度作成しただけで終わり、その後の見直しや更新をしないケースです。市場環境や顧客ニーズは常に変化するため、定期的な見直しが必要です。
対策
四半期ごとに定例の見直し会議を設定し、「予算配分の見直し」「標準手順の更新」という固定議題を設けます。A/Bテストの結果やKPIの変化を必ず7P分析表に反映し、継続的に改善するサイクルを回します。PDCAを回す仕組みを組織に組み込むことで、7P分析が形骸化せず実効性を保てます。
7P分析を成功させるチェックリスト
7P分析を実行する前、または定期的な見直しの際に、以下のチェックリストを活用してください。すべての項目が満たされていれば、7P分析は単なる資料ではなく、実務で機能する運用の指示書となります。
基本項目
- 目的・KPI・制約が一文で明確に定義されている
- 7つの要素すべてに具体的な内容が記載されている
- 要素間の整合性が取れており、矛盾が解消されている
実行計画
- 標準手順(SOP)が文書化されている
- 教育・研修計画が具体的に決まっている
- 物的証拠(レビュー・認証・事例など)が用意されている
- 予算配分が明記されている
- 人員配置が明確になっている
- 媒体別のカレンダーが作成されている
測定と改善
- 各要素に対応するKPIが設定されている
- 測定方法が明確になっている
- A/Bテスト計画が添えられている
- 各施策に担当者が割り当てられている
- 実施期限が設定されている
- 定期的な見直しのスケジュールが決まっている
コンプライアンス
- 関連する法規制が確認されている
- 広告表現が法令に適合している
- 顧客情報の取り扱いルールが明確になっている
- 法務レビューの工程が組み込まれている
このチェックリストをチーム内で共有し、定期的に確認することで、7P分析の実効性を高めることができます。
まとめ
7P分析は、製品・価格・流通・販促という基本要素に、人・プロセス・物的証拠を加えることで、サービスビジネスにおける顧客体験を一貫して設計できるフレームワークです。
単に7つの要素を埋めるだけでなく、目的とKPIを明確にし、要素間の整合性を取り、数値で測定しながら継続的に改善していくことが重要です。この記事で紹介した5つのステップとテンプレートを活用すれば、明日から実務で使える7P分析を作成できます。
まずは自社のビジネスで目的とKPIを一文で定義することから始めてみてください。事実とデータを集め、7Pの表で矛盾を洗い出し、優先順位をつけて小さくテストする。このサイクルを四半期ごとに回すことで、投資の優先順位が明確になり、成果に直結する施策に集中できるようになります。
7P分析を活用して、一貫性のある顧客体験を設計し、ビジネスの成果を最大化していきましょう。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。