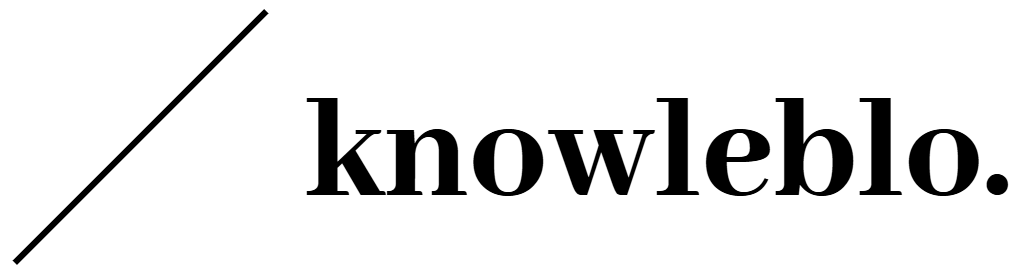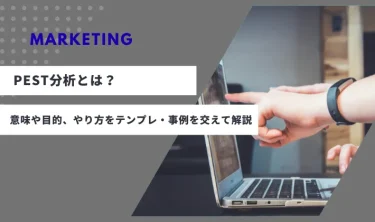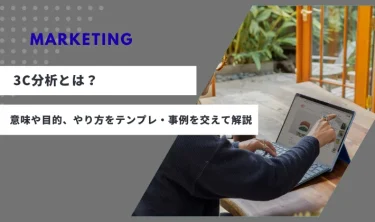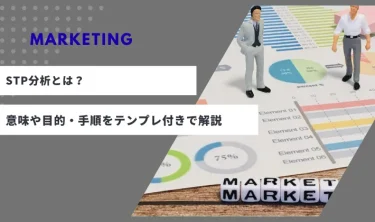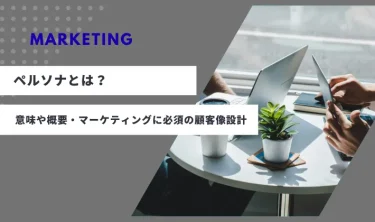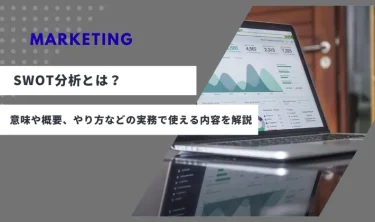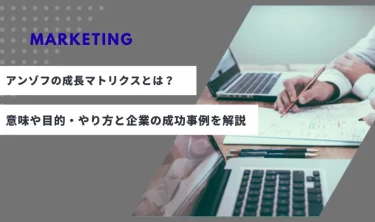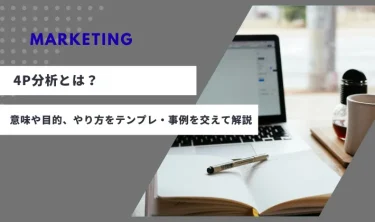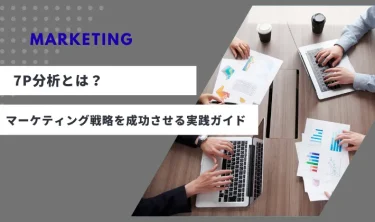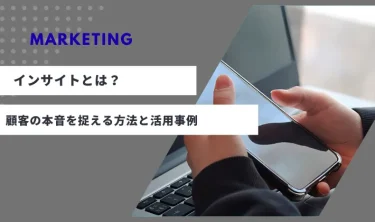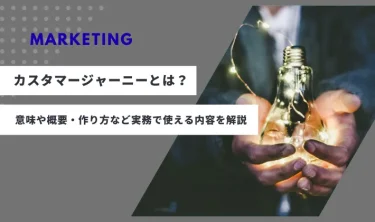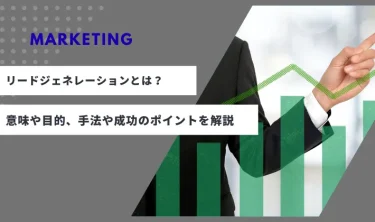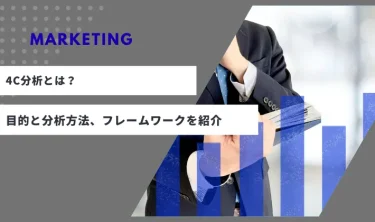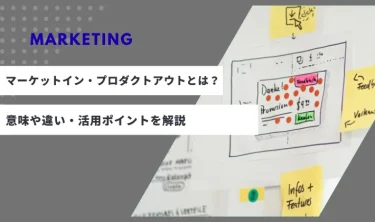マーケティング施策を考える際、「何から手をつければいいかわからない」「チーム内で議論がまとまらない」といった悩みを抱えていませんか。そんなときに役立つのが「マーケティングフレームワーク」です。
本記事では、マーケティングフレームワークの基本から、実務で使える主要フレームワークの種類、選び方、使い方まで、実践的な視点で解説します。最後には、すぐに使えるテンプレートもご紹介しますので、ぜひ明日からの業務に活用してください。
- 1 マーケティングフレームワークとは
- 2 マーケティングフレームワークを使う3つのメリット
- 3 マーケティングフレームワークの一覧表
- 4 【環境分析】外部環境・業界を理解するフレームワーク
- 5 【戦略設計】ターゲットと方向性を決めるフレームワーク
- 6 【施策設計】具体的な打ち手を作るフレームワーク
- 7 【体験設計】顧客の行動
- 8 【仕組み設計】体制とプロセスを整えるフレームワーク
- 9 【顧客分析】顧客価値を可視化するフレームワーク
- 10 【コミュニケーション設計】メディアと配分を最適化するフレームワーク
- 11 マーケティングフレームワークの選び方
- 12 フレームワークを組み合わせる際の注意点
- 13 マーケティングフレームワークの使い方・手順
- 14 すぐに使える!マーケティングフレームワークテンプレート
- 15 マーケティングフレームワーク活用事例
- 16 よくある失敗パターンと回避策
- 17 マーケティングフレームワーク実行前のチェックリスト
- 18 マーケティングフレームワークで成果を出すために
マーケティングフレームワークとは
マーケティングフレームワークとは、マーケティング活動を効率的に進めるための「思考の型」のようなものです。具体的には、環境分析から戦略設計、施策実行、効果測定まで、一連のマーケティング業務を体系的に整理し、考える順番と項目の抜け漏れを防ぐための枠組みを指します。
たとえば、新商品の発売を検討する場合、市場環境を把握し、競合を分析し、ターゲットを定め、価格や販売チャネルを決定する必要があります。フレームワークを使えば、これらのプロセスを順序立てて進められるため、思いつきではなく根拠に基づいた判断が可能になります。
フレームワークは自由な発想を制限するものではありません。むしろ、基礎となる分析や整理を効率化することで、より創造的な施策立案に時間を使えるようになります。部門や担当者が変わっても同じ手順で進められるため、組織全体のマーケティング品質を底上げする効果も期待できます。
マーケティングフレームワークを使う3つのメリット
マーケティングフレームワークを活用することで、以下の3つの大きなメリットが得られます。
【マーケティングフレームワークを活用するメリット】
- 意思決定のスピードが向上する
- 再現性や説明の説得力が高まる
- チーム内の共通言語や共通認識になる
それぞれ詳しく解説します。
メリット1:意思決定のスピードが向上する
フレームワークを使うと、議論が「個人の好み」ではなく「客観的な根拠」に基づいて進められます。たとえば、3C分析で顧客、競合、自社の状況を同じ粒度の指標で整理すれば、どの課題を優先的に解決すべきかが自然と見えてきます。
データに基づいた議論は合意形成を早め、意思決定にかかる時間を大幅に短縮します。変化の激しい市場環境では、このスピードが競争優位性につながります。
メリット2:再現性や説明の説得力が高まる
フレームワークは「なぜその結論に至ったのか」というプロセスを記録する役割も果たします。施策が成功した場合も失敗した場合も、どの要素が結果に影響したのかを分解して分析できるため、次回の改善につなげやすくなります。
また、上司や他部署への説明も容易になります。感覚的な判断ではなく、論理的な根拠を示せるため、予算承認や部門間の調整もスムーズに進みます。
メリット3:チーム内の共通言語や共通認識になる
「PEST」「STP」「4P」「カスタマージャーニー」といったフレームワークの用語を共有すると、マーケティング部門だけでなく、営業、制作、カスタマーサポートなど、異なる部門間でのコミュニケーションが円滑になります。
全員が同じ「地図」を見ながら仕事を進められるため、顧客体験の一貫性が保たれ、施策の効果も高まります。フレームワークは単なる分析資料ではなく、チーム全体で共有する「作業台」として機能します。
マーケティングフレームワークの一覧表
マーケティングフレームワークは数多く存在しますが、それぞれに適した目的や使用場面があります。
ここでは、主要なフレームワークを目的別に整理し、どの局面で何を使うべきかを一覧表でまとめました。
目的別フレームワーク一覧表
以下の表は、マーケティングの各段階で使用すべき代表的なフレームワークをまとめたものです。
| 目的・局面 | 主なフレームワーク | 主要アウトプット |
|---|---|---|
| 外部環境の把握 |
|
重要トレンドの短期・中期要約 |
| 業界・競争環境の把握 |
|
顧客・競合・自社の現状把握、業界圧力の見取り図 |
| 戦略の選択 |
|
ターゲット設定、戦略方向性、成長パスの決定 |
| 価値と施策の設計 |
|
価値提案、価格設定、チャネル選定、訴求内容の整合 |
| 顧客体験と歩留まり管理 |
|
顧客のつまずきポイント、KPI設定、改善優先順位 |
| 仕組み・体制設計 |
|
業務フロー、SLA設定、目標と責任の明確化 |
| 効果測定・最適化 |
|
メディア配分、効果測定、投資対効果の最適化 |
この表を基準にすれば、「今、自分たちのチームが取り組むべき課題には、どのフレームワークが適しているか」が明確になります。
次の見出しでは、各フレームワークの具体的な使い方を詳しく解説していきます。
【環境分析】外部環境・業界を理解するフレームワーク
マーケティング戦略を立てる際、まず取り組むべきは「自社を取り巻く環境の理解」です。外部環境や業界構造を正しく把握することで、戦略の方向性を見誤るリスクを減らせます。
この章では、環境分析に役立つ3つの代表的なフレームワークをご紹介します。
- PEST分析
- 3C分析
- 5フォース分析
PEST分析
PEST分析は、Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の4つの視点から、マクロ環境の変化を分析するフレームワークです。
PEST分析の目的と使い方
PEST分析は、自社ではコントロールできない外部要因を定期的に観測し、短期・中期の対応策を明確にするために使います。なぜこの分析が必要かというと、外部環境の変化に早めに気づいて備えることで、競合との差別化につながるからです。
たとえば、「広告のクリック単価(CPC)が前年比18%上昇」という経済的変化に気づいた場合、短期的には広告予算を価値訴求型のコンテンツに再配分し、中期的には価格戦略の見直しを検討するといった対応が考えられます。
PEST分析の記載例
各要素について、具体的な数値と出典を記録しましょう。
- Politics(政治) 個人情報保護法の改正により、Cookieを使った広告ターゲティングが制限される(2024年施行)
- Economy(経済) 広告クリック単価が前年比+18%(Google広告データ、2024年Q3)
- Society(社会) 「低刺激」キーワードの検索ボリュームが前年比+22%(Googleトレンド)
- Technology(技術) AIチャットボットの導入により、カスタマーサポートの自動化が進む
四半期ごとに更新日を記録し、定期的に見直すことで、環境変化への対応が習慣化されます。
「PEST分析」は、政治(Political)・経済(Economic)・社会(Social)・技術(Technological)の4切り口で、外部環境の変化を整理する方法です。市場や規制、生活者の価値観、技術進歩など、事業の外で起きる変化[…]
3C分析
3C分析は、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から、ビジネス環境を整理するフレームワークです。
3C分析の目的と使い方
3C分析の目的は、顧客・競合・自社の現状を同じ粒度で並べて比較し、強みや課題の差分を明確にすることです。
この分析が重要な理由は、比較する項目の粒度が揃っていないと、誤った判断につながるからです。
たとえば、顧客についてはCVR(コンバージョン率)や離脱率、競合については価格帯や導線設計、自社についてはLTV(顧客生涯価値)やCAC(顧客獲得コスト)といった具体的な数値で整理します。
3C分析の記載例
| 視点 | 項目 | 数値・状況 |
|---|---|---|
| Customer(顧客) | カート離脱率 | 68%(Google Analytics) |
| Customer(顧客) | 主な検索キーワード | 「低刺激 化粧品」「敏感肌 コスメ」 |
| Competitor(競合) | A社の価格帯 | 3,000〜5,000円 |
| Competitor(競合) | B社の返品率 | 2.8% |
| Company(自社) | LTV | 24,000円 |
| Company(自社) | CAC | 8,000円(回収期間3ヶ月) |
| Company(自社) | 返品率 | 2.2% |
このように数値で整理すると、「カート離脱率68%が最大のボトルネック」といった優先課題が自然と見えてきます。
3C分析(さんしーぶんせき)とは、マーケティング戦略や事業計画を立案する際に活用される基本的なフレームワークです。Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)という3つの要素(頭文字が「C」で始まる要[…]
5フォース分析
5フォース分析は、業界の競争環境を5つの要因から分析し、収益性や参入障壁を評価するフレームワークです。経営学者マイケル・ポーターが提唱しました。
5フォース分析の目的と使い方
5フォース分析は、業界に働く5つの圧力(新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、既存競合との競争)を可視化し、業界の収益構造を理解するために使います。
この分析が必要な理由は、収益性は自社の努力だけでなく、業界構造にも大きく左右されるからです。たとえば、原材料の供給元が限られている業界では、売り手の交渉力が強く、価格戦略に制約が生じることがわかります。
5フォース分析の記載例
- 新規参入の脅威 初期投資が少なく、参入障壁が低い(脅威:高)
- 代替品の脅威 類似商品が多く、スイッチングコストが低い(脅威:高)
- 買い手の交渉力 価格比較サイトの普及により、顧客の価格感度が高い(交渉力:強)
- 売り手の交渉力 原材料供給元が集中しており、価格交渉が難しい(交渉力:強)
- 既存競合との競争 大手3社がシェアの70%を占め、競争が激しい(競争:激)
圧力が強い要素については、提携・内製化・差別化などの対策を併記しておくと、後の戦略設計がより現実的になります。
【戦略設計】ターゲットと方向性を決めるフレームワーク
環境分析が終わったら、次は「誰に、どのような価値を届けるか」という戦略を設計します。
この章では、ターゲット設定や戦略の方向性を決めるための代表的なフレームワークを解説します。
- STP分析
- ペルソナ設計
- SWOT分析・TOWS分析
- アンゾフマトリクス
- ジョブ理論(JTBD)
STP分析

STP分析は、Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)の3つのステップで、市場戦略を設計するフレームワークです。
STP分析の目的と使い方
STP分析の目的は、市場を細分化し、狙うべき顧客層を明確にし、競合との差別化ポイントを言語化することです。この分析が重要な理由は、すべての顧客に向けた施策では、単価もコンバージョン率も上がりにくいからです。
たとえば、化粧品市場であれば「安全性を重視する30代女性」を第一ターゲットとし、価格重視層は第二ターゲットに設定します。そして、ポジショニングとして「低刺激・専門家監修・テスト済み」という価値を一言で定義します。この価値定義が、以降の価格設定、販売チャネル、広告訴求のすべての基準になります。
STP分析の記載例
| Segmentation(セグメンテーション) |
|
| Targeting(ターゲティング) |
|
| Positioning(ポジショニング) |
|
このように明確に定義することで、チーム全体が同じ方向を向いて施策を進められます。
STP分析とは、マーケティング戦略立案の基本フレームワークです。自社の商品・サービスを「どこの市場で、誰に向けて、どんな立ち位置で提供するか」を整理する手法で、Segmentation(セグメンテーション)・Targeting(ターゲティン[…]
ペルソナ設計
ペルソナとは、ターゲット顧客を具体的な一人の人物像として詳細に描いたものです。
ペルソナ設計の目的と使い方
ペルソナ設計の目的は、ターゲットを「30代女性」といった属性だけでなく、行動・心理・価値観まで含めて具体化することです。なぜ具体化が必要かというと、属性だけでは意思決定の軸が定まらず、施策のブレが生じやすいからです。
ペルソナには、属性・行動・心理・判断基準・購入シナリオをA4一枚にまとめます。データや顧客インタビューの引用元と更新日を必ず記載することで、主観的な思い込みを排除できます。
BtoB企業の場合は、意思決定に関わる複数の役割(部門長、担当者、情報システム部門、法務部門など)ごとにペルソナを分けると、提案資料がより刺さりやすくなります。
【ペルソナ設計の記載例】
| 基本属性 |
|
| 行動・心理 |
|
| 判断基準 |
|
| 購入シナリオ |
※データ出典:顧客インタビュー5件、購買履歴分析(2024年9月) |
ペルソナとは、自社商品・サービスを利用する架空の顧客像を具体的に設定したものです。 マーケティング戦略上の典型的な顧客モデルであり、年齢や職業、価値観など細部まで決めた「理想的なお客様の姿」を指します。ターゲット(想定顧客層)よりも具[…]
SWOT分析・TOWS分析
SWOT分析は、Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4つの視点で現状を整理するフレームワークです。TOWS分析は、SWOTで整理した事実を基に、具体的な戦略を導き出す手法です。
SWOT/TOWS分析の目的と使い方
SWOT分析の目的は、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理し、現状を客観的に把握することです。しかし、多くの企業がSWOT分析で終わってしまい、具体的な戦略につながらないという課題があります。
そこで役立つのがTOWS分析です。TOWS分析では、SWOTで整理した事実を組み合わせて、以下の4つの戦略を導きます。
- SO戦略(強み×機会) 強みを活かして機会を最大化する
- ST戦略(強み×脅威) 強みを活かして脅威を回避・軽減する
- WO戦略(弱み×機会) 弱みを克服して機会を活かす
- WT戦略(弱み×脅威) 弱みと脅威の影響を最小化する
SWOT/TOWS分析の記載例
【SWOT分析】
| 内部環境 | 内容 |
|---|---|
| Strengths(強み) | ブランド指名検索が月間5,000件、リピート率45% |
| Weaknesses(弱み) | 新規顧客獲得単価が高い(8,000円) |
| 外部環境 | 内容 |
|---|---|
| Opportunities(機会) | 敏感肌市場が年率8%成長 |
| Threats(脅威) | 広告クリック単価が前年比+18% |
【TOWS分析】
- SO戦略 ブランド力を活かし、口コミマーケティングで敏感肌市場のシェアを拡大
- ST戦略 ブランド検索への投資を増やし、広告費高騰の影響を軽減
- WO戦略 初回購入ハードルを下げる限定キャンペーンで新規顧客を獲得
- WT戦略 CRM施策を強化し、既存顧客のLTV向上で広告依存を減らす
このように、事実→洞察→戦略という流れで橋渡しができます。
ビジネスの現場で「次にどんな戦略を取るべきか分からない」「チーム内で意見がまとまらない」という悩みを抱えていませんか? SWOT分析は、そんな課題を解決する強力なツールです。強み・弱み(内部要因)と機会・脅威(外部要因)を整理し、事実[…]
アンゾフマトリクス
アンゾフマトリクスは、市場と製品の2軸で成長戦略を4つに分類するフレームワークです。経営学者イゴール・アンゾフが提唱しました。
アンゾフマトリクスの目的と使い方
アンゾフマトリクスの目的は、成長の方向性を「既存市場×既存製品」「新市場×既存製品」「既存市場×新製品」「新市場×新製品」の4つに整理し、リスクと必要なリソースを評価することです。
- 市場浸透戦略(既存市場×既存製品) 既存顧客への販売強化、シェア拡大
- 市場開拓戦略(新市場×既存製品) 新しい顧客層や地域への展開
- 製品開発戦略(既存市場×新製品) 既存顧客向けに新商品を開発
- 多角化戦略(新市場×新製品) まったく新しい市場と製品に挑戦
右下に行くほどリスクが高まるため、検証の負荷も大きくなります。たとえば、既存市場×新製品の戦略を選ぶ場合、既存チャネルや顧客基盤という強みを活かした検証計画を先に作ると、失敗のリスクを抑えられます。
アンゾフの成長マトリクスとは、企業の成長戦略を検討するための古典的なフレームワークです。市場(顧客層)と製品(商品・サービス)という2軸で成長方向性を分析し、「既存」と「新規」の組み合わせから4つの戦略オプションを導き出します。1960年代[…]
アンゾフマトリクスの記載例
| 市場/製品 | 既存製品 | 新製品 |
|---|---|---|
| 既存市場 | 【市場浸透】リピート施策強化、定期購入プランの導入 | 【製品開発】敏感肌向け美容液の新発売 |
| 新市場 | 【市場開拓】男性向けスキンケア市場への参入 | 【多角化】ヘルスケア分野への進出 |
自社のリソースとリスク許容度を考慮して、適切な成長戦略を選びましょう。
ジョブ理論(JTBD)
ジョブ理論(Jobs To Be Done)は、顧客が製品やサービスを「雇う」理由、つまり「達成したい仕事(ジョブ)」に着目するフレームワークです。
ジョブ理論の目的と使い方
ジョブ理論の目的は、顧客が「何のために」その製品を購入するのかを深く理解することです。なぜこの理解が重要かというと、属性や行動データだけでは説明できない、深層的な動機が購買意思決定を左右するからです。
たとえば、顧客がコーヒーを買う理由は「眠気覚まし」だけではありません。「朝のルーティンで心を落ち着かせたい」「仕事の合間にリフレッシュしたい」といった、感情的・社会的なジョブが隠れている可能性があります。
顧客インタビューを通じて、購買の文脈や妨害要因を掘り下げ、その洞察を価値提案に反映させることが重要です。
ジョブ理論の記載例
ジョブの定義
状況(When)
妨害要因
価値提案への反映
このように、ジョブ理論は顧客の深層心理に基づいた施策設計を可能にします。
【施策設計】具体的な打ち手を作るフレームワーク
戦略が決まったら、次は具体的な施策に落とし込む段階です。このセクションでは、製品、価格、流通、プロモーションなど、マーケティングミックスを設計するためのフレームワークを解説します。
- 4P・7P・4C
- UVP(独自の価値提案)・USP(独自の強み)
4P・7P・4C
マーケティングミックスの基本フレームワークが4Pです。さらにサービス業では7P、顧客視点でのチェックには4Cを活用します。
4P・7P・4Cの目的と使い方
4P分析の目的は、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)の4つの要素を整合させ、一貫性のある施策を設計することです。サービス業では、People(人)、Process(プロセス)、Physical Evidence(物的証拠)を加えた7Pで設計します。
4Cは、顧客視点でのチェックリストとして機能します。Customer Value(顧客価値)、Cost(顧客コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)の4つの視点で、顧客体験が一貫しているかを確認します。
なぜこの整合性が重要かというと、価値提案と実際の施策がずれていると、顧客の信頼を失い、コンバージョン率が下がるからです。
4P・7P・4Cの記載例
4P分析

- Product(製品) 敏感肌向け低刺激スキンケアライン、臨床テスト済み
- Price(価格) 初回限定2,980円、通常価格4,500円(常時割引は廃止)
- Place(流通) 自社ECサイト、Amazon、一部ドラッグストア
- Promotion(プロモーション) Instagram広告、インフルエンサーマーケティング、専門家の推薦コンテンツ
「4P分析」は、製品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・販促(Promotion)をそろえて検討するための枠組みです。 この記事では、定義だけでなく、実務で使える手順やテンプレート、ミニ事例、注意点までを一つに[…]
7P分析(サービス業の場合)

- People(人) 皮膚科医監修、専門知識を持つカスタマーサポート
- Process(プロセス) 初回購入から7日以内に使用感フォローメール送信
- Physical Evidence(物的証拠) 臨床試験データ、第三者認証マーク
マーケティング施策を実行しても成果が出ない、サービスの品質にばらつきがある、そんな課題を抱えていませんか。 7P分析は、製品・価格・流通・販促の基本要素に加えて、人・プロセス・物的証拠という3つの要素を組み合わせることで、サービスビジ[…]
4C分析(顧客視点チェック)
- Customer Value 「肌トラブルの不安解消」という価値は明確か
- Cost 初回価格は心理的ハードルを下げているか
- Convenience ECサイトの購入導線はスムーズか
- Communication 専門家の推薦など、信頼を高めるメッセージが届いているか
このように、提供側の視点(4P/7P)と顧客視点(4C)の両方から整合性を確認しましょう。
UVP(独自の価値提案)・USP(独自の強み)
UVP(Unique Value Proposition)とUSP(Unique Selling Proposition)は、自社の価値や強みを一言で言い切るフレームワークです。
UVP/USPの目的と使い方
UVP/USPの目的は、競合との比較軸を自社で定義し、顧客に選ばれる理由を明確にすることです。なぜこれが重要かというと、価値が曖昧だと価格競争に巻き込まれ、利益率が下がるからです。
UVPは「顧客が得られる成果」に焦点を当て、USPは「他社にはない独自の強み」を強調します。たとえば、「低刺激・長持ち」「導入の手間最小・即サポート」といった表現で、顧客が望む成果と根拠をセットで掲げます。
この価値定義を、広告、Webサイト、営業資料など、すべての顧客接点でブレずに使い続けることが重要です。
UVP/USPの記載例
BtoC(化粧品)の場合
- UVP 「敏感肌でも安心して使える、専門家監修の低刺激スキンケア」
- USP 「皮膚科医100名の監修、臨床テスト済み、返金保証付き」
BtoB(SaaS)の場合
- UVP 「専任IT担当者がいなくても、導入初日から使える業務管理ツール」
- USP 「60分以内のサポート対応、初回設定代行込み、7日で価値体験」
値引きではなく価値で語る姿勢が、ブランドの強さにつながります。
【体験設計】顧客の行動
顧客の購買プロセスや利用体験を可視化することで、どこで顧客がつまずいているのか、どの段階で離脱しているのかを特定できます。
この章では、顧客体験を設計し、改善点を明確にするためのフレームワークを解説します。
- カスタマージャーニーマップ
- ファネル分析
- AARRR(海賊指標)
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスと出会ってから購入、利用、継続に至るまでの一連の体験を時系列で可視化するフレームワークです。
カスタマージャーニーマップの目的と使い方
カスタマージャーニーマップの目的は、顧客の行動、思考、感情、タッチポイント、課題を各フェーズで整理し、体験のどこで問題が起きているかを特定することです。なぜこの可視化が必要かというと、企業側の視点だけでは気づかない、顧客の小さなつまずきが離脱の原因になっていることが多いからです。
一般的なジャーニーは、認知→検討→購入→利用→継続の5つのフェーズで構成されます。各フェーズで、顧客の行動・思考と感情・タッチポイント・課題・解決策・KPIを表形式で整理します。
たとえば、「購入直前の不安」が主な離脱要因であれば、FAQ充実、返金保証の明示、口コミの配置といった施策を検討し、ファネル分析の数値と対応づけます。
カスタマージャーニーマップの記載例
| フェーズ | 行動 | 思考・感情 | タッチポイント | 課題 | 解決策 | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知 | Instagram広告を見る | 「肌に優しそう」と興味を持つ | Instagram広告 | 商品の詳細がわからない | LP誘導、価値訴求を強化 | 広告クリック率2.5% |
| 検討 | 公式サイトで詳細確認 | 「本当に効果があるか不安」 | 公式サイト、口コミサイト | 証拠や実績が不足 | 臨床データ・専門家推薦を上段配置 | サイト滞在時間3分以上 |
| 購入 | カートに追加→決済 | 「返品できるか心配」 | ECサイト決済ページ | 返金保証が目立たない | 返金保証バナーを追加 | カート離脱率68%→55% |
| 利用 | 商品使用開始 | 「思ったより良い」 | 商品本体、同梱パンフレット | 使い方がわかりにくい | 使用方法動画をメール送付 | 初回満足度85% |
| 継続 | リピート購入 | 「定期購入したい」 | リピート購入ページ、メルマガ | 定期購入の案内が遅い | 初回購入7日後にフォローメール | リピート率45% |
このように、顧客の感情変化と課題を可視化することで、優先的に改善すべきポイントが明確になります。
ファネル分析
ファネル分析は、顧客が認知から購入、継続に至るまでの各段階での歩留まりを数値で管理するフレームワークです。
ファネル分析の目的と使い方
ファネル分析の目的は、購買プロセスの各段階でどれだけの顧客が次のステップに進んでいるか、どこで最も多く離脱しているかを定量的に把握することです。なぜこの分析が重要かというと、感覚ではなくデータに基づいて改善の優先順位を決められるからです。
典型的なファネルは、以下のような構造になります。
- 認知 広告表示数、サイト訪問数
- 興味・関心 ページ閲覧数、滞在時間
- 比較・検討 商品詳細ページ閲覧、カート追加
- 購入 決済完了
- 継続・紹介 リピート購入、レビュー投稿
各段階の転換率(コンバージョン率)を計測し、最もボトルネックになっている箇所から改善します。たとえば、カート追加から決済完了への転換率が30%と低ければ、決済ページの改善が最優先課題となります。
ファネル分析の記載例
| 段階 | 人数 | 転換率 | 主なKPI | 担当 | 改善施策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広告表示 | 100,000 | – | インプレッション数 | 広告チーム | – |
| サイト訪問 | 5,000 | 5.0% | クリック率 | 広告チーム | 広告クリエイティブ改善 |
| 商品詳細閲覧 | 2,500 | 50% | ページ閲覧率 | Webチーム | LP構成の見直し |
| カート追加 | 800 | 32% | カート追加率 | Webチーム | 購入ボタンの視認性向上 |
| 決済完了 | 240 | 30% | 購入率(CVR) | Webチーム | 返金保証の明示、決済手段追加 |
| リピート購入 | 108 | 45% | リピート率 | CRMチーム | フォローメール、定期購入案内 |
このように、数値で管理することで「どこを直せば最も効果が出るか」が一目瞭然になります。
マーケティングファネルとは何か、どのように活用すれば良いのか悩んでいませんか。 特にBtoB企業でマーケティングに携わる初心者の方に向けて、本記事ではマーケティングファネルの基本から具体的なテンプレート、そして実践的な作り方までを解説[…]
AARRR(海賊指標)
AARRRは、Acquisition(獲得)、Activation(活性化)、Retention(継続)、Referral(紹介)、Revenue(収益)の5つの段階で、プロダクトの成長を管理するフレームワークです。「海賊指標」とも呼ばれます。
AARRRの目的と使い方
AARRRの目的は、特にSaaSやアプリなどのプロダクトビジネスにおいて、顧客のライフサイクル全体を可視化し、成長のボトルネックを特定することです。なぜこのフレームが有効かというと、新規獲得だけでなく、活性化や継続といったプロダクトの本質的な価値提供にも焦点を当てられるからです。
各段階で主要なKPIを1つに絞り、責任者とチャネルを明確にすることで、改善の優先順位が自然と決まります。特にスタートアップや新規事業では、まずActivation(初回価値体験)とRetention(継続利用)を優先し、その後にAcquisition(大規模獲得)に投資するのが定石です。
AARRRの記載例
| 段階 | KPI | 目標値 | 現状値 | 担当 | 改善施策 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition(獲得) | 新規ユーザー登録数 | 1,000/月 | 850/月 | マーケティング | SNS広告強化 |
| Activation(活性化) | 初回価値体験率(7日以内に主要機能利用) | 60% | 45% | プロダクト | オンボーディング改善 |
| Retention(継続) | 30日継続率 | 40% | 32% | プロダクト | リマインドメール配信 |
| Referral(紹介) | 紹介経由の新規登録率 | 15% | 8% | マーケティング | 紹介プログラム導入 |
| Revenue(収益) | 有料転換率 | 10% | 7% | セールス | 無料期間中の価値訴求強化 |
AARRRを使うことで、プロダクト成長の全体像を把握し、どの段階に注力すべきかが明確になります。
【仕組み設計】体制とプロセスを整えるフレームワーク
優れた戦略や施策も、実行する仕組みが整っていなければ成果につながりません。
この章では、業務フロー、役割分担、目標管理など、マーケティング活動を支える仕組みを設計するフレームワークを解説します。
- サービスブループリント
- KPIツリー
- OKR(目標と主要な結果)
- North Star Metric(北極星指標)
サービスブループリント
サービスブループリントは、顧客接点(フロントステージ)と裏側の業務(バックステージ)を一体で可視化し、サービス提供の全体像を設計するフレームワークです。
サービスブループリントの目的と使い方
サービスブループリントの目的は、顧客が体験するサービスの流れと、それを支える裏側の業務プロセスを一枚の図で整理し、役割・SOP(標準業務手順)・SLA(サービスレベル合意)を明確にすることです。なぜこの可視化が必要かというと、顧客体験の継ぎ目や問題は、裏側の部門間の連携不足で起きることが多いからです。
たとえば、美容サロンであれば、「受付→カウンセリング→施術→会計→アフターフォロー」という顧客の流れに対して、「予約システム確認→カルテ準備→施術記録→請求処理→フォローメール送信」という裏側の業務を対応づけます。各ステップで誰が何をいつ実行するか、どの指標で品質を測るかを図示します。
サービスブループリントの記載例
| 顧客行動(フロント) | 顧客接点 | フロントステージ(見える業務) | バックステージ(見えない業務) | サポートプロセス | SLA・KPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 予約 | 予約サイト | 予約受付、確認メール送信 | 予約システムへ登録、空き枠調整 | 予約管理システム | 予約確認メール60分以内送信 |
| 来店・受付 | 受付カウンター | 挨拶、カルテ確認 | 当日予約リストの確認、カルテ準備 | 顧客管理システム | 待ち時間5分以内 |
| カウンセリング | カウンセリングルーム | 悩みヒアリング、提案 | 過去履歴の参照、メニュー提案準備 | カルテシステム | カウンセリング時間10分 |
| 施術 | 施術ルーム | 施術実施 | 使用商材の記録、次回予約案内準備 | 在庫管理システム | 施術時間60分(目安) |
| 会計 | 受付カウンター | 会計、次回予約案内 | 請求処理、ポイント付与 | POSシステム | 会計待ち時間3分以内 |
| アフターフォロー | メール | – | フォローメール送信、満足度アンケート | メール配信システム | 来店翌日にメール送信 |
このように、顧客体験と裏側の業務を一体で設計することで、サービスの一貫性と品質が保たれます。
KPIツリー
KPIツリーは、最上位の目標を因果関係に基づいて分解し、各部門やチームのKPIに落とし込むフレームワークです。
KPIツリーの目的と使い方
KPIツリーの目的は、全社や部門の最終目標(売上、利益など)から、それを達成するために必要な要素を論理的に分解し、各メンバーが何を改善すべきかを明確にすることです。なぜこの分解が重要かというと、個別KPIだけを最適化すると、全体最適が損なわれるリスクがあるからです。
たとえば、「売上」を最上位KPIとした場合、「新規顧客売上」と「既存顧客売上」に分解され、さらに「新規顧客売上=新規顧客数×客単価」「新規顧客数=サイト訪問数×CVR」といった具合に因果関係で分解していきます。
この構造を図示することで、どのKPIがどの目標に影響するのか、どこを改善すれば最も効果が大きいのかが一目でわかります。
KPIツリーの記載例
売上(月間500万円)
├─ 新規顧客売上(300万円)
│ ├─ 新規顧客数(1,000人)
│ │ ├─ サイト訪問数(20,000人) ← 広告チーム担当
│ │ └─ CVR(5%) ← Webチーム担当
│ └─ 客単価(3,000円) ← 商品企画担当
└─ 既存顧客売上(200万円)
├─ リピート顧客数(400人) ← CRMチーム担当
└─ リピート客単価(5,000円) ← 商品企画担当各KPIに担当者を割り当て、定期的にモニタリングすることで、目標達成に向けた進捗管理がしやすくなります。
OKR(目標と主要な結果)
OKRは、Objectives(目標)とKey Results(主要な結果)を設定し、組織やチームの方向性を揃えるフレームワークです。GoogleやIntelなど、多くの企業が採用しています。
OKRの目的と使い方
OKRの目的は、野心的でわかりやすい目標(Objective)と、その達成度を測る具体的な指標(Key Results)を設定し、組織全体のベクトルを揃えることです。なぜOKRが有効かというと、KPIだけでは「何のために」が見えにくく、メンバーのモチベーションが維持しにくいからです。
Objectiveは定性的で、チームを鼓舞する表現にします(例:「業界No.1の顧客満足度を実現する」)。Key Resultsは定量的で、通常3〜5個設定します。四半期ごとに見直し、達成率60〜70%を目指すのが一般的です(100%達成は目標設定が低すぎる可能性があります)。
OKRの記載例
Objective(目標)
Key Results(主要な結果)
- 新規顧客のCVRを3.5%から5.0%に向上させる
- カート離脱率を68%から50%に改善する
- 初回購入後7日以内の満足度調査で星4.5以上を獲得する
- リピート率を45%から55%に向上させる
担当
- KR1:マーケティングチーム
- KR2:Webチーム
- KR3:カスタマーサポートチーム
- KR4:CRMチーム
四半期末に達成状況を振り返り、学びを次のOKRに活かします。
North Star Metric(北極星指標)
North Star Metricは、企業やプロダクトが最も重視すべき「唯一の指標」を定義するフレームワークです。
North Star Metricの目的と使い方
North Star Metricの目的は、顧客価値と事業成長の両方を表す最重要指標を定め、組織全体がその指標の向上に向けて動けるようにすることです。なぜ唯一の指標が必要かというと、複数の指標を追いかけると、優先順位が曖昧になり、部門間で矛盾が生じやすいからです。
North Star Metricの条件は以下の通りです。
- 顧客が得る価値を表している
- 事業の成長と相関している
- シンプルで誰でも理解できる
- 定期的に測定可能である
たとえば、Airbnbは「予約泊数」、Spotifyは「月間アクティブユーザーの総再生時間」、Uberは「月間完了乗車数」をNorth Star Metricとしています。
North Star Metricの記載例
BtoC(ECサイト)の場合
North Star Metric:「月間アクティブ購入者数」
【理由】
- 継続的に購入する顧客は、商品に価値を感じている
- 購入者数の増加は売上成長に直結する
【関連指標】
- 新規購入者数
- リピート購入率
- 平均購入頻度
BtoB(SaaS)の場合
North Star Metric:「週次アクティブユーザー数(WAU)」
【理由】
- 継続的に利用されているということは、プロダクトが価値を提供している証拠
- アクティブユーザーが増えれば、有料転換や契約継続につながる
【関連指標】
- 初回価値体験率(7日以内に主要機能利用)
- 30日継続率
- 有料転換率
North Star Metricを定めることで、組織全体が同じ方向を向いて施策を進められます。
【顧客分析】顧客価値を可視化するフレームワーク
すべての顧客が同じ価値を持っているわけではありません。
どの顧客に投資すべきか、どの顧客グループを育てるべきかを定量的に判断するためのフレームワークを解説します。
- RFM分析
- コホート分析
- LTV・CAC分析
RFM分析
RFM分析は、Recency(最終購入日)、Frequency(購入頻度)、Monetary(購入金額)の3つの指標で顧客をセグメント分けし、優良顧客を特定するフレームワークです。
RFM分析の目的と使い方
RFM分析の目的は、顧客を価値に応じてグループ分けし、それぞれに適した施策を実施することです。なぜこの分析が必要かというと、すべての顧客に同じコストをかけるのは非効率であり、高価値顧客には手厚く、低価値顧客には効率的に対応する方が費用対効果が高いからです。
各指標を5段階でスコアリングし(5が最高)、合計点数や組み合わせで顧客をセグメント化します。たとえば、RFMすべてが5の顧客は「VIP顧客」、RとFは高いがMが低い顧客は「ロイヤルだが単価が低い顧客」と分類できます。
RFM分析の記載例
| セグメント | R(最終購入) | F(頻度) | M(金額) | 特徴 | 施策例 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP顧客 | 5 | 5 | 5 | 最近も頻繁に高額購入 | 限定商品案内、専任担当配置 |
| 優良顧客 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 継続的に購入 | ポイント優遇、新商品先行案内 |
| 有望顧客 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 最近購入したが頻度・金額は低い | クロスセル施策、使い方提案 |
| 休眠予備軍 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 以前は優良だが最近購入がない | 再購入キャンペーン、理由ヒアリング |
| 休眠顧客 | 1 | 1-2 | 1-2 | 長期間購入がない | 低コストのメール配信のみ |
このように顧客を分類することで、マーケティング予算を効率的に配分できます。
マーケティング担当者として売上向上や顧客育成のプレッシャーを感じる中で、「RFM分析」という言葉を耳にしたことはありませんか。RFM分析とは、顧客を「いつ購入したか(Recency)」「どれくらい頻繁に購入したか(Frequency)」「い[…]
コホート分析
コホート分析は、同じ期間に獲得した顧客グループ(コホート)ごとに、その後の行動や継続率を追跡する分析手法です。
コホート分析の目的と使い方
コホート分析の目的は、時期や施策によって顧客の定着パターンがどう変わるかを可視化し、何が継続率向上に効いているのかを特定することです。なぜこの分析が重要かというと、全体の平均値だけを見ていると、施策の真の効果が見えないからです。
たとえば、2024年7月に獲得した顧客と9月に獲得した顧客で、30日継続率や60日継続率を比較します。もし9月の継続率が高ければ、その期間に実施した施策(オンボーディング改善、初回特典の変更など)が効果的だったと判断できます。
コホート分析の記載例
| 獲得月(コホート) | 初月継続率 | 2ヶ月目継続率 | 3ヶ月目継続率 | 主な施策 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 60% | 35% | 22% | 通常オンボーディング |
| 2024年8月 | 58% | 33% | 20% | 通常オンボーディング |
| 2024年9月 | 68% | 45% | 32% | オンボーディング動画追加 |
| 2024年10月 | 70% | 48% | – | 初回特典の変更+動画 |
この表から、オンボーディング動画の追加が継続率向上に効果的だったことがわかります。
LTV・CAC分析
LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とCAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト)は、顧客一人当たりの収益性を評価し、マーケティング投資の妥当性を判断する指標です。
LTV・CAC分析の目的と使い方
LTV・CAC分析の目的は、顧客を獲得するために使った費用と、その顧客から得られる利益を比較し、マーケティング投資の費用対効果を評価することです。なぜこの分析が重要かというと、新規顧客をどれだけ獲得しても、獲得コストが高すぎれば事業は成立しないからです。
健全なビジネスモデルでは、LTV/CAC比率が3以上、CAC回収期間が12ヶ月以内が目安とされています。
LTVの計算式
LTV = 平均購入単価 × 平均購入頻度 × 平均継続期間
CACの計算式
CAC = マーケティング・営業コストの合計 ÷ 新規顧客獲得数
LTV・CAC分析の記載例
現状の数値
- 平均購入単価:4,000円
- 平均購入頻度:年4回
- 平均継続期間:1.5年
- LTV:4,000円 × 4回 × 1.5年 = 24,000円
- 月間マーケティングコスト:240万円
- 月間新規顧客獲得数:300人
- CAC:240万円 ÷ 300人 = 8,000円
- LTV/CAC比率:24,000円 ÷ 8,000円 = 3.0
- CAC回収期間:8,000円 ÷ (4,000円 × 4回 ÷ 12ヶ月) = 6ヶ月
評価
LTV/CAC比率が3.0、回収期間が6ヶ月と健全な水準。ただし、LTVを向上させる余地があるため、リピート施策を強化する。
高RFM層(優良顧客)の共通点を分析し、その特徴を持つ顧客セグメントへの投資を増やすことで、全体のLTVを向上させられます。
【コミュニケーション設計】メディアと配分を最適化するフレームワーク
顧客とのコミュニケーションには、さまざまなメディアやチャネルがあります。
それぞれの役割を理解し、効果的に組み合わせるためのフレームワークを解説します。
- PESO/POEMモデル
- MMM(マーケティングミックスモデリング)
PESO/POEMモデル
PESOモデルは、Paid(有料メディア)、Earned(獲得メディア)、Shared(共有メディア)、Owned(自社メディア)の4つのメディアタイプに分類し、統合的なコミュニケーション戦略を設計するフレームワークです。POEMは、Paidに代わりにPromotion(販促)を含めたバリエーションです。
PESO/POEMの目的と使い方
PESOモデルの目的は、各メディアの特性と役割を理解し、一貫したメッセージを複数のチャネルで展開することです。なぜこの分類が重要かというと、同じメッセージでもメディアごとに強みや到達範囲が異なるため、適切に組み合わせることで相乗効果が生まれるからです。
核となるメッセージは共通にし、メディアごとに表現の濃度や形式を調整します。最終的には、指名検索や直接訪問といった「自社メディアへの流入」を増やすことを目指します。
PESO/POEMの記載例
| メディアタイプ | 具体例 | 役割 | KPI | 施策例 |
|---|---|---|---|---|
| Paid(有料) | Google広告、SNS広告、インフルエンサー広告 | リーチ拡大、新規認知 | インプレッション数、クリック率 | 「低刺激スキンケア」訴求の広告配信 |
| Earned(獲得) | メディア掲載、口コミ、レビュー、PR記事 | 信頼性向上、第三者評価 | 掲載数、言及数 | プレスリリース配信、専門家への商品提供 |
| Shared(共有) | SNS投稿、UGC、顧客レビュー | 拡散、共感形成 | シェア数、エンゲージメント率 | ハッシュタグキャンペーン、顧客体験の共有促進 |
| Owned(自社) | 公式サイト、ブログ、メールマガジン、公式SNS | 詳細情報提供、関係構築 | サイト訪問数、メール開封率 | SEOコンテンツ、メルマガ配信 |
各メディアの役割を明確にし、データを基に配分を定期的に見直すことで、マーケティング効率が向上します。
MMM(マーケティングミックスモデリング)
MMMは、複数のマーケティング施策が売上に与える因果効果を統計的に推定し、最適な予算配分を導き出す分析手法です。
MMMの目的と使い方
MMMの目的は、各マーケティングチャネル(テレビCM、Web広告、SNS、イベントなど)が売上に与える影響を定量的に測定し、投資対効果の高いチャネルに予算を最適配分することです。なぜこの分析が必要かというと、ラストクリック(最後に接触した広告)だけで評価すると、認知段階で貢献したチャネルの効果を見逃してしまうからです。
MMMでは、過去の売上データとマーケティング投資データを統計モデルで分析し、各チャネルの貢献度や飽和点(これ以上投資しても効果が薄い水準)を推定します。大規模な分析には専門ツールやデータサイエンティストが必要ですが、小規模でも月次の配分と成果の関係を可視化すれば、簡易的なMMMとして機能します。
MMMの活用ステップ
- データ収集 過去12ヶ月以上の売上データと、各チャネルへの投資額を週次または月次で集める
- モデル構築 統計ツール(RやPythonなど)を使い、売上を目的変数、各チャネル投資を説明変数とした回帰モデルを構築
- 効果推定 各チャネルの係数から、投資1万円あたりの売上貢献度を算出
- 最適配分の導出 ROIが高いチャネルへの配分を増やし、低いチャネルは削減または改善
- 検証と更新 新しい配分で実施し、結果をモデルに反映して精度を向上
MMM分析の記載例(簡易版)
| チャネル | 月間投資額 | 推定売上貢献 | ROI | 判定 | 次月配分案 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google広告 | 100万円 | 350万円 | 3.5 | 高 | 120万円に増額 |
| SNS広告 | 80万円 | 240万円 | 3.0 | 中 | 80万円維持 |
| インフルエンサー | 50万円 | 100万円 | 2.0 | 低 | 30万円に減額 |
| SEO・コンテンツ | 20万円 | 80万円 | 4.0 | 高 | 40万円に増額 |
| メールマガジン | 10万円 | 60万円 | 6.0 | 非常に高 | 20万円に増額 |
この表から、メールマガジンとSEOのROIが高いことがわかり、これらへの投資を増やす判断ができます。
本格的なMMM導入には計測基盤と運用体制を整える必要がありますが、まずは配分と成果の関係を可視化することから始めましょう。
マーケティングフレームワークの選び方
数多くのフレームワークが存在しますが、すべてを使う必要はありません。
目的、データの有無、組織の成熟度に応じて適切なフレームワークを選ぶことが重要です。
【マーケティングフレームワークの選び方】
- 目的に応じた選び方
- 組織の成熟度に応じた選び方
目的に応じた選び方
フレームワークは、達成したい目的によって選ぶべきものが変わります。以下を参考にしてください。
短期の意思決定が必要な場合
3C分析→SWOT/TOWS分析→4P分析→ファネル分析の順で進めると、現状把握から施策立案までスピーディーに完結します。
長期の戦略策定が必要な場合
PEST分析→5フォース分析→STP分析→アンゾフマトリクスの順で、マクロ環境から成長戦略まで体系的に設計します。
データが乏しい場合
ジョブ理論(JTBD)→ペルソナ設計→カスタマージャーニーから始め、顧客インタビューや定性調査を基に仮説を立てます。
データが豊富にある場合
ファネル分析→コホート分析→LTV・CAC分析→MMMの順で、定量データを基に最適化を進めます。
組織の成熟度に応じた選び方
マーケティング組織の成熟度によっても、適切なフレームワークは異なります。
スタートアップ・立ち上げ期
まずはリーンキャンバスやジョブ理論で仮説を立て、小さく検証を回します。顧客理解を深めるために、ペルソナやカスタマージャーニーを活用します。
成長期
3C分析やSTP分析で市場ポジションを明確にし、4P/7Pで施策を整えます。ファネル分析やAARRRで成長のボトルネックを特定します。
成熟期
RFM分析やコホート分析で顧客セグメントを細分化し、効率的な投資を行います。MMMで媒体配分を最適化し、ROIを最大化します。
フレームワークを組み合わせる際の注意点
複数のフレームワークを組み合わせる場合、以下の点に注意してください。
一貫性を重視する
多くのフレームワークを使うほど良いわけではありません。選んだフレームワークが互いに矛盾せず、一連の流れで機能するかを確認しましょう。
過剰な分析を避ける
分析だけで終わらず、必ず施策・KPI・担当・期限まで落とし込みます。「分析のための分析」にならないよう注意が必要です。
定期的に見直す
市場環境や事業フェーズが変われば、適切なフレームワークも変わります。四半期ごとに「今のフレームワークで十分か」を見直す習慣をつけましょう。
マーケティングフレームワークの使い方・手順
フレームワークを理解しても、実際にどう使うかがわからなければ意味がありません。
ここでは、どのフレームワークにも共通する、実践的な5つのステップを解説します。
【マーケティングフレームワークを使う手順】
- STEP1:目的と評価軸を一文で定義する
- STEP2:事実を収集する(名詞+数値+出典)
- STEP3:フレームワークに当て込み、矛盾を特定する
- STEP4:施策・KPI・担当・期限に落とし込む
- STEP5:小規模テストで検証し、改訂する
STEP1:目的と評価軸を一文で定義する
最初に「何を達成し、何で測るか」を一文で明確にします。ここが曖昧だと、どのフレームワークを使っても結論がブレてしまいます。
なぜこのステップが必要か
目的が明確でないと、分析の途中で「何のためにこれをやっているのか」がわからなくなり、議論が迷走します。また、評価軸が定まっていないと、施策の成否を判断できません。
記載例
「Q3(7〜9月)に新規顧客からの売上を20%増加させる。主要KPIはCVR(コンバージョン率)、補助KPIはCAC(顧客獲得コスト)と回収期間。制約条件は広告費上限300万円、在庫上限1,500個」
このように数値と期限を明記することで、チーム全体が同じゴールを共有でき、意思決定のスピードが上がります。
STEP2:事実を収集する(名詞+数値+出典)
主観や推測を排除し、客観的な事実を「名詞+数値+出典」の形式で集めます。フレームワークに必要な項目に沿って、データを整理しましょう。
なぜこのステップが必要か
主観や「たぶん」「おそらく」といった曖昧な表現で議論すると、意見の対立が生まれやすく、合意形成に時間がかかります。数値と出典があれば、事実ベースで優先順位を決められます。
記載例
- 「低刺激」キーワードの検索ボリューム前年比+22%(Googleトレンド、2024年9月)
- カート離脱率68%(Google Analytics、2024年8月平均)
- 競合A社の価格帯3,000〜5,000円(公式サイト確認、2024年9月)
- 自社の平均待ち時間14分(店舗ログ、2024年8月)
- 顧客満足度調査で「返金保証があると安心」が回答の62%(自社アンケート、n=200、2024年8月)
このように、各項目に数値と出典を明記することで、後から見直す際にも信頼性が保たれます。
STEP3:フレームワークに当て込み、矛盾を特定する
集めた事実を選んだフレームワークに当て込み、価値提案と施策の間に矛盾がないかを確認します。矛盾があれば赤字でマーキングし、修正します。
なぜこのステップが必要か
戦略と施策がバラバラだと、顧客に一貫したメッセージが届かず、信頼を失います。また、リソースが分散し、効果も薄れます。
記載例(矛盾の特定)
- 「低刺激」を価値として訴求 × 症例データや第三者認証が不足(矛盾)
- 「短時間で完了」を訴求 × 実際の平均待ち時間は14分(矛盾)
- 「高品質・専門性」を訴求 × 常時20%オフの割引を実施(矛盾)
修正案
- 症例データを10件以上追加し、専門家の推薦コメントをLP上段に配置
- 業務フローを見直し、平均待ち時間を10分以内に短縮
- 常時割引を廃止し、初回限定価格のみに変更
矛盾を解消することで、顧客体験の一貫性が高まり、コンバージョン率の向上が期待できます。
STEP4:施策・KPI・担当・期限に落とし込む
設計で終わらせず、具体的な施策を「KPI・担当・期限」とセットで表にまとめます。これにより、実行と評価が1対1で結ばれます。
なぜこのステップが必要か
「誰が、いつまでに、何を、どの数値で成功とするか」が明確でないと、施策は実行されず、成果も測定できません。責任の所在を明確にすることで、実行力が高まります。
記載例
| 施策 | 目標KPI | 担当 | 期限 | 予算 |
|---|---|---|---|---|
| LPの価値訴求を強化(症例追加、専門家コメント配置) | CVR 3.5%→5.0% | マーケティングBチーム | 9月30日 | 制作費20万円 |
| 平均待ち時間の短縮(受付フロー改善) | 待ち時間 14分→10分 | CS統括 | 8月31日 | なし |
| 症例・レビュー掲載の強化 | レビュー評価 4.6→4.8 | 広報チーム | 継続(月10件) | なし |
| 返金保証バナーの追加 | カート離脱率 68%→55% | Webチーム | 9月15日 | なし |
このように表形式で整理することで、進捗管理がしやすくなり、定例会議でもスムーズに状況確認ができます。
STEP5:小規模テストで検証し、改訂する
仮説は現場の反応でしか磨けません。影響が大きく、変更が容易な箇所からA/Bテストを設計し、KPIで判定して表に反映します。
なぜこのステップが必要か
どれだけ綿密に設計しても、顧客の実際の反応は予測と異なることがあります。小さく試して学ぶことで、リスクを抑えながら精度を高められます。
記載例(A/Bテストの設計)
テスト1:LPの価値訴求
- パターンA:「低刺激・専門家監修」を強調
- パターンB:「初回限定2,980円」を強調
- 評価指標:CVR
- 実施期間:2週間
- 結果:パターンAのCVRが4.2%、パターンBが3.8%→パターンAを採用
テスト2:返金保証バナーの配置
- パターンA:商品説明の直下に配置
- パターンB:カートボタンの直上に配置
- 評価指標:カート追加率
- 実施期間:2週間
- 結果:パターンBのカート追加率が+8%向上→パターンBを採用
検証結果を定期的に振り返り、四半期ごとに「配分見直し」と「SOP(標準業務手順)更新」を固定枠として会議に組み込むことで、学習が仕組み化されます。
すぐに使える!マーケティングフレームワークテンプレート
ここでは、実務ですぐに使える1ページ版のテンプレートをご紹介します。このテンプレートに沿って情報を整理することで、戦略から施策までを一貫して管理できます。
1ページ版テンプレート
以下のテンプレートをコピーして、自社の状況に合わせて記入してください。
| セクション | 記入内容 |
|---|---|
| 目的・KPI・制約 | Q3新規売上+20%達成。主要KPI:CVR、補助KPI:CAC・回収期間。制約:広告費300万円、在庫1,500個 |
| 選定フレームワーク | PEST・3C・STP・4P・カスタマージャーニー・ファネル・SWOT/TOWS |
| 環境分析の要約 | CPC+18%で価値訴求への再配分が必要。敏感肌市場は年率8%成長。競合は価格訴求が中心 |
| 戦略の要約 | ターゲット:安全性重視の30代敏感肌女性。ポジショニング:低刺激・専門家監修・テスト済み |
| 主要施策 | ①LP価値訴求強化 ②症例掲載10件/月 ③待ち時間短縮 ④返金保証の明示 |
| KPI・担当・期限 | CVR 3.5→5.0%:マーケB:9/30、レビュー4.6→4.8:広報:継続、待ち時間14→10分:CS:8/31 |
| リスク・法規制 | 薬機法表現の制約あり。法務レビュー必須 |
| 次回更新日 | 10月10日 四半期レビューで配分見直し |
テンプレートの使い方のポイント
- 更新日を必ず記録する 情報の鮮度を保つため、各セクションに最終更新日を記載します
- 数値は必ず出典とセットで記載 後から見直す際に、どこから取得したデータかがわかるようにします
- 矛盾点は赤字でマーキング 戦略と施策の不整合がないかを視覚的に確認できるようにします
- 1ページに収める 情報量が多すぎると読まれなくなるため、要点を絞って簡潔にまとめます
マーケティングフレームワーク活用事例
実際にフレームワークを活用して成果を上げた事例を2つご紹介します。
事例1:BtoC・EC(化粧品)
【課題】
【使用したフレームワーク】
【分析と施策】
- PEST分析:広告CPC(クリック単価)が前年比+18%上昇していることを確認
- 3C分析:比較・検討段階でのカート離脱率が68%と高いことを特定
- STP分析:ターゲットを「安全性を重視する30代敏感肌女性」に明確化
- 4P分析:価値を「低刺激・専門家監修・臨床テスト済み」に再定義し、常時割引を廃止
- カスタマージャーニー:比較段階で「本当に効果があるか」「返品できるか」という不安があることを発見
- ファネル分析:LP→商品詳細→カート追加の各段階の離脱率を測定
- 施策実施:症例データと第三者評価をLP上段に配置、返金保証を明示
【結果】
- LP CVR:3.5%→5.0%(+1.5pt)
- CAC(顧客獲得コスト):8,000円→7,000円(-12%)
- 在庫回転率も改善
この事例では、複数のフレームワークを連携させることで、課題の本質を特定し、的確な施策を打つことができました。
事例2:BtoB・SaaS
【課題】
【使用したフレームワーク】
【分析と施策】
- JTBD:顧客インタビューで「導入の手間や負担への不安」が最大の障壁と判明
- ペルソナ設計:「専任IT担当者がいない中堅企業の総務部長」を具体化
- 7P分析:価値を「導入の手間最小・即サポート」に再定義。Process(プロセス)に「初回価値体験を7日以内に提供」というSOPを設定
- サービスブループリント:インサイドセールスのSLAを「初回接触60分以内」に変更。顧客接点ごとに裏側の業務フローを整備
- 資料再構成:提案資料を「導入負担→ROI→競合比較」の順に再構成
【結果】
- 商談化率:22%→36%(+14pt)
- 契約後の定着率(30日継続利用):68%→80%(+12pt)
- カスタマーサポート満足度向上
この事例では、顧客の本質的な課題(ジョブ)を理解し、プロセス全体を顧客視点で再設計することで、商談化率と定着率の両方を改善できました。
よくある失敗パターンと回避策
フレームワークを使っても成果が出ない場合、以下のような失敗パターンに陥っていることがよくあります。
- 失敗パターン1:フレームワークを乱用する
- 失敗パターン2:主観と感覚で埋める
- 失敗パターン3:分析で終わってしまう
- 失敗パターン4:KPIが不一致・多すぎる
- 失敗パターン5:見直しや更新をしていない
失敗パターン1:フレームワークを乱用する
複数のフレームワークを使いすぎて、分析に時間がかかりすぎたり、情報が分散したりするパターンです。
【回避策】
失敗パターン2:主観と感覚で埋める
数値やデータがないまま、「たぶん」「おそらく」といった主観で分析を進めてしまうパターンです。
【回避策】
失敗パターン3:分析で終わってしまう
フレームワークで分析しただけで満足し、具体的な施策に落とし込まないパターンです。
【回避策】
失敗パターン4:KPIが不一致・多すぎる
各部門がバラバラのKPIを追いかけたり、KPIが多すぎて優先順位がわからなくなったりするパターンです。
【回避策】
失敗パターン5:見直しや更新をしていない
一度作ったフレームワークをそのまま放置し、環境変化に対応できないパターンです。
【回避策】
マーケティングフレームワーク実行前のチェックリスト
フレームワークを使った分析や計画を公開・実行する前に、以下のチェックリストで最終確認を行いましょう。
実行前チェックリスト
- 目的・KPI・制約が一文で定義されているか
「何を達成し、何で測り、どんな制約があるか」が明確に記載されているか確認します。 - 選んだフレームワークの選定理由が明記されているか
なぜそのフレームワークを選んだのか、目的との整合性が説明できるか確認します。 - 各フレームワークの要点が1ページに要約されているか
情報量が多すぎると読まれないため、エッセンスを簡潔にまとめているか確認します。 - すべての項目に「名詞+数値+出典」があるか
主観的な表現がないか、すべてのデータに出典が記載されているか確認します。 - 施策・担当・期限・KPIが揃っているか
具体的なアクションプランに落とし込まれ、責任の所在が明確か確認します。 - 価値提案と施策に矛盾がないか
ブランドメッセージと実際の施策が一貫しているか、顧客体験に継ぎ目がないか確認します。 - 検証計画(A/Bテスト)と次回レビュー日が決まっているか
施策の効果をどう測定するか、いつ見直すかが明記されているか確認します。
これらがすべて満たされていれば、資料は「意思決定の装置」として機能し、チーム全体が同じ方向を向いて動けるようになります。
マーケティングフレームワークで成果を出すために
マーケティングフレームワークは、単なる「分析の枠」ではなく、チーム全体の思考と行動を加速させる「装置」のようなものです。
フレームワークは「枠」ではなく、思考と行動の「加速装置」です。目的と評価軸を一文で固め、客観的な事実を集め、適切なフレームワークに当て込み、具体的な施策・担当・期限・KPIに落とし込み、小さく試して学習を回す。この流れを四半期のリズムに組み込めば、判断は速くなり、学びは蓄積され、成果は再現可能になります。
フレームワークを使いこなすことで、あなたのマーケティング活動は必ず次のステージへ進むはずです。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。