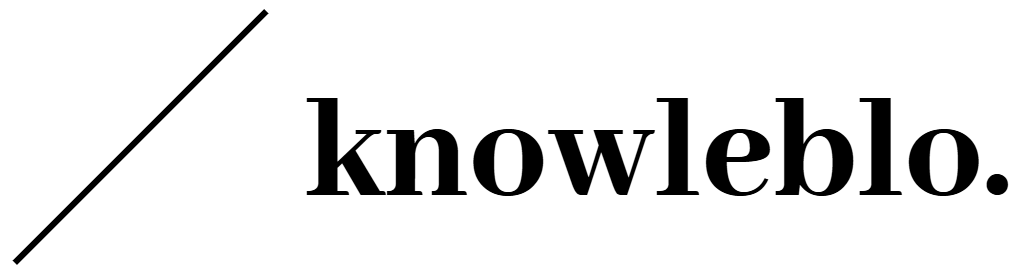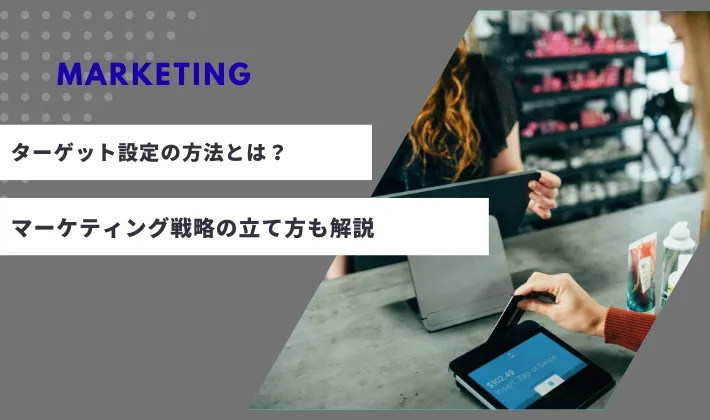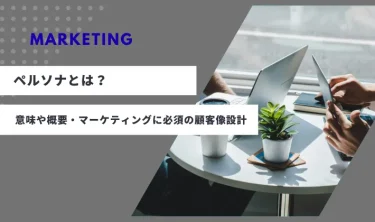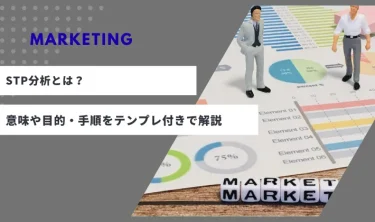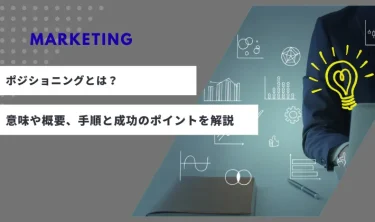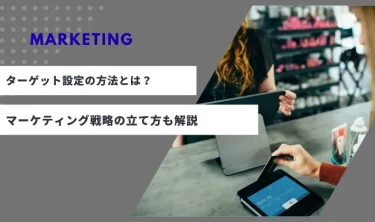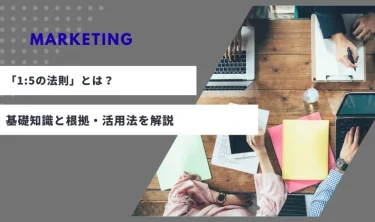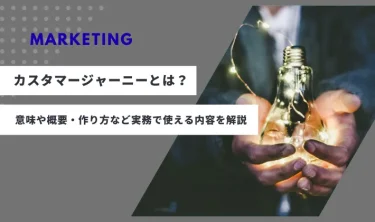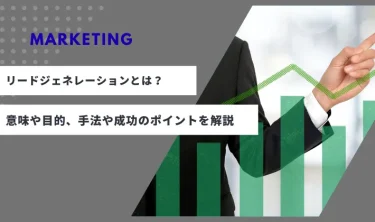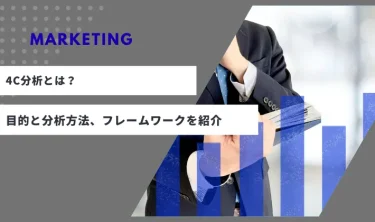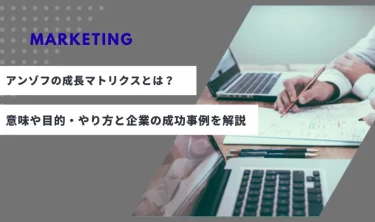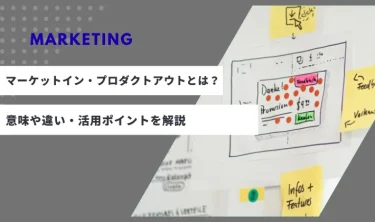マーケティングの現場で「ターゲット設定」という言葉を耳にすることは多いでしょう。しかし、「自社の商品・サービスは誰に向けて提供するのか?」を明確にできずに悩む初心者マーケターも少なくありません。実は、マーケティングにおいて適切なターゲット設定は成果を左右する極めて重要なプロセスです。
例えば明確なターゲティング戦略によって、「接触したユーザーの8割以上が商談に進む」「成約までの期間が3分の1に短縮」「1件あたり受注単価が2.5倍に増加」といった劇的な成果が報告されています。この記事では、企業のマーケティング担当者を対象に、ターゲット設定の基本から具体的な方法・手順、そして成功のポイントをわかりやすく解説します。
誰に向けてマーケティング施策を展開すべきかが明確になれば、限られた予算・時間を無駄にせずに効果的な集客や販促が可能になります。本記事を読むことで、ターゲット設定の意味や重要性を理解し、自社のマーケティング戦略に自信を持って活かせるようになるでしょう。
ターゲット設定とは
「ターゲット」とは、企業が商品・サービスの提供相手として定める特定の顧客層を意味します。そして「ターゲット設定」とは、数ある消費者の中から自社の商品・サービスを購入・利用してもらいたい顧客層を絞り込む作業のことです。言い換えれば、マーケティング資源(予算・人員・時間など)を集中投入する標的市場(ターゲット)の選択を行うプロセスだと定義できます。
ポイントは「絞り込む」という点です。ターゲット設定では、自社の商品を「誰にでも」売ろうとするのではなく、特定の人物像やセグメントにフォーカスします。確かにターゲットを絞れば潜在顧客の数は減少しますが、それでもなおターゲット設定が重要なのはなぜでしょうか?この疑問について、次に詳しく説明します。
ターゲット設定が重要な理由
マーケティングでターゲットを明確に定めることは、現在の市場環境で成功するための前提条件です。その主な理由は以下のとおりです。
消費者ニーズの多様化
現代では消費者それぞれが異なる価値観・ニーズを持ち、「万人向け」の商品は通用しにくくなっています。高度経済成長期のように企業が大量生産・画一的提案をしても、老若男女問わず売れた時代(マスマーケティング)は終わりました。今や「誰にでも響く商品」を狙うと、結果的に誰の心にも響かない可能性が高いのです。
経営資源には限りがあるため
人員・時間・広告予算など企業のリソースは有限であり、闇雲にあらゆる顧客にアプローチする余裕はありません。そこで対象を選択して集中する(選択と集中)ことで、限られたリソースを最も効果的な市場に投入できます。実際、ターゲットを曖昧にして複数の層を同時に狙うと、「二兎を追う者は一兎をも得ず」で予算を浪費し成果を逃しがちです。
競争環境の激化
市場には競合他社がひしめいており、幅広い層を狙った商品・サービスは類似品と比較され埋もれがちです。むしろ特定のニッチ層に的を絞ることで、競合が手薄な市場を開拓し差別化を図れます。適切なターゲット設定により、競合が取りこぼしている顧客層で独自のポジションを築けるのです。
マーケティング施策の起点になる
ターゲット設定はすべてのマーケティング戦略の出発点であり、ここを間違えると後工程も狂ってしまいます。誰に向けたブランドか不明確なままでは、製品開発から広告メッセージまで一貫性がなくなり、結局「誰にも選ばれない」結果につながります。
消費者主導の時代
インターネットの普及した現在、顧客は自分に合う商品を自ら選び取るのが当たり前になりました(=「顧客が企業を選ぶ時代」)。そのため企業側は徹底して「この商品はどんな人のためのものか」を考え抜かなければなりません。提供相手を明確にして初めて、顧客に「自分ごと」と感じてもらえる商品・サービスを提案できるのです。
以上のように、ターゲット設定はマーケティングの土台となる極めて重要なプロセスです。的確なターゲット設定なくして、現代のマーケティング成功は望めないと言っても過言ではありません。
ターゲット設定のメリット
ターゲットを明確に定めてマーケティング施策を展開すると、企業には様々なメリットがもたらされます。その代表的なメリットを見てみましょう。
マーケティング資源の効率的活用(生産性向上&コスト最適化)
ターゲットを絞り込み社内で共有することで、企画・開発・営業・広告など全部署の取り組みが同じ顧客像に向かって統一されます。例えば「若い女性」がターゲットであれば、開発部門は若年女性向けの商品コンセプトを練り、広告部門もそれに合ったトーンのクリエイティブを作る、といった具合に足並みが揃います。結果として無駄な施策の重複やミスマッチが減り、マーケティング全体の効率と生産性が高まります。また、扱う商品ラインナップもターゲットニーズに合うものに絞り込めるため、不要な在庫や冗長な商品の削減によるコストダウン効果も期待できます。例えば何でも揃えるために商品種類を無闇に増やせば在庫管理コストが膨らみますが、ターゲットに合わせて必要な商品だけに絞ればコストを抑えられます。
メッセージの最適化と顧客理解の深化
誰に届けるかが明確になれば、そのターゲット層に刺さる最適なメッセージやプロモーションを設計しやすくなります。ターゲットの関心事や課題に合わせて訴求ポイントを絞り込めるため、画一的なスペック紹介ではなく共感を呼ぶマーケティングが可能になります。さらに特定の顧客層にフォーカスすることで、その層のニーズ・嗜好・行動パターンを深く理解しやすくなるという利点もあります。顧客理解が深まれば、商品開発やサービス改善にも的確に反映でき、結果として顧客満足度の向上につながります。
競合優位性(USP)の確立
明確なターゲティングにより、競合他社が手薄な特定市場で強力なポジションを築くことができます。大手が狙わないニッチなターゲット層に照準を合わせれば、小さな市場でも高いシェアとブランド認知を獲得しやすくなります。このようにターゲット設定は差別化戦略としても機能し、自社ならではの強みを活かして競合に先んじるチャンスをもたらします。
顧客ロイヤリティ向上が期待できる
自分にピッタリの商品・サービスを提供された顧客は、「まるで自分のために作られたみたいだ」と感じて購買意欲が高まります。さらに、自分のニーズを理解してくれる企業に対して愛着や信頼感が生まれ、結果としてロイヤリティ(忠誠心)の向上につながります。ターゲットを絞り、セグメントごとにパーソナライズされた体験を提供することで、顧客との長期的な関係構築が可能になるのです。リピート購入や口コミ紹介など、ロイヤル顧客からもたらされる利益は計り知れません。
このように、ターゲット設定にはマーケティング効果を最大化する多くのメリットがあります。言い換えれば、ターゲットを定めないままではこれらの恩恵を享受できず、効率も効果も上がらないということです。「成功するマーケティング戦略は、常に明確なターゲット設定から始まる」と心得ましょう。
ターゲット設定の方法・手順
マーケティングでターゲットを設定する作業は、一般的に次のステップで進めます。
STEP1: 市場をセグメントに細分化(セグメンテーション)
まずは、市場をいくつかのセグメント(細分化されたグループ)に分けます。セグメントとは、ある基準で分類された一つひとつのグループのことです。商品やサービスの対象となり得る顧客を様々な切り口でグルーピングするイメージです。
例えば、以下のような代表的な基準で市場を分類できます。
- 年齢
- 性別
- 職業(職種)
- 居住地域
- 家族構成
- 年収や予算規模
上記は一例ですが、BtoCビジネスであれば人口統計的属性(デモグラフィック:年齢・性別・職業・収入など)や地理的属性(地域・気候など)、心理的属性(ライフスタイル・価値観など)、行動属性(購買頻度・利用状況など)がよく使われる切り口です。
BtoBビジネスの場合は、業種・業界、企業規模、職種、役職などでセグメント化するとよいでしょう。例えば年齢でセグメントする場合、消費者を「10代以下」「20代」「30代」「40代以上」など年代別のグループに分けることができます。こうして「20代の若年層」「30代の働き盛り層」「40代以上の富裕層」といった具合に属性ごとの特徴が異なる集団が出来上がります。
マーケティング戦略で成果を求められる企業の担当者に向けて、マーケティングセグメンテーションの基本から具体的なやり方までを解説する記事です。市場を細分化して顧客をいくつかのセグメント(顧客グループ)に分け、それぞれに最適な戦略を立てることで、[…]
STEP2: セグメントごとの特徴を分析する
市場をいくつかのセグメントに区切ったら、各セグメントの特徴や傾向をリサーチして明らかにします。それぞれのグループの顧客が「どんなニーズや嗜好を持つか」「どんな行動パターンか」などを調べる段階です。例えば、ある地域の年代別セグメントを分析したところ、「20代は趣味やレジャーに積極的」「30代は仕事や家庭で忙しく実用性を重視」「40代は経済的に安定し品質志向」といった特徴が見えてくるかもしれません。このように各セグメントのデータを集めて比較することで、グループごとの違いが浮き彫りになります。
セグメント分析にあたっては、既存顧客へのアンケートやインタビュー、市場調査レポートの活用、社内データの分析など様々な方法があります。重要なのは先入観に頼らずデータに基づいて把握することです。顧客像に関する仮説がある場合も、できる限りリサーチで検証して根拠を得るようにしましょう。このプロセスを踏むことで、次のステップで最も有望なターゲット層を選ぶ判断材料が揃います。
STEP3: 最適なターゲットセグメントを選定する(ターゲティング)
各セグメントの特徴がわかったら、自社の商品・サービスに最もマッチするセグメントを選び出します。これが「ターゲットを決める」という段階です。選び方には2つのアプローチがあります。
プロダクト志向のアプローチ(プロダクトイン)
自社の商品・サービスの特徴や強みを考えたとき、それを最も必要としてくれそうなセグメントはどれか?という観点で選びます。例えば「高機能で価格が高めの商品」であれば富裕層やプロ志向の層、「低価格で手軽なサービス」であれば若年層や学生などが候補になるでしょう。
マーケット志向のアプローチ(マーケットイン)
既存の優良顧客が属するセグメントや、市場全体で見て伸びているセグメントなど、データから有望な層を見つけ出す観点で選びます。例えば自社の顧客データを分析して「30代女性の利用が多い」ことが分かればその層に焦点を当てる、外部データで「シニア市場が拡大している」ならば高齢者層を狙う、といった方法です。
いずれにせよ、自社にとって「この層なら勝負できる」という明確な根拠を持ってターゲットセグメントを定めることが重要です。ここで決めたターゲットこそが、今後のマーケティング戦略全般で優先的に狙っていく顧客層となります。
ターゲット設定が戦略に与える影響の例
例えば、あるスーパーマーケットがターゲット設定を行う場合を考えてみましょう。
もしそのスーパーが自店のターゲットを「とにかく安さを追求する顧客」に設定すれば、毎日その時点で一番安く野菜を出荷している産地から仕入れるなど、とにかく価格最優先の品揃え・仕入戦略を取るでしょう。一方でターゲットを「食の安全志向が高い顧客」に設定すれば、農薬不使用・有機栽培にこだわる生産者と契約し、高くても安全品質な野菜を仕入れて販売するといった戦略に変わります。
このようにターゲット層の違いによって、商品ラインナップや仕入先、価格設定やプロモーション方法まで大きく変わってくるのです。ターゲット設定は単なるマーケティング施策の一部ではなく、事業戦略全体の方向性を決定づける重要な意思決定だと言えるでしょう。
STEP4: ターゲットのペルソナ(人物像)を設定する
選び出したターゲットセグメントをさらに具体的に理解するために、ペルソナ(Persona)を設定します。ペルソナとは、そのターゲットを代表する架空の人物像で、年齢・性別・職業・性格・趣味嗜好・課題などを細部まで設定した理想的顧客モデルのことです。ターゲットセグメントが「○○な傾向のある30代女性」といった大まかな層のイメージであるのに対し、ペルソナは実在しそうな「たった一人の具体的なお客さん」として描き出します。
ペルソナ設定の目的は、チーム全員が共通の顧客像を思い浮かべられるようにすることです。詳細な人物像が思い浮かべば、「この人にならどんな言葉で伝える?」「この人はどこで情報収集している?」といった具体的な問いに答えやすくなり、施策の検討が顧客視点で進めやすくなります。例えばペルソナの趣味・ライフスタイルまで想定すれば、「このペルソナは通勤中にスマホで情報収集するタイプだからSNS広告が有効だ」「夜に子供が寝静まった後に悩みを感じるはずだから、その時間帯にメールマガジンを送ろう」といった効果的な媒体選定や施策のタイミングも見えてきます。
30歳・男性、東京在住の営業職。妻子がおり賃貸アパート暮らし。趣味は釣りとドライブ。最近抜け毛に悩んでおり、自分に合った薄毛対策を模索中…
上記のようにペルソナを作り込むことで、「その人」に響くメッセージや提供価値が明確になっていきます。ただし注意点として、ペルソナはあくまで市場調査や顧客データに基づいて設定する必要があります。社内都合で理想化された架空人物を作ってしまうと現実の顧客とかけ離れてしまうため、「自社にとって都合の良い人物像にしない」ことが重要です。
ペルソナは定期的に見直し、必要に応じてアップデートすることで、常に現実の顧客ニーズを反映した有用な指針となります。
ペルソナとは、自社商品・サービスを利用する架空の顧客像を具体的に設定したものです。 マーケティング戦略上の典型的な顧客モデルであり、年齢や職業、価値観など細部まで決めた「理想的なお客様の姿」を指します。ターゲット(想定顧客層)よりも具[…]
STEP5: ポジショニングで自社の立ち位置を明確にする
最後に、ターゲットに対して自社の商品・サービスをどのように位置づけるか(ポジショニング)を検討します。ポジショニングとは、選定したターゲットの目に映るブランドの独自の役割や価値を築く活動です。具体的には、競合製品と比較して「自社はここが優れている」「○○においては負けない強みがある」といった差別化要因を明確に打ち出します。
市場には常に競合他社が存在するため、ターゲットに選ばれるためには自社ならではの魅力を示さなければなりません。例えば価格面で競争するのか、品質やアフターサービスで勝負するのか、あるいはブランドの世界観や顧客体験価値で差別化するのか──戦略は様々ですが、ターゲット顧客に響く軸で他社との差を打ち出すことが肝心です。
ポジショニングまで明確にすることで、「誰に売るか」「何を売るか(提供価値)」「なぜ選ばれるか」が一本の筋で繋がります。これにより、商品コンセプトから広告メッセージ、販売チャネル戦略に至るまでブレのない一貫したマーケティング戦略を構築することが可能となります。
STP分析とは、マーケティング戦略立案の基本フレームワークです。自社の商品・サービスを「どこの市場で、誰に向けて、どんな立ち位置で提供するか」を整理する手法で、Segmentation(セグメンテーション)・Targeting(ターゲティン[…]
マーケティング担当者なら一度は耳にする「ポジショニング」という言葉。しかし、実際に「マーケティングにおけるポジショニングとは何か」と問われると、具体的に説明できない方も多いのではないでしょうか。
ポジショニングは、自社の商品やサービス[…]
ターゲット選定の評価基準・ポイント
ターゲットとするセグメントを決める際には、いくつかの視点でそのセグメントの魅力度や適性を評価すると効果的です。
以下に、マーケティング戦略立案時によく使われる主要な評価基準をまとめます。
| 評価基準 | 説明 |
|---|---|
| 市場規模(Scale) | ターゲットとなる市場規模が十分に大きいかどうか。ニッチすぎる層では売上規模が限られ、投資に見合う利益を継続的に得られない可能性があります。事業コストを上回る収益を上げられる規模かを見極めましょう。 |
| 市場成長性 | 現時点で市場規模が小さくても、将来的な成長余地が大きいかを検討します。今後拡大が見込まれるターゲット層であれば、将来的に有望な市場となり得ます。例えば高齢化や技術トレンドなどで新たに拡大しているセグメントは注目です。 |
| 競合状況(Rival) | そのセグメント内に競合ブランドがどれくらいいるか、競合の強さはどうかを評価します。他社がひしめく激戦区よりも、競合が少なく強力なリーダーが存在しない隙間市場の方が攻略しやすいでしょう。競争優位を築ける余地のあるターゲットかを見定めます。 |
| 波及効果(Ripple) | 選んだターゲット層が周辺の市場へ与える影響力にも注目します。特定層に浸透したブランドが、口コミやトレンドによって他の層にも波及するケースがあります。例えば発信力の強いインフルエンサー的な層を攻略すれば、関連する多数の層に波及効果が期待できます。 |
| 到達可能性(Reach) | そのターゲット層に効果的にリーチできるか(アクセス可能か)を確認します。いくら魅力的な市場でも、該当層に広告や営業でアプローチできなければ成果は見込めません。該当層が利用するメディアや流通チャネルに自社が適切にアクセスできるかを検討しましょう。 |
| 測定可能性(Response) | ターゲット層へのマーケティング施策の効果を測定・検証できるかも重要です。反応を計測できない場合、PDCAを回せず改善が困難になります。例えばWeb施策であればアクセス解析やCVR計測が可能か、オフラインでもアンケートや購買データで効果検証できるかを考えます。 |
上記の視点は、自社にとって「どのターゲットが最も有望か?」を客観的に判断する助けになります。例えば、新規参入なら競合が少ないニッチを狙う、将来性重視なら成長市場に賭ける、既存チャネルを活かすなら到達しやすい層に絞る、といった選択が可能です。ターゲット選定時にはこれらの基準で候補を比較し、最も成功確率が高いターゲットを見極めましょう。
なお、ターゲット設定後も市場環境は変化します。定期的にこれらの指標を見直し、必要に応じてターゲット戦略を修正・更新する柔軟性も持つと良いでしょう。
ターゲット設定で陥りがちな間違い(注意点)
ターゲット設定は「絞り込む」作業だけに、一歩判断を誤るとマーケティング上の大きな失敗につながりかねません。最後に、マーケターが陥りがちなターゲット設定の間違いとその対策を押さえておきましょう。
ターゲットの範囲が広すぎる(「オールターゲット」の罠)
自社のターゲットを「老若男女すべて」「全国民」のように実質絞り込んでいないケースです。一見ターゲット設定をしているように見えて最も危険なパターンで、社内でも部門ごとに想定顧客像がバラバラになりやすく、施策も散発的・不統一になります。さらにメッセージも焦点が定まらず、誰にでも当てはまるような薄い内容になりがちで、結局「何も心に残らない広告」で終わってしまいます。
対策
属性が限定的すぎるターゲット設定(性別・年齢だけで決めてしまう)
よくあるのが「ターゲットは20~30代前半の女性」のように、性別と年齢層だけで漠然と定義しているケースです。一見絞り込んでいるようですが、同じ年代・性別でもライフスタイルや価値観は人によって大きく異なります。例えば「20代後半女性」の中には、独身OLもいれば小さな子どもを持つ主婦、共働きで子育て中の母親など様々な生活ステージの人が混在します。単に年齢・性別だけでひと括りにすると、結局ターゲット像が曖昧になり「オールターゲット」と同様の弊害(部門ごとに勝手に解釈がズレる、メッセージが平凡になる等)を招きます。
対策
データや根拠なしにターゲットを決めてしまう
社内の思い込みや上層部の勘だけで「我が社のターゲットは○○だろう」と決めてしまうのも危険です。リサーチに裏付けられていないターゲット設定では、製品・サービスがヒットするかどうかは運任せになってしまいます。もし想定が外れていれば、狙った層からも外した層からも選ばれず惨敗するリスクがあります。
対策
ターゲット設定の検証・改善を行わない
設定したターゲットが妥当だったかを検証せず放置するのも避けるべき誤りです。ターゲット設定は一種の仮説立てでもあります。実際に施策を展開した結果、売上や反応データを分析して「狙い通りだったか」「想定外のズレがないか」をチェックしましょう。仮説通り成果が出た場合でも、「なぜ成功したのか」「仮説の根拠は正しかったのか」を検証することで、次の戦略立案に活かせます。
対策
設定したターゲットに固執して更新しない
一度ターゲット設定がうまくいったからといって、長期間同じターゲット像に固執することにも注意が必要です。顧客ニーズや市場環境は時間とともに変化します。かつてのメイン顧客層が歳を取り購買行動が変わることもありますし、新たなテクノロジーやライフスタイルの変化で重要ターゲットが移り変わることもあります。
対策
以上のポイントに留意しながらターゲット設定を行えば、大きく的を外すリスクは格段に減らせるはずです。「この商品・サービスは○○という人のためのものだ」と胸を張って言えるくらいまで、ターゲット像を具体化・明確化することが成功への近道です。
まとめ
ターゲット設定とは、数多くいる消費者の中から自社の商品・サービスを訴求すべき相手を選び抜くマーケティング戦略上の重要なプロセスです。万人受けを狙うのではなく、絞ったターゲットに経営資源を集中することで、効率的かつ効果的なマーケティング施策を実現できます。適切なターゲット設定により、社内の方向性が統一され生産性が上がるだけでなく、ターゲット顧客からの強い支持とロイヤリティを得られます。逆にターゲットが不明確なままだと、メッセージも戦略もブレてしまい、せっかくの施策が空回りに終わる可能性が高まります。
現代の多様化した市場では、「誰に向けてビジネスをするのか」を明確にすることがこれまで以上に重要になっています。本記事で紹介した手順やフレームワークを活用し、自社にとって最適なターゲットを設定してください。根拠あるターゲット戦略を構築し定期的に検証・改善を行っていけば、限られたリソースでも高いROI(投資対効果)を実現するマーケティング施策が展開できるでしょう。
ターゲット設定を制する者がマーケティングを制します。正しいターゲット設定で、貴社のマーケティング活動をさらに成功へと導いていきましょう。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。