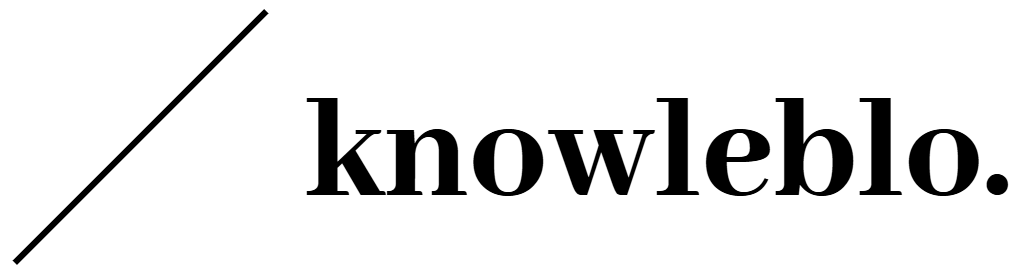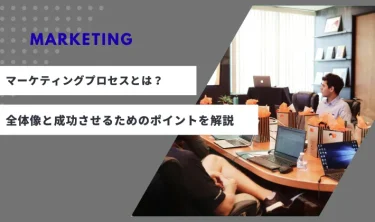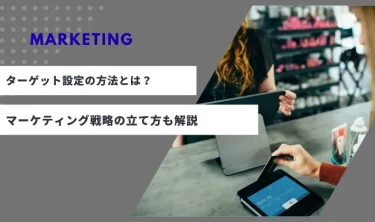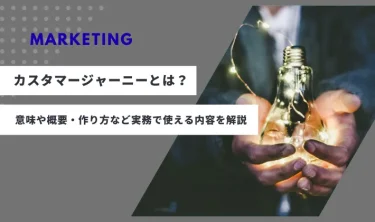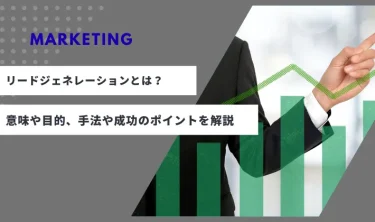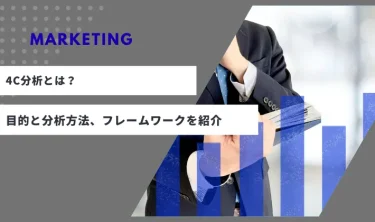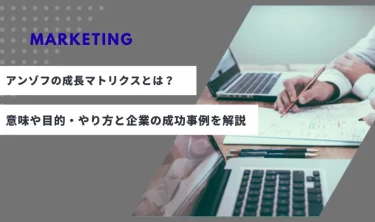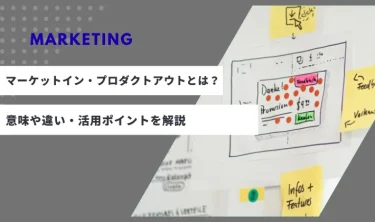マーケティング活動で頻繁に耳にする「タッチポイント」という言葉をご存知でしょうか。企業と顧客の接点を意味するこの概念は、売上向上や顧客満足度の向上において重要な役割を果たします。しかし、「言葉は聞いたことがあるが具体的に何を指し、どのように活用すれば良いのか分からない」という方も多いでしょう。本記事では、企業のマーケティング担当者(初心者の方を含む)を対象に、マーケティングにおけるタッチポイントの基本から実践的な活用方法までを解説します。記事を読むことで、タッチポイントの意味や重要性、BtoBとBtoCそれぞれでの特徴、さらに効果的な戦略の立て方を理解し、自社のマーケティング施策に活かせるようになるでしょう。
マーケティングにおけるタッチポイントとは?
タッチポイント(顧客接点)とは、企業と顧客との間で接触が生まれるあらゆる機会を指します。
例えば、Web広告を見て商品を知ることや、店舗でスタッフの接客を受けること、メールマガジン(ニュースレター)を受け取ることなど、顧客が企業やその商品・サービスに触れる瞬間はすべてタッチポイントです。さらに、購入後に問い合わせ窓口に連絡する、使い方についてサポート情報を調べる、といった購入後のやり取りもタッチポイントに含まれます。タッチポイントはオンライン(インターネット上の接点)とオフライン(直接対面などインターネットを介さない接点)の両方に存在し、現代ではデジタル化によりオンラインのタッチポイントが急増しています。
また、商品やサービスの種類によって、発生するタッチポイントの数や内容も異なります。日用品や低価格の商品であれば「店頭で見てそのまま購入」というように事前の接点は少なく済みますが、高額な自動車や住宅などではいくつかの選択肢を比較検討するため、購入前のタッチポイントが増える傾向にあります。同様に、BtoB(企業間取引)の商材では取引金額が大きく検討期間も長くなることが多いため、一般的にタッチポイントの数も多くなります。
ここで混同しやすいのが「チャネル」という用語です。チャネルとは、企業と顧客が接点を持つための手段や媒体を指します。つまりタッチポイントを生み出すための経路がチャネルです。先述の例で言えば、テレビCMやWeb広告、チラシ、SNSといったものはBtoC(企業が一般消費者と取引するビジネス)における代表的なチャネルであり、企業Webサイトやブログ(オウンドメディア)、営業担当者による訪問などはBtoB(企業間取引)における主要なチャネルです。一方でタッチポイントは、そうしたチャネルを通じて実際に生じる個々の接触の瞬間そのものを指します。例えば「メール」というチャネルを用いて顧客に情報提供する場合、顧客が実際にメールを開封して内容を読む行為がタッチポイントとなります。チャネルはあくまで手段であり、タッチポイントが顧客体験の実体験と言えます。
では、なぜ現代のマーケティングにおいてタッチポイントがこれほど重要視されているのでしょうか。次にその背景と重要性を見ていきましょう。
マーケティングタッチポイントが重要な理由
現代の顧客はオンライン・オフラインを行き来しながら、実に多様なタッチポイントを経験します。
例えば、「YouTubeの動画広告で商品を知り、店頭で実物を確認し、ECサイトで購入、その後にカスタマーサポートに問い合わせ、さらにオフラインのユーザーイベントに参加する」といったように、購買前から購入後まで様々なチャネルを横断して企業と接点を持つケースも珍しくありません。デジタル化が進む以前であれば、テレビCMや店舗接客といった限られた接点だけでも顧客の関心を得ることができました。しかし現在では、企業から一方的に情報提供する従来型のマーケティング手法は成り立ちにくくなり、競争の焦点も製品そのものの優位性から顧客が得られる体験の質へと移っています。
また、SNSの普及により顧客同士の情報共有が活発になり、購入の決め手として企業発信の情報よりも口コミやレビューといった顧客の声が重視される傾向が強まっています。顧客自身もインターネット検索などで必要な情報を容易に得られるようになったため、企業がコントロールできない領域でブランドイメージが左右される場面も増えています。このような状況では、企業が顧客と直接コミュニケーションをとれる貴重な機会であるタッチポイントを最大限に活用し、ポジティブな体験を提供していくことが一層重要になります。実際、良い体験はSNS上で好意的な口コミとなってブランドを後押ししますし、逆に不満の残る体験は悪い評判となって企業イメージを低下させるリスクがあります。
一つひとつのタッチポイントの質が、顧客のロイヤルティやブランド評価を左右すると言っても過言ではありません。
タッチポイント戦略が適切に設計されていない場合、顧客体験がバラバラになって見込み顧客を取り逃がしたり、部署ごとに異なる発信内容でブランドメッセージに一貫性がなくなったりするリスクがあります。反対に、顧客行動を踏まえて接点を整理・強化し、あらゆるタッチポイントで一貫した体験を提供できれば、さまざまなメリットが得られます。それにより競争力強化やブランド価値向上にも直結します。
具体的な効果として、以下のような点が挙げられます。
| 競争力の強化 |
|
|---|---|
| ブランド認知度・イメージの向上 |
|
| 顧客リピート率の増加とLTV(顧客生涯価値)の向上 |
|
このように、タッチポイントを戦略的に設計・最適化することは単なるマーケティング施策にとどまらず、企業全体の成長を支える重要な基盤となります。ただし、むやみに接点を増やせば良いというものではありません。顧客の購買プロセスに沿って必要なタッチポイントを整理し、優先順位をつけて改善することが不可欠です。
次章では、効果的なタッチポイント戦略を立てるための方法を具体的に見ていきましょう。
タッチポイントの種類と具体例
タッチポイントは、その発生する場面や経路によってさまざまな種類があります。大きくはオンライン上の接点とオフラインでの接点に分けられ、さらに顧客の購買プロセス(購入前・購入時・購入後)の段階ごとに整理することができます。
代表的なタッチポイントの例をオンライン/オフライン×購買段階別に示すと以下のようになります。
| 顧客フェーズ | オンラインの主なタッチポイント例 | オフラインの主なタッチポイント例 |
|---|---|---|
| 認知・興味(購入前) |
|
|
| 検討・比較(購入時) |
|
|
| 購入・契約 |
|
|
| 購入後(フォロー) |
|
|
上表のように、認知段階から購買、さらには購入後のフォローに至るまで、顧客は様々な経路で企業と接点を持ち得ます。自社の商品・サービスにおいては、これら各段階におけるタッチポイントを洗い出し、抜け漏れがないか確認することが重要です。
次に、BtoBとBtoCそれぞれのマーケティングでタッチポイントにどのような特徴や違いがあるかを見てみましょう。
BtoBマーケティングにおけるタッチポイントの特徴
BtoB(企業間取引)のマーケティングでは、タッチポイントの性質や設計にBtoCとは異なる注意が必要です。BtoB商材は取引額が大きく検討期間も長期にわたることが多いため、購買に関わる決裁者(意思決定者)も複数存在します。一方、各タッチポイントは主に「情報提供」や「信頼関係の構築」という役割を担い、最終的な契約に至るまで段階的かつ長期的に顧客に働きかける必要があります。感情や衝動に訴える施策よりも、論理的なメリットや実績データを示す理性的な訴求が重視される点もBtoCとの大きな違いです。
BtoBの顧客は、まずオンライン上で製品やサービスの情報収集を行い、さらに詳細な資料やセミナーで知見を深め、最終的に営業担当者との直接的な商談を経て購買判断する、というように多段階のプロセスを踏む傾向があります。そのため、各段階で適切なタッチポイントを用意し、一貫した情報提供を行うことが重要です。主なBtoBタッチポイントの例として、以下のようなものがあります。
| オウンドメディアによる情報提供 |
|
|---|---|
| コンテンツ活用 |
|
| リード獲得イベント |
|
| 直接コミュニケーション |
|
| 導入後のフォロー |
|
上記のように、BtoBマーケティングではオンライン・オフラインの様々なチャネルを駆使してリード(見込み顧客)を育成し、信頼を醸成していくことが求められます。
特に、展示会やホワイトペーパー、営業訪問など企業側が直接コントロールできるタッチポイントを戦略的に組み合わせ、最終的な意思決定を後押しすることが重要です。
BtoCマーケティングにおけるタッチポイントの特徴
BtoC(企業と消費者間の取引)のマーケティングでは、一般消費者が対象となるため、タッチポイントのあり方もBtoBとは異なります。消費者の購買行動は比較的短期間で完結し、意思決定も個人の裁量で行われるケースが多いのが特徴です。
また、テレビやSNSなど日常生活に密着したチャネルで接触する機会が多く、購買の動機にも感情的な要素やプロモーション(セールやクーポンなど)の影響が大きく作用します。そのため、各タッチポイントで消費者の興味を引き、一貫したポジティブな体験を提供することが特に重要となります。一度でも不満や違和感を与えてしまうと、すぐに競合他社へ離れてしまう可能性があるためです。
BtoCでは、認知から購入に至るまで非常に多様なタッチポイントが存在します。企業側はあらゆる接点でブランドの世界観やメッセージを統一し、スムーズに購買へ結び付ける工夫が求められます。
主なBtoCタッチポイントの例として、以下のようなものが挙げられます。
| マスマーケティング |
|
|---|---|
| デジタル広告・コンテンツ |
|
| ソーシャルメディア |
|
| 店頭での体験 |
|
| 購入後のフォロー |
|
このようにBtoCマーケティングでは、企業は多数のチャネルを横断して生活者と接点を持つことになります。その際、どのチャネルでも顧客がストレスなく商品を購入できるように、サービス内容や提供体験の品質を統一する(オムニチャネル戦略)ことが欠かせません。
例えば、オンラインストアで見た商品情報と店舗での説明が食い違わないようにしたり、どの接点でも共通のブランドメッセージが伝わるように工夫することで、顧客に安心感を与え購買につなげることができます。
タッチポイント戦略の立て方
タッチポイントを戦略的に強化するには、現状の分析から施策の実行・改善まで計画的に取り組むことが大切です。ここでは、効果的なタッチポイント戦略を立案・実行するための基本的な手順を5つのステップに分けて説明します。
STEP1 現状のタッチポイントを整理する
最初に、自社が現在保有しているタッチポイントを洗い出します。顧客が認知から購入、購入後に至るまでの各フェーズで、どのような接点が存在するかを一覧にしましょう。単にチャネル名を列挙するだけでなく、各接点が果たす役割(例:認知段階なら「ブランドを知ってもらう」、購入段階なら「スムーズに購入手続きを完了させる」など)を明確にし、それぞれの有効性も併せて確認します。
例えば、購入フェーズへの導線が途中で途切れていないか、購入後のフォローアップ体制が整っているか、といった点を点検します。こうした棚卸しによって、現状で不足しているタッチポイントや改善が必要な箇所が浮き彫りになります。
STEP2 カスタマージャーニーマップを作成する
続いて、整理した接点をもとにカスタマージャーニーマップを作成します。カスタマージャーニーマップとは、顧客が認知から購入、さらに購入後の推奨(口コミ)に至るまでの行動や感情の流れを時系列に可視化したものです。各タッチポイントがどの順序で繋がり、顧客にどのような影響(感情の変化や疑問点など)を与えるかを地図状に描き出すことで、体験全体を俯瞰できます。作成にあたっては、「顧客はその時点で何を感じているか」「どこで不満や課題が生じやすいか」「各段階で顧客が期待する体験は何か」を考慮することが重要です。必要に応じて顧客データやアンケート結果も活用し、顧客像(ペルソナ)の属性ごとに異なる接点の好みや行動パターンも反映させます。完成したカスタマージャーニーマップは定期的に更新し、常に最新の顧客行動や市場環境の変化を反映させましょう。
STEP3 各段階のKPIを設定する
ジャーニーの各段階ごとに達成すべき指標(KPI)を設定します。こうしたKPIは最終的なビジネス目標(KGI)と紐付け、各フェーズで何をどこまで達成すればゴールに近づけるかを明確にするものです。例えば、認知段階では広告の到達人数(リーチ数)やSNSフォロワー数、興味・関心段階ではサイト訪問数や資料ダウンロード数、比較・検討段階ではレビュー閲覧数やカート投入率、購入段階ではコンバージョン率(成約率)や平均購入単価が設定されます。また、購入後のリテンション(継続利用)段階では会員継続率や解約率、アドボカシー(推奨)段階ではレビュー投稿件数や紹介プログラム利用数といった指標が考えられます。
これらKPIをモニタリングすることで、各タッチポイント施策が目標通り機能しているかを評価できます。なお、特定のフェーズだけを最適化しても全体としての成果向上に繋がらない場合もあるため、可能であればチャネル横断のデータを統合し、顧客の最初の接点から最終的な購入・継続利用に至るまで一貫して追跡・分析できる環境を整えることが望ましいでしょう。
STEP4 効果的なチャネルを選定し実行する
次に、設定したKPIを達成するために各フェーズでどのチャネルをどのように活用するかを具体的に計画し、施策を実行します。その際、ステップ1で定義した「接点ごとの役割」を前提に設計することが重要です。役割を踏まえた配置にすることで、各チャネルがカスタマージャーニー全体の中で適切に機能しやすくなり、結果としてKPI達成に繋がります。例えば、認知段階ではSNS広告で興味を喚起し自社サイトへ誘導する、比較段階ではメールでクーポンを配布して購買を後押しするといったように、フェーズごとに効果的な施策を配置します。
その際、チャネルごとに顧客体験の質やメッセージがばらつかないよう注意し、すべての接点で統一されたブランド体験を提供しましょう。これにより顧客はシームレスに行動でき、企業への信頼感も高まります。チャネルやプラットフォームの選択肢は日々進化するため、新しい媒体が登場した場合には柔軟に取り入れ、常に最適なタッチポイント構成を維持する姿勢も重要です。
STEP5 効果を検証し改善を繰り返す
最後に、実行した施策の結果を計測・分析し、改善サイクルを継続的に回します。重要なのは、勘や思い込みではなくデータに基づいて判断することです。課題が多い場合は優先順位をつけ、小さくても即効性のある改善から着手することで、短期間で成果を実感でき、社内の理解や協力も得やすくなります。
例えば、Web広告の成果が振るわなければ広告クリエイティブやターゲティングを見直す、店舗での接客満足度に課題があればスタッフ研修やサービスフローを改善するといった具合に、一つひとつの接点を改善していきます。ここで重要なのは、個別最適にとどまらず顧客体験全体の最適化(全体最適)を目指す視点です。データを活用して顧客行動の変化を捉えつつ、部門横断で施策を調整し、あらゆるチャネルで常に質の高い体験を提供できるようにします。このような継続的な改善により、ブランド体験の向上と売上やLTVの持続的な伸長が期待できます。
マーケティング担当者として、「マーケティングプロセスという言葉は聞くけれど、具体的に何をすればいいのだろう?」と悩んでいませんか。
本記事は、企業のマーケティング担当者や初心者の方に向けて、マーケティングプロセスの基本から具体的な実践[…]
まとめ
マーケティングにおけるタッチポイントは、企業と顧客を結ぶ重要な接点であり、その設計と最適化がマーケティング成功の鍵を握ります。本記事では、タッチポイントの基本的な意味から始まり、BtoBとBtoCそれぞれの特徴や具体例、さらには効果的な戦略の立て方まで包括的に解説しました。
ポイントは、あらゆるチャネルを通じて顧客に一貫した良質な体験を提供し、適切な指標で成果を測定しながら継続的に改善を図ることです。タッチポイントを意識した施策を積み重ねていくことで、顧客との信頼関係が強化され、ブランド価値や売上の向上にもつながっていくでしょう。自社のマーケティング活動でも、本記事で紹介した考え方や手順を参考に、効果的なタッチポイント戦略を構築してみてください。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。