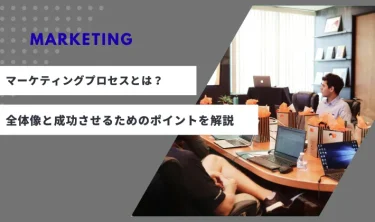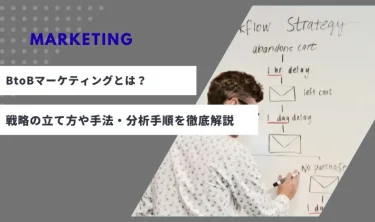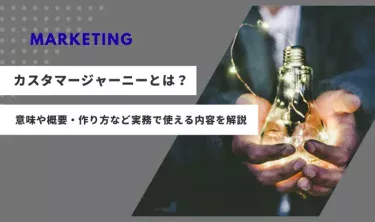自社のマーケティング活動において、「どの活動が本当に価値を生んでいるのか?」「どこに無駄が潜んでいるのか?」と悩んでいませんか。
本記事は、企業のマーケティング担当者に向けて、マーケティングバリューチェーンの基礎知識から分析の具体的なステップ、成功事例までを網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、自社のマーケティング活動を自信をもって分解し、改善すべき点と投資の優先順位を明確に示せるようになっているはずです。
バリューチェーンとは?
バリューチェーンとは、企業が製品やサービスを通じて顧客に価値を届けるまでの一連の活動を「鎖(チェーン)」のようにつなげて捉える考え方です。
活動は、製品を直接生み出す「主活動」と、それを支える「支援活動」に分かれます。
そして、マーケティングバリューチェーンとは、その中でも特に、顧客との接点(認知から購入、継続利用まで)に焦点を当てたものです。目的は、価値を生む活動にリソースを集中させ、価値を生まない、あるいは損なっている活動を見直すことにあります。
バリューチェーンの構成要素
バリューチェーンは「主活動」と「支援活動」で成り立っています。それぞれの活動が、マーケティング視点でどのような役割を担っているのかを下の表で確認してみましょう。
| 区分 | 活動 | マーケティング視点の要点 |
|---|---|---|
| 主活動 | 調達物流 | 仕入れ条件の最適化、リードタイム短縮、EC向け在庫精度の向上など。 |
| 主活動 | 製造・運用 | 顧客が求める価値と商品仕様の一致、テストから量産までの時間短縮など。 |
| 主活動 | 出荷物流 | EC・店舗受け取り・当日配送など、配送コストと顧客満足度の両立。 |
| 主活動 | 販売・マーケティング | 戦略設計(STP・4P)、顧客生涯価値(LTV)を最大化するための施策。 |
| 主活動 | アフターサービス | 返品ポリシー、サポート体制、顧客満足度(NPS)の向上など。 |
| 支援活動 | 調達(購買) | 取引先の選定、共同での販促企画、コスト削減など。 |
| 支援活動 | 技術開発 | 製品改良、データ基盤の構築、パーソナライズ技術など。 |
| 支援活動 | 人的資源管理 | スキル開発、営業やCS担当者の育成、適切な評価制度など。 |
| 支援活動 | 企業インフラ | 財務、法務、ITシステム、データ管理とプライバシー対応など。 |
重要なのは、顧客に届く価値は、単一の活動ではなく、これらの活動すべてが連動して生まれるという点です。鎖の最も弱い部分が、チェーン全体の強度を決めてしまうのと同じです。だからこそ、活動全体を俯瞰して捉える視点が不可欠になります。
サプライチェーンとの違い
サプライチェーンは「モノの流れ」に、バリューチェーンは「価値の発生」にそれぞれ主眼を置いています。両者は密接に関連しますが、問いかける視点が異なります。
| 観点 | バリューチェーン | サプライチェーン |
|---|---|---|
| 目的 | 価値創出と差別化の設計 | 供給と物流の最適化 |
| 主対象 | 活動全体と価値の連鎖 | 調達〜製造〜配送の流れ |
| 評価軸 | 顧客価値、利益、LTV | コスト、在庫、納期 |
| マーケティングへの示唆 | 価値の源泉を特定し、投資を配分する | 在庫や納期が顧客体験に与える影響を管理する |
ビジネスモデルとバリューチェーンの関係
ビジネスモデルが「誰に、何を、どう届け、どう収益化するか」という事業の設計図だとすれば、バリューチェーンはその設計図を実行に移すための具体的な活動計画です。
ビジネスモデルで描いた価値提案を、どの活動で作り、どの活動で伝え、どの活動で守るのかを具体的に落とし込みます。この連携が曖昧だと、せっかく広告費を投下しても期待した成果を得るのは難しくなります。
ビジネスモデル分析でバリューチェーンが重視される理由
ビジネスモデルを分析する上でバリューチェーンが重視される理由は、主に3つあります。
- 収益の源泉を特定できる:利益に最も貢献している活動を見つけ出し、そこにリソースを集中できます。
- 他社との差別化を仕組み化できる:個人のスキルに頼りがちな強みを、標準化された活動設計に落とし込み、組織としての強みに変えられます。
- コスト構造を可視化できる:広告費や物流費などを活動別に分解し、「受注1件あたりいくらかかっているのか」といった具体的なコスト構造を明らかにできます。
ビジネスモデルを語るだけで終わらせず、活動別の実行計画まで落とし込む。この一手間が、事業の成否を分けます。
バリューチェーン分析とは?
バリューチェーン分析とは、自社の活動を一つひとつ分解し、「どの活動が、どれくらいのコストをかけて、どれくらいの価値を生んでいるのか」を可視化する手法です。
分析を通じて、強化すべき活動、簡素化すべき活動、外部に委託すべき活動などを判断し、投資配分の意思決定と改善の優先順位を決めます。これは計画のための分析ではなく、具体的なアクションを起こすための分析です。
バリューチェーン分析の目的
バリューチェーン分析の目的は、大きく4つに整理できます。
- 価値を生み出している源泉の特定
- 価値を生まない無駄な活動の削減
- 競合他社との差別化ポイントの強化
- データに基づいた合理的な投資配分
例えば、広告費を増やすよりも、出荷までの時間を短縮する方が売上向上につながるケースがあります。これは、売上を阻害するボトルネックが広告ではなく、物流にあるためです。このように、活動別の事実を見て、最も効果的な場所にリソースを動かすこと。これがバリューチェーン分析の本質です。
バリューチェーン分析のメリット
バリューチェーン分析を行うことで、これまで感覚的に捉えていた自社の強みや課題を、数字と具体的な因果関係で語れるようになります。
メリット① 強み・弱みの可視化
自社の強みはどこで生まれているのか。それは製品開発力か、販売網の広さか、それとも手厚いアフターサポートか。活動単位で分解すれば、その源泉が明確になります。
例えば、「出荷リードタイムが業界標準より24時間短い」なら、それは明確な強みです。逆に「解約理由の30%がサポート対応への不満」であれば、そこが弱点です。強みはさらに伸ばし、弱みは仕組みで改善する。具体的な活動データに基づいて議論することで、組織内の合意形成もスムーズに進みます。
メリット② 競合との差別化を設計できる
競合が広告宣伝に強みを持つなら、自社は出荷のスピードやサポートの質で差をつける、という戦略的な選択が可能になります。
「当日出荷率95%」「チャットの初回応答60秒以内」といった体験価値は、広告費をかけただけでは簡単に真似できません。外部からは見えにくい活動に強みを作ることで、模倣されにくい持続的な競争優位性を築くことができます。
メリット③ コストを最適化し、利益を拡大できる
どのコストを削減すべきか、狙いを定めて判断できるようになります。闇雲に広告費を5%削るよりも、出荷プロセスを改善して遅延を1日短縮する方が、結果的に売上が8%伸びる、といったこともあり得ます。
このように、活動ごとの費用対効果を見極めることで、利益の最大化を図れます。
メリット④ 投資の優先順位が明確になる
予算は有限です。すべての活動に同じようにリソースを割くことはできません。バリューチェーン分析によって活動ごとのROI(投資対効果)を比較することで、どの活動に優先的に投資すべきか、データに基づいて判断できます。
例えば、短期的な売上増が目標なら購入に近い活動を、長期的な顧客関係の構築が目標ならアフターサポートなどを優先する、といった戦略的な意思決定が可能になります。
バリューチェーン分析の具体的な手順
バリューチェーン分析は、決まった手順に沿って進めることで、精度の高いアウトプットが期待できます。ここでは、実務で使える具体的な進め方を4つのステップで解説します。
1. 自社のバリューチェーンを洗い出す
まず、自社の事業活動を具体的なタスクレベルで洗い出します。例えば、「検索広告の運用」「LPの制作」「カートのUX改善」「在庫の引き当て」「出荷作業」「初期設定のサポート」といった形です。
なぜこの作業が必要かというと、活動の粒度を揃えることで、後のステップでコストや価値を公平に比較できるようになるからです。「1つの活動に、1人の責任者と、1つの主要KPI」という原則で整理し、活動の一覧表(台帳)を作成しましょう。
2. 各活動のコストを分析する
次に、洗い出した活動ごとに、どれくらいのコストがかかっているのかを算出します。人件費、ツールの利用費、広告費、配送費などを各活動に割り振ります。
このステップの目的は、「受注1件あたり」「出荷1件あたり」といった活動単位のコストを明確にすることです。同時に、その活動が生み出す価値(例:コンバージョン数、リピート率など)も定義し、コストと価値を並べて費用対効果を比較できるようにします。
3. 強み・弱みを分析する
活動ごとのKPIを、過去の平均値や業界のベンチマーク、競合の数値などと比較します。基準との差が大きい活動は、自社の強み、あるいは弱点である可能性があります。
次に、事業全体のボトルネックとなっている活動について仮説を立てます。例えば、「在庫引き当てのシステム化が遅れているため、出荷に時間がかかっている」といった形です。その上で、各課題のインパクト(売上や利益への影響)と実行の難易度を評価し、最も効果が高く、実現可能な施策から優先的に着手します。
4. VRIO分析で競争優位性を評価する
VRIO(ヴリオ)分析は、自社の経営資源がどれくらいの競争優位性を持っているかを評価するフレームワークです。各活動の背景にある資源(例:独自のデータ基盤、物流網、営業の育成プログラムなど)を、以下の4つの観点で評価します。
| 資源 | 価値 (Value) |
希少性 (Rarity) |
模倣困難性 (Imitability) |
組織 (Organization) |
競争優位性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独自の顧客データ基盤 | 高 | 中 | 中 | 高 | 競争均衡以上 |
| 全国のドライブスルー網 | 高 | 高 | 高 | 中 | 持続的優位の可能性 |
この分析を通じて、「価値が高く、希少で、真似されにくく、組織として活用できている」資源こそが、持続的な競争優位性の源泉です。これらを重点的に投資・保護すべき対象として特定します。
他のフレームワークとの組み合わせ方
バリューチェーン分析は、他のフレームワークと組み合わせることで、さらに分析の精度を高めることができます。
VRIO分析
VRIO分析は、活動の裏側にある「経営資源」の質を見極めるのに役立ちます。例えば、同じ「当日配送」という活動でも、その競争力は、基幹システム、物流拠点の配置、需要予測の精度といった資源の総合力で決まります。VRIOの観点を加えることで、表面的な活動だけでなく、その競争力の源泉となっている資源にまで踏み込んだ投資判断が可能になります。
ファイブフォース分析
ファイブフォース分析は、業界の収益性を決める5つの外部要因(競合、新規参入、代替品、買い手の交渉力、売り手の交渉力)を分析する手法です。
この分析によって、自社が置かれている業界の構造的な圧力を理解できます。例えば、買い手の力が強い市場では、販売やサポートといった下流の活動に依存しすぎると、価格競争に巻き込まれやすくなります。そこで、上流の技術開発やブランド構築といった活動で差別化を図り、交渉力を高めるといった戦略的な判断が可能になります。
バリューチェーン分析を成功させるポイント
分析を成功させる鍵は、計画の完璧さよりも、スピーディーな意思決定と実行にあります。
自社の状況に合わせてカスタマイズする
教科書通りのテンプレートをそのまま使うのではなく、自社のビジネスモデルや組織の状況に合わせて、分析の粒度を調整することが重要です。
例えば、SaaSビジネスであれば、顧客の定着に関わる「オンボーディング」や「活用促進」の活動を細かく分解します。活動名は現場で使われている言葉で定義し、責任者とKPIを明確にすることで、分析結果が現場の具体的なアクションにつながりやすくなります。
分析のタイミングを見極める
四半期ごとの計画策定や、予算の再配分、価格改定といった経営の意思決定が必要なタイミングで分析を行うのが効果的です。
また、毎月すべての活動をチェックするのではなく、売上や利益、解約率といった重要指標に大きな動きがあった際に、関連する活動を深掘りする形が現実的です。経営層の関心事と分析テーマを連動させることで、分析活動そのものが形骸化するのを防げます。
【業界別】バリューチェーンの特徴
業界によって、価値が生まれやすい活動や、ボトルネックになりやすい活動は異なります。ここでは代表的な3つの業界を例に、その特徴を比較します。
| 業界 | 価値が生まれやすい活動 | ボトルネックになりやすい活動 | 注力すべきKPIの例 |
|---|---|---|---|
| 製造業(BtoB) | 設計・試作、品質保証、技術営業 | 調達や見積もりのリードタイム | 見積もり回答時間、再注文率 |
| 小売業(BtoC) | 商品仕入れ、店舗での見せ方、配送体験 | 在庫の引き当て、返品処理 | 当日出荷率、在庫回転率 |
| SaaS(BtoB/BtoC) | オンボーディング、活用促進、カスタマーサポート | 初期設定、データ移行 | 初回価値の達成率、アクティブユーザー率 |
バリューチェーン分析の活用事例
実際の企業がどのようにバリューチェーンを活用しているのか、具体的な事例を2つ紹介します。
スターバックス
スターバックスの価値の源泉は、主活動における「心地よい店舗体験」と、それを支える支援活動の「バリスタ育成」にあります。
彼らは分析を通じて、混雑時の待ち時間が顧客満足度を下げているという課題を特定しました。そこで導入したのが「モバイルオーダー」です。これにより、顧客の待ち時間を短縮し、客単価と回転率を同時に改善することに成功しました。これは、プロモーションという単体の活動ではなく、商品企画から店舗オペレーションまでが連動して価値を生んだ好例です。
IKEA
IKEAの強みは、主活動における「セルフサービス型の店舗オペレーション」と「フラットパック(平たい梱包)による物流」にあります。これを、支援活動である高い「デザイン力」と「調達力」が支えています。
彼らは、ショールームからレジ、配送までの顧客の行動を分析し、商品の積み込みなどが負担になっていることを発見。オンラインストアでは在庫表示と配送予約を連携させることで、購入の機会損失を防ぎました。広告費に頼るのではなく、活動設計の最適化によって売上を伸ばした代表的な事例です。
DXとバリューチェーンの関係
DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質は、単にデジタルツールを導入することではなく、デジタル技術を活用してビジネスの価値提供プロセスそのものを再設計することです。その際、バリューチェーンはDXの「設計図」として機能します。
例えば、顧客データを統合して活動ごとの効果を正確に計測したり、AIによる需要予測で在庫を最適化したり、アプリでオンボーディングを自動化したりといった施策が考えられます。これらの施策は、活動の連鎖に沿って設計することで、その効果が乗算的に高まります。
よくある質問
バリューチェーン分析は中小企業にも有効ですか?
はい、有効です。むしろ、意思決定が速く、現場との距離が近い中小企業の方が効果を実感しやすいと言えます。
活動を10〜15程度に絞り込み、月次で1〜2つの改善を繰り返すだけでも、解約率や顧客評価に目に見える変化が現れます。限られた予算だからこそ、どこに投資すべきかをデータで示すことが重要になります。
バリューチェーン分析はどのタイミングで行うべきですか?
期初の計画策定や、四半期ごとの見直し、価格改定といった経営判断の前が最適なタイミングです。
毎月すべての活動を網羅的に見直す必要はありません。売上などに大きな変化があった際に、関連する活動を「点」ではなく「線」で捉えて分析することで、真の原因特定につながります。
SWOT分析など他の分析手法との違いは何ですか?
SWOT分析が、内外の環境を広く見て戦略の「仮説」を立てる手法であるのに対し、バリューチェーン分析は、活動レベルで価値とコストを点検し、具体的な「実行計画」を作る手法です。
先にSWOT分析で大まかな方向性を定め、その後にバリューチェーン分析で具体的なアクションに落とし込む、というように併用するのが効果的です。
まとめ
マーケティングバリューチェーンは、顧客価値と利益を生む活動を一つの連鎖として捉え、最適化していくための考え方です。
分析の手順はシンプルです。
- 活動全体を洗い出す
- コストと価値を分析する
- 強みと弱みを見極める
- VRIO分析で資源を評価する
- 投資の優先順位を決める
重要なのは、鎖の最も弱い輪を見つけ、そこを鍛えることです。それだけで、売上と顧客体験は着実に改善します。まずは自社の活動を一覧にすることから始めてみてください。次の四半期には、きっとデータに基づいた自信のある提案ができるようになっているはずです。
ナレブロについて

「ナレブロ」は、ナレッジブログ(Knowledge Blog)の略称です。運営者自身が実務を通じて培ってきた知見や経験(ナレッジ)を惜しみなくアウトプットし、読者の皆さまに還元することを目的としています。
現代において、真に価値のある情報の多くはクローズドな場所に偏っています。だからこそ本ブログでは、オープンなプラットフォームでありながら、実戦で役立つ高鮮度な情報発信を追求しています。「マーケティング」や「スキルアップ」の知見を提供することで、志高く働く方々の「近道」となる。それがナレブロの運営理念です。
関連ページ:コンテンツ制作・運営ポリシー