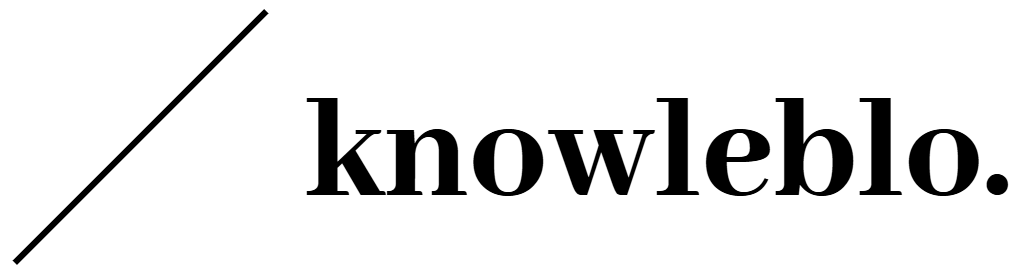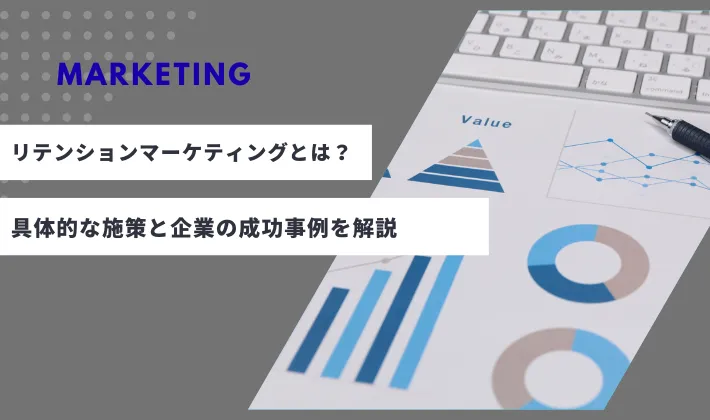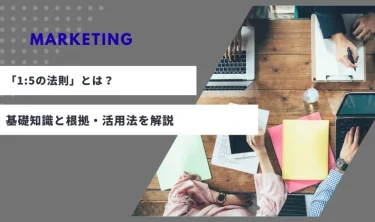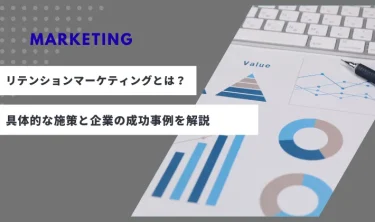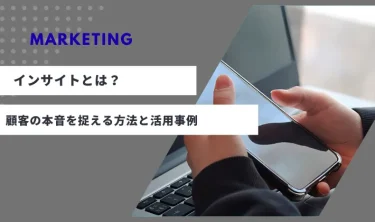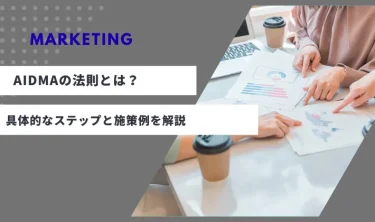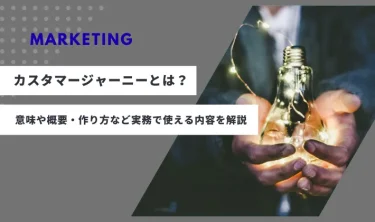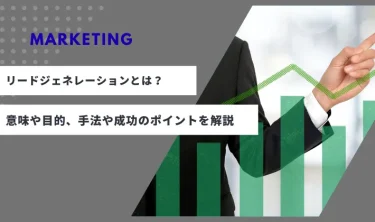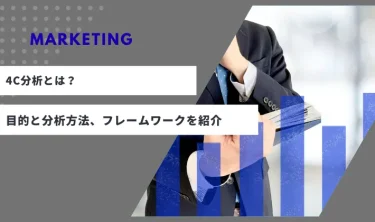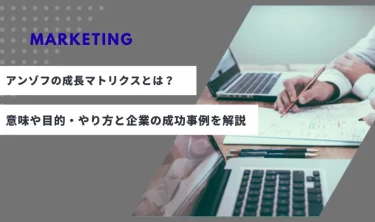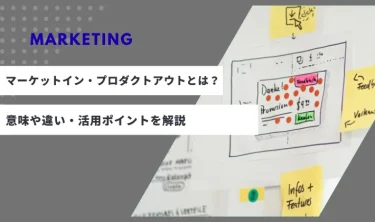リテンションマーケティング(Retention Marketing)は、既存顧客との関係を深め、継続的な売上を生み出すためのマーケティング手法です。新規顧客の獲得コストが上昇するなか、リピート率を上げてLTV(顧客生涯価値)を高めることが企業の成長に直結しています。
この記事では、リテンションマーケティングの基本から施策、KPI設定、成功事例、最新トレンドまで体系的に解説します。マーケティング初心者でも理解しやすいように、図や事例を交えて丁寧に紹介します。
リテンションマーケティングとは?
リテンションマーケティングとは、既存顧客との継続的な関係構築を目的としたマーケティング手法です。
具体的には、既存顧客に繰り返し購入・利用してもらったり、長期契約につなげたりするための施策全般を指します。そもそもマーケティングの目的は、大きく「新規顧客の獲得」と「既存顧客との関係維持」に分けられますが、リテンションマーケティングは後者に焦点を当てたものです。なお、「Retention(リテンション)」という言葉には「維持」や「保持」という意味があり、その名の通り顧客維持のためのマーケティングがリテンションマーケティングだと言えます。
また、マーケティング領域でのリテンションは「既存顧客の解約防止(顧客維持)」という意味合いで使われる用語です。たとえば購入後のメールフォローや、Webサイト上でのレコメンド表示、お得な会員向けキャンペーンの提供、アフターサポートの充実といった施策がリテンションマーケティングに該当します。
こうした取り組みによって顧客との信頼関係を高め、結果的に企業の収益向上につなげることがリテンションマーケティングの狙いです。
リテンションマーケティングが注目される理由
近年、多くの企業がリテンションマーケティングに注力し始めています。その背景には以下のような社会的・経済的な理由があります。
国内市場の縮小と競争激化
日本では2011年をピークに総人口が減少傾向にあります。総務省統計局のデータによれば、2011年以降日本の人口は明らかに減少に転じており、少子高齢化により今後も減少が加速すると予想されています。人口減少に伴い国内の新規顧客獲得は以前より難しくなっており、限られた顧客層の中でビジネスを成長させるには既存顧客の維持・活用がこれまで以上に重要になっています。新規顧客の奪い合いが激しくなる中、既存顧客との関係強化によって安定した売上を確保しようという動きが高まっています。
新規顧客の獲得コスト増大
新規開拓にかかる広告費や販促費が年々上昇していることも一因です。ある調査では、新規顧客獲得のためのコストは既存顧客維持のコストの5倍にもなると報告されています。実際、顧客に商品を知ってもらい購入に至るまでには広告出稿や見込み客の育成など長いプロセスが必要で、その分コストもかさみます。一方、既存顧客であれば商品理解や信頼関係がある程度構築されているため、比較的低コストで追加の提案や販売が可能です。この「顧客獲得費用1:5の法則」とも呼ばれる原則からも、新規顧客ばかりに注力する非効率さが浮き彫りになっています。
マーケティング業界でよく耳にする「1:5の法則」をご存じでしょうか。
これは新規顧客よりも既存顧客を大切にすることでコスト削減や利益向上につながるという法則です。企業のマーケティング担当者で、専門用語に不慣れな初心者の方でも安心してく[…]
サブスクリプションモデルの浸透
サブスクやSaaSなど継続課金型のビジネスモデルが普及したことで、「顧客に長く使い続けてもらう」こと自体が収益の鍵となっています。単発の販売よりも、ライフタイムバリュー(LTV)を最大化する戦略が重視されるようになり、そのためにもリテンションマーケティングへの注目が集まっています。質の高い顧客体験を提供し続けて解約を防止することが、サブスク型ビジネスの成長には不可欠だからです。
以上の理由から、既存顧客を大切にし関係を深めるリテンションマーケティングは、現在の市場環境で非常に重要性が増していると言えるでしょう。新規顧客の獲得が難しく高コストな時代だからこそ、「今いるお客様に継続利用・追加購入してもらう」戦略に改めて光が当たっています。
リテンションマーケティングのメリット
リテンションマーケティングに取り組むことで、企業は様々なメリットを得られます。主なメリットは以下の通りです。
収益の安定化とLTV向上
既存顧客との関係強化は、安定した収益基盤の構築につながります。クロスセル(関連商品の提案)やアップセル(上位商品の提案)を行うことで1人当たり顧客生涯価値(LTV)の向上が期待でき、結果として長期的な売上安定に寄与します。また、一度確立した顧客との信頼関係や販売ノウハウは他の顧客にも応用できるため、ビジネス全体の底上げにもつながります。
新規開拓より低コスト・高効率
前述の通り、新規顧客の獲得には既存顧客維持の約5倍のコストがかかるといわれています。既存顧客への追加販売であれば、すでに商品や企業への理解がある分、最初から提案やキャンペーンの効果を伝えやすく、高い利益率で販売できます。実際、「新規顧客への販売コストは既存顧客の5倍」というマーケティングの1:5の法則も広く知られており、新規獲得偏重の戦略がいかに非効率かが指摘されています。既存顧客へのアプローチは、企業にとって費用対効果の高い成長手段と言えるでしょう。
顧客の離脱防止と休眠顧客の再活性化
リテンション施策を講じることで解約や離反の防止にもつながります。既存顧客が離れてしまう原因を分析し対策することで、今いる顧客の満足度向上と離脱抑止が可能です。例えば定期フォローや満足度調査を行い不満点を早期に解消すれば、顧客の解約リスクを下げられます。また、しばらく利用が途絶えている休眠顧客に対しても、限定クーポンの配布や利用方法の案内などで再度アプローチできます。休眠客の掘り起こしによって「失われた売上」を復活させられる点も、リテンションマーケティングの大きな利点です。
ロイヤル顧客化による紹介効果
満足した既存顧客は企業のファンとなり、口コミや紹介を通じて新たな顧客獲得にも貢献します。リテンションマーケティングを通じて顧客ロイヤルティ(愛着や信頼)が高まれば、SNS投稿やレビューで自社を薦めてくれるケースが増え、間接的に新規顧客を生み出す効果も期待できます。このように既存顧客を大切にすることが新規顧客増にもつながる点も見逃せません。
以上のように、リテンションマーケティングには「一石二鳥以上」のメリットがあります。既存顧客への注力は売上・利益の拡大だけでなく、顧客満足度向上やブランド忠誠度向上、新規顧客獲得の効率化など多方面に好影響をもたらします。
なお、データからもその有効性が示されています。例えば既存顧客への販売成功率は60〜70%と高い一方、新規顧客へのそれは5〜20%程度にとどまるという調査結果もあり、既存顧客重視の重要性が数値的にも裏付けられています。
リテンションマーケティングの具体的な施策
リテンションマーケティングを実践する方法には様々なものがあります。ここでは代表的な施策を紹介します。それぞれ自社の顧客ニーズに合わせて組み合わせることがポイントです。
SNSによる情報発信と交流
TwitterやInstagramなどのSNSを活用し、自社の商品・サービスに関する有益な情報発信や、企業の身近さを感じてもらう社内ストーリーの共有、口コミ投稿への返信などを行う方法です。SNSの拡散力を生かして顧客とのエンゲージメントを高めると同時に、新規顧客の獲得にもつながる効果が期待できます。実際、有益な情報提供を続けてファンとの関係性を築くことで、顧客ロイヤルティの向上や紹介の増加につながります。
メールマーケティングによる定期フォロー
既存顧客に対して定期的にメール配信を行う施策です。すべての顧客に一律の内容を送るのではなく、購買履歴や興味関心に応じて内容をセグメントしパーソナライズすることで高い効果を発揮します。例えば「初回購入から日が浅い顧客には使い方ガイドを送る」「一定期間購入がない顧客にはクーポンを送る」といったように、顧客の状況に合わせたメールを送信します。メール送信後は開封率やクリック率、再購入率などを計測して効果検証・改善を行い、継続的に精度を高めましょう。
ロイヤルティプログラム・クーポン施策
購買頻度や累計購入額が高い優良顧客に対して特典を提供するロイヤルティプログラムを導入したり、離れてしまった休眠顧客に限定クーポンを配信したりする施策です。たとえば会員ランク制度やポイント還元、誕生日クーポンの発行、顧客限定セールの開催などによって、「常連でいるほどお得になる」仕組みを作ります。これにより顧客の継続利用意向を高め、競合他社への乗り換えを防ぐ効果が期待できます。特に休眠顧客向けの割引クーポンは、もう一度自社に注意を向けてもらうきっかけとして有効です。
パーソナライズされたレコメンド
顧客一人ひとりの購買履歴や閲覧履歴に基づき、興味を持ちそうな商品やコンテンツをレコメンド(推薦)表示する手法です。Amazonの「この商品を見た人はこんな商品も見ています」「あなたへのおすすめ」機能はその典型例です。適切なレコメンドにより顧客の関心にマッチした商品提案ができれば、上位サービスの利用(アップセル)や関連商品の追加購入(クロスセル)につながります。レコメンド機能は専用ツールを導入して行うのが一般的で、効果測定レポートなどの機能が付いたものを選ぶと分析と改善が容易です。
プッシュ通知(アプリ向け)
スマートフォンアプリを提供している場合は、プッシュ通知も有効なリテンション施策です。アプリをしばらく起動していない休眠ユーザーの画面に、期間限定セールや本日限定キャンペーン情報などを通知して再利用を促します。メールと違いアプリを開かなくても情報を届けられるため、開封率が高く休眠顧客の呼び戻しに最適です。ただし通知の送りすぎは逆効果になり得るため、内容や頻度のチューニングが重要です。
カスタマーサポートの充実
購入後の問い合わせ対応やサポート体制を整えることも欠かせません。顧客と良好な関係を築くにはアフターフォローが重要であり、質問や不満を迅速に解消することで顧客満足度が高まります。メールや電話対応に加えて、最近ではLINE公式アカウントやチャットボットでのサポート提供も効果的です。困ったときにすぐ相談できる環境を用意することで信頼感が生まれ、「またこの会社を利用したい」という気持ちにつながります。
カスタマーサクセスの取り組み
近年注目されるカスタマーサクセスとは、顧客が自社商品・サービスを通じて成功体験を得られるよう能動的に支援する活動です。単に問題発生時に対応するサポートに留まらず、活用促進の提案や定期的なチェックインを行い、顧客が期待以上の価値を得られるよう伴走します。この取り組みは顧客ロイヤルティの向上に直結し、結果的に解約率の低下やLTVの最大化に寄与します。「顧客の成功なくして自社の成功なし」という姿勢で、積極的に顧客をサポートすることが重要です。
オフラインイベントの開催
顧客参加型のワークショップやセミナー、ユーザー同士の交流会、新製品の体験イベント等を開催し、直接コミュニケーションを図る方法です。オンライン施策に比べ拡散力は劣りますが、対面での体験によって商品理解が深まりやすく、強い愛着やコミュニティ意識を育みやすいという利点があります。オフラインイベントで顧客同士が悩みを相談し合ったり、体験を共有したりすることで、自社への信頼感を一層高めることができます。得られた顧客の声を商品改善に活かすこともできるでしょう。
データ分析ツールの導入(CRM活用など)
リテンション施策を効果的に行うには顧客データの収集・分析が欠かせません。そこでCRM(顧客関係管理)やDMPなどの専用ツールを導入し、顧客属性や購買履歴、Web行動データを一元管理・分析する企業も多いです。これにより顧客セグメントごとの行動傾向や離脱リスクを可視化し、適切な施策をタイミング良く打つことが可能になります。分析ツール活用のメリットは、効率的なデータ収集・精度の高い分析・アプローチの自動化など多数あり、データドリブンに顧客維持策のPDCAを回せるようになります。
顧客フィードバックの収集と商品・サービス改善
既存顧客からの意見や要望を積極的に収集し、サービスに反映することも重要な施策です。アンケート調査やインタビュー、レビュー分析などを通じて顧客が感じている不満点や期待を把握し、迅速に改良を加えます。こうした顧客の声を取り入れた改善を続けることで、顧客満足度が向上し離脱防止につながります。実際にアンケートで得た声をサービス改善に結びつけ、顧客から「自分の意見を汲んでくれた」と評価されリピート率が向上した企業もあります(※後述の星野リゾートの事例など)。顧客にとって「自分の体験がどんどん良くなっていく」サービスは愛着が湧き、長期利用してもらいやすくなるのです。
以上のように、リテンションマーケティングの施策は多岐にわたります。自社の業種や顧客層に適したチャネルを選びつつ、「常に顧客一人ひとりに合わせた最適なアプローチを心がける」ことが大切です。どの施策でも共通するのは、顧客のニーズを理解し信頼関係を深める姿勢で取り組むことに他なりません。
リテンションマーケティングの成功事例
実際にリテンションマーケティングを活用して成果を上げている企業の例を見てみましょう。
既存顧客に目を向けた施策がどのような効果をもたらすのか、代表的なケースをご紹介します。
NTTドコモ
通信大手のNTTドコモでは、従来の通信料収入中心のビジネスモデルから、顧客との関係強化によるLTV最大化モデルへの転換を図る中でリテンション施策が活用されました。約8,000万という膨大な顧客データベースをもとに、マーケティングオートメーション(MA)ツールを駆使して最適なチャネルでのパーソナライズドなキャンペーンを展開し、100パターン以上のシナリオ配信による継続的な検証・改善を実施しました。その結果、コンバージョン数が従来比12.5倍にまで増加するという大きな成果を上げています。ドコモの事例は、データに基づき顧客一人ひとりに合ったアプローチを行うことで、既存顧客の潜在ニーズを引き出し売上を飛躍的に伸ばした好例と言えるでしょう。
Netflix
世界最大級の動画配信サービスであるNetflixもリテンションマーケティングの成功企業です。同社ではユーザーの視聴履歴や視聴時間帯、利用デバイスなどの行動データを詳細に収集・分析し、個々のユーザーに最適なコンテンツをおすすめするアルゴリズムを強化しています。例えば「視聴傾向に応じたおすすめ作品の提示」や、ユーザー全体の嗜好データを活かしたオリジナルコンテンツの制作などを行い、サービスへの満足度を高めています。これらの取り組みによりユーザーの解約率(チャーンレート)を低下させ、LTVを向上させることに成功しています。Netflixのケースからは、データドリブンな顧客理解とパーソナライズがリテンション向上に直結することがわかります。
SmartHR(クラウド人事労務ソフト開発・BtoB)
中小企業向け人事労務SaaSで急成長したSmartHRは、既存顧客の解約率(月次チャーン)を約0.7%に抑えています。これは一般的なSaaS平均(月次2~3%とも言われる)を大きく下回る水準です。その秘訣は、解約した顧客への徹底したヒアリングによるサービス改善にあります。ユーザーが離れる理由を一つひとつ洗い出し機能改良に反映し続けた結果、当初2~3%あったレベニューチャーンレートが0.7%まで改善されたのです。例えば「○○の処理に時間がかかる」という声に対し工程を自動化するなど迅速な対応を行い、「自分たちの要望でサービスが良くなる」という利用企業の満足度向上と長期利用の促進に成功しました。
Sansan(クラウド名刺管理サービス・BtoB)
名刺管理SaaSのSansanも驚異的な顧客維持を実現しています。契約企業の月次解約率は0.6%程度と公表されており、これを支えているのが同社のカスタマーサクセス体制です。Sansanは2012年に日本企業でいち早く専門のカスタマーサクセス部門を設置し、企業規模別にチームを分けて導入企業ごとに伴走支援を行っています。利用状況のスコアリング(週次アクティブ率や名刺登録枚数などを100点満点評価)や理想活用パターンの提示、メール開封率や研修動画視聴率のモニタリングによる解約アラートの運用など、極めてきめ細かなプロアクティブ支援を実施。こうした徹底サポートにより利用企業は確実に成果を上げられるため、高い継続率を維持できています。実際、同社は契約あたり月次売上(ARPU)の向上と解約率低減によってLTVを最大化し、事業成長の原動力としています。
ZOZOTOWN(ファッションECモール・BtoC)
大手ファッション通販サイトのZOZOTOWNは、新規獲得だけでなく既存顧客の囲い込み施策にも積極的です。会員限定クーポンの配布や公式アプリでのプッシュ通知配信など様々なリテンション施策を展開しており、中でも有名なのが「ツケ払い」というユニークなサービスです。「ツケ払い」は商品注文から2ヶ月後まで支払いを延長できる後払い制度で、カートに商品を入れたまま購入を忘れて休眠化しがちなユーザーの購買確定率を高めることに成功しました。手元に資金がなくても購入手続きができるため、金銭的理由で離脱する顧客を減らし、ZOZOとの関係が途中で途切れないようにしているのです。これにより若年層を中心にリピート利用を促進し、同社の安定した成長に貢献しています。
星野リゾート(高級リゾートホテル運営・BtoC)
星野リゾートは国内外で高級旅館・ホテルを展開する企業で、リテンションマーケティングによってリピート率20%以上という高水準を達成しています。具体的な施策としては、宿泊客へのアンケート調査を通じてサービスへの意見を収集・改善し続けている点が挙げられます。寄せられた要望や不満は即座にデータ化・分析され、施設のサービス向上に活かされています。その上で、再訪したお客様には過去のアンケート内容や滞在履歴をスタッフが把握した上で接客を行い、一人ひとりに最適なおもてなしを提供しています。例えば前回の宿泊時に「枕の硬さ」の好みを聞いていれば次回はあらかじめ用意するといったOne to Oneの対応で顧客満足度を高め、結果として高いリピート率を実現しているのです。
スターバックス(カフェチェーン・BtoC)
世界的コーヒーチェーンであるスターバックスは、日本国内でも顧客ロイヤリティの高さで知られます。同社が成功している背景には複数のリテンション施策の組み合わせがあります。まず会員向けのロイヤリティプログラム「Starbucks Rewards」では、来店購入ごとにポイント(Star)を付与し、貯まったポイントで無料ドリンクや限定グッズと交換できる仕組みを提供しています。このリワード制度により顧客は継続利用のメリットを感じ、来店頻度の向上につながっています。また、スターバックスはパーソナライズされたマーケティングにも注力しており、顧客の購買履歴や嗜好データに基づいて「お気に入り商品〇〇の割引クーポン」や誕生日特典を個別に配信します。顧客は「自分だけの特別なオファー」を受け取ることで優遇されていると感じ、ブランドへの愛着とリテンションが向上します。さらにモバイルアプリの活用も重要な要素です。アプリから事前注文・決済ができ、ポイント管理や限定オファー確認も容易なため利便性が高く、顧客体験を向上させています。加えて、店舗ではバリスタの丁寧な接客や居心地の良い空間づくりに力を入れており、総合的に高品質な顧客体験が長期的なロイヤルカスタマーを生み出しています。これらの施策を組み合わせたスターバックスの戦略により、多くの顧客が長年にわたり同ブランドを利用し続ける好循環が生まれています。
このように国内外のトップ企業も積極的にリテンションマーケティングを取り入れ、顧客維持による事業成長を実現しています。自社の規模や業界に合わせて施策を工夫すれば、中小企業でも十分に応用可能な戦略と言えるでしょう。
リテンションマーケティングを成功に導くポイント
リテンションマーケティングの効果を最大化するためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。以下に成功のための重要なポイントをまとめます。
成果指標(KPI)の明確化
施策の成否を判断するために、何をもって成功とするかを定量的に定めておく必要があります。例えば「リテンションレート(既存顧客維持率)」や「チャーンレート(解約率)」「LTV(顧客生涯価値)」などが代表的な指標です。期間ごと(例:月次や四半期)にこうした指標をモニタリングし、リテンション施策実施前後でどのように数値が変化したかを検証しましょう。明確なKPIがあれば、改善の必要性や投資対効果を判断しやすくなります。
顧客データの収集と分析
リテンション施策立案の第一歩は、「自社の顧客を深く知る」ことです。顧客の属性(年齢・性別など)、過去の購買履歴、Webやアプリの利用状況、問い合わせ履歴…といったデータを可能な限り収集・蓄積し、分析できる基盤を整えましょう。ところが実際には、データを集めていなかったり部署ごとに分散して有効活用できていなかったりするケースも少なくありません。そのため、少人数の顧客ならExcel等で一元管理し、数が多い場合はCRMツールや顧客データベースを導入するなどして、データを活用できる状態にすることが大切です。質の高いデータ分析により、初めて的確なリテンション戦略を描くことができます。
顧客セグメントの分類と最適化
集めたデータを基に顧客をグループ分け(セグメンテーション)し、セグメントごとに最適な施策を立案・実行することが成功の鍵です。例えばRFM分析(Recency:最終購入日、Frequency:購入頻度、Monetary:累計購入額)を用いて「優良顧客」「休眠顧客」「新規顧客」などに分類し、それぞれに響くアプローチを考える手法があります。優良顧客にはアップセル目的の特別オファーを、休眠顧客には復帰を促すご案内メールを、といった具合に顧客の状態・ニーズに合わせて施策を変えることで効果が最大化します。属性や行動データに応じて一人ひとりに刺さるコミュニケーション戦略を設計することが重要です。この際、担当者の勘だけに頼らずデータに裏付けられた客観的なセグメント分けを行うことで、より精度の高いターゲティングが可能になります。
マーケティング戦略で成果を求められる企業の担当者に向けて、マーケティングセグメンテーションの基本から具体的なやり方までを解説する記事です。市場を細分化して顧客をいくつかのセグメント(顧客グループ)に分け、それぞれに最適な戦略を立てることで、[…]
適切なツールの活用
顧客分析やセグメント別施策の実行には、マーケティングオートメーション(MA)やCRMなどの専用ツールを活用すると効率的です。顧客情報の一元管理や行動データの自動トラッキング、メール配信の自動化、効果測定レポートの作成など、人手では大変な作業もツールが支援してくれます。特に顧客数が多い企業では、ツール導入によって担当者の負荷を減らしつつ精緻なリテンション施策が展開できるでしょう。ただしツールはあくまで手段なので、前述のような戦略設計(KPI設定やセグメント分析)をしっかり行った上で使いこなすことが大切です。
継続的な検証と改善
リテンションマーケティングは一度やって終わりではなく、PDCAサイクルを回して継続的に改善することが成功への近道です(※PDCA: 計画→実行→評価→改善のサイクル)。定期的に主要指標をモニタリングし、計画した施策が想定通りの効果を上げているか評価します。もし目標に届いていない場合は施策内容を見直し、別のアプローチを試すなど改善策を講じます。例えばメールの開封率が低ければ件名や配信対象を変えてテストする、ロイヤルティプログラムの参加率が低ければ特典内容を再検討するといった具合です。仮説検証を繰り返しながらブラッシュアップしていく姿勢が、リテンション施策成功の大きなポイントです。
以上の点を意識することで、リテンションマーケティングの取り組みを効果的に進めることができるでしょう。「成果指標の明確化」「顧客分析の徹底」「セグメントに応じたアプローチ」の3点は特に重要です。言い換えれば、ゴールを定め、顧客を知り、その顧客に合った施策を実行するという基本を忠実に行うことが成功への近道です。
まとめ
新規顧客の獲得競争が激化する時代において、リテンションマーケティングは企業の持続的成長に欠かせない戦略となっています。既存顧客との信頼関係を維持・強化し、顧客一人ひとりに寄り添った価値提供を続けることで、安定した売上と高い顧客ロイヤルティを実現できるからです。リテンションマーケティングは「LTVの向上」「費用対効果の良さ」「休眠顧客の掘り起こし」「ロイヤル顧客の創出」といった観点から企業成長に大きく貢献し得ます。
重要なのは、顧客の期待を常に上回る価値を提供し続けることです。顧客との関係維持とは裏を返せば「顧客から選び続けてもらうこと」であり、そのためには購入前後を通じて期待を超える体験を提供し続ける努力が求められます。で解説されているように、顧客に今以上の価値を提供し続けることこそが利益の最大化につながる近道と言えるでしょう。リテンションマーケティングに取り組む際は、目先の売上だけでなく長期的な信頼と顧客満足の積み重ねを意識してください。それが結果的に自社のブランド力を高め、新規顧客からも選ばれる好循環を生み出します。
顧客との関係構築にゴールはありません。継続的に顧客の声に耳を傾け、ニーズの変化に対応し、施策を磨き上げていくことで、競争環境の中でも揺るぎない顧客基盤を築くことができるでしょう。ぜひ自社でもリテンションマーケティングを戦略に取り入れ、「お客様に選ばれ続ける企業」を目指してみてください。信頼関係に根ざしたマーケティングは、必ずや御社の大きな強みとなるはずです。
ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。